一流ジャズミュージシャンの名言!一筋縄ではなかった

「みんな、正直になろう。スタンみたいに吹けるのならば、吹きたいだろう?」 ジョン・コルトレーン
ジョン・コルトレーンと言えば、説明不要なジャズ界随一のテナーサックス奏者です。そのコルトレーンにして「彼のように吹きたい」と言わせた「スタン」というのは、白人テナーサックス界の最高峰「スタン・ゲッツ」その人です。ジョン・コルトレーンがジャズ界に残した業績は、ジャズ界にとっては、最大級の偉業です。初期、中期、後期、最晩年に至るまで進化し続けたコルトレーンのスタイルは、いまだにジャズ界に影響を与え続けていると言ってよいでしょう。
そのジャズ界を疾走したあまりに激烈なスピードは、リスナーはもちろん、音楽業界自体も対応できないほど変化に富んだものでした。特にコルトレーン後期に所属したレーベル「インパルス」時代は、激烈なモードからフリーに至った時期。コルトレーンは終生ポピュラーな人気を得ることはありませんでした。当時から現在に至るまでコルトレーンの名声は、限られたジャズ界だけでのものだったのです。
一方、白人の二枚目テナー奏者スタン・ゲッツは早くより成功し、そのまま出世街道を驀進、MGMなどの大手メジャー・レーベルと契約(レーベルはヴァーヴ)してレコードは売れまくりました。実力はもちろんですが、ボサノヴァの大ヒットで人気と収入はジャズ界でも群を抜く高さに。そのソフトな音楽は世界中のポップス・ファンにまでアピールしました。
ところが、ことスタンの評判となると、スタンの性格上の問題もあり、ミュージシャン仲間の間でさえ、決して良いものではありませんでした。当然、ねたみや嫉妬の対象としても格好の的だったのです。
そんな中、プレイ・スタイルや人柄などあらゆる点で正反対なコルトレーンが発したこの言葉「みんな、正直になろう。スタンみたいに吹けるのならば、吹きたいだろう?」は、スタンの流麗なスタイルや実力を素直にリスペクトした、真面目なコルトレーンらしい名言です。
誰よりもコードに精通し、練習に練習を重ね「シーツ・オブ・サウンド」と言われた高度なテクニックで他を圧倒し、先鋭かつ峻烈な演奏でジャズ界を引っ張ったコルトレーン。そんな激しく厳しい音楽の一方で、「バラード」や「ウィズ・ジョニー・ハートマン」などの良質なバラードアルバムを吹きこんでもいるサックスの巨匠コルトレーンの言葉は、周りを黙らせるに十分な名言です。

「インプレッションズ」より「インプレッションズ」(Amazon)
トリルを多用した短いセンテンスで歌う後期コルトレーンの特徴的なソロのモード・ジャズの傑作。ソロが始まって8分を過ぎたあたりからオルタネイト・フィンガリング(サックスの構造上、違う指使いで同じ音を出すテクニック)による倍音(音の構造上、一つの音には違う音が同時に鳴っており、その違う音にフォーカスした状態)を使った音(スカスカ音が抜けるような効果)を多用し、そのまま15分間一気に疾走します。
そのコルトレーンのあまりの迫力に、この時一緒にステージにいたアルトサックスのエリック・ドルフィーはラストのテーマの1,2音しか吹けず、伴奏のマッコイ・タイナーは、途中からコンピングをやめ、ドラムとベースだけが必死にコルトレーンにくらいついていくしかなかったという激しい演奏です。
コルトレーンの峻烈さとは正反対のスタンスを貫いたそのスタン・ゲッツには次の言葉があります。
「ジャズってのは、結局はナイトミュージック(夜の音楽)なのさ。」スタン・ゲッツ
スタン・ゲッツほど、モダン・ジャズ期に人気と実力がリンクした幸福なジャズメンはいないと言ってよいでしょう。もし、すべてを兼ね備えた完璧なジャズメンは誰か?という問いに答えるとするならば、スタン・ゲッツは真っ先に名前が挙がるミュージシャンと言えます。「人気、実力、経済力、健康、無茶さ」の5つの視点ですべてにおいて他からぬきんでていると言えます。しかもそれにもかかわらず、決して人間性においてはバランスの良い人間ではなかったというところがジャズメン、スタン・ゲッツの面目躍如と言ったところです。
誰からもうらやましがられたスタンのジャズ・テナー人生で、最後の最後に録音された感動的な演奏がコチラ!

「ピープル・タイム・ザ・コンプリート・レコーディング」より「アイ・ウィッシュ・ユー・ラブ」(91年3月6日ヴァージョン) (Amazon)
この「ピープル・タイム」は、驚くべきことにスタンが亡くなる三か月前の演奏です。コペンハーゲンのジャズクラブ「カフェ・モンマルトル」において、1991年3月ピアノのケニー・バロンとのデュオで録音されたものです。この時すでに、スタンはガンを患って何年もたっている状態でした。先入観なしに耳を傾けると、大病を患っている人とは思えないほどの瑞々しい演奏が流れ出て、ただただ感嘆するばかりです。
演奏では、スタンのブレス(息遣い)も、しっかり録音され、必ずしも身体の状態は良くなかったことがわかりますが、スタンは命を音楽に変えるかのように、切々と恋の歌を歌いあげていきます。ここにきて、この色気を発揮できるスタンのテナーには、会場はもちろん、CDで聴いているこちらもうっとり聴きほれてしまうしかない演奏です。
このライブ音源は、先に二枚組「ピープル・タイム」として出されましたが、現在ではその時のすべての音源を聴くことができる「ピープル・タイム・ザ・コンプリート・レコーディング」が手に入ります。そして、この曲「アイ・ウィッシュ・ユー・ラブ」は全3ヴァージョンともこのコンプリート盤でしか聴くことができません。
3ヴァージョンともに素晴らしい出来ですが、今回ご紹介したこの最後の91年3月6日ヴァージョンはなかでも特にシンプル。最後にスタンがいたった境地に感動してしまいます。
スタン・ゲッツが生涯奏でたサックスの音色は、スタンの言葉通りの極上の「ナイト・ミュージック」です。
「いいぞ!もっとバカなことをやれ!」アート・ブレイキー
この言葉は、ドラムのアート・ブレイキーが新しくピアニストとして入ってきた若き日のキース・ジャレットに対してはなった言葉です。21歳のキースにとってジャズのメジャー・デビューとなったのがアートのバンド。当時流行のフリー・ジャズに触発されたキースがピアノの弦を直接かき鳴らすというようなことをすると、ドラム越しにアートはいつもこう怒鳴って励ましていたそうです。
アート・ブレイキーは、モダン・ジャズ・ドラムの巨匠であり、その派手なスタイルで多くの名演を残しました。そして、何よりもモダン・ジャズ期においては、「帝王」と呼ばれたマイルス・デイヴィスと二分するジャズ界の大勢力を持つボス的存在でした。
その新人発掘力と育成力は最上級のもので、ジャズ界の登竜門として、アートの元から大きく育ったミュージシャンは数多くいます。一例をあげると
トランペットでは、リー・モーガン、フレディ・ハバード、ウィントン・マルサリスなどなど。サックスでは、ハンク・モブレー、ジャッキー・マクリーン、ウェイン・ショーターなど。ピアノは、ホレス・シルヴァー、ボビー・ティモンズ、といったひとかどの面々。そして、めでたくメジャー・デビューを飾ったキース・ジャレットも短期間ではありますが、アートの薫陶を受けました。
アートが、その新人タレント養成に磨きをかけたアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズというバンドのはたした役割は大きく、そのきっかけとなった名盤がコチラです!

「バードランドの夜 VOL.1」より「スプリット・キック」(Amazon)
ここでは、ザ・ジャズ・メッセンジャーズの結成前夜に録音された熱い演奏が繰り広げられます。何と言っても目玉は、天才トランペッターのクリフォード・ブラウン。デビュー当時のクリフォードがいかに完成されたトランペッターだったかがわかる名演です。
アートは、その長いキャリアにおいて常に第一線にあって、超一流のミュージシャンと共演し、そして次々と新人を超一流へと育て上げていきます。その中の一人に上げられるピアニストのキース・ジャレットがザ・ジャズ・メッセンジャーズ在籍時にアートに言った名言がコチラです。
「アート、あいつらみんな下手だからくびにしちゃって!」キース・ジャレット
これは、キース・ジャレットが、アートのバンドにいた数か月の短い間に、何度となくアートに言った名言です。もちろん、アートによってこの進言は取り入れられることはなく、キースの方がすぐに退団してしまうことになりました。その時のことは、アートに言わせれば「学校で頭のいい生徒が、できの悪いクラスに入ってうんざりするようなものだった」という表現をしています。
この後すぐにサックス奏者のチャールズ・ロイドのバンドに入り、キースの快進撃が始まります。飛ぶ鳥を落とす勢いとはこういうことを言うのでしょう。それからのキースのジャズ人生は順風満帆、あっという間にジャズ・ピアニストの巨匠の仲間入りを果たします。
その時期の名盤は数限りなくありますが、今回ご紹介するのは、そんな活発で才気煥発なキースの作品の中で、一際目立つ「静」の作品です。
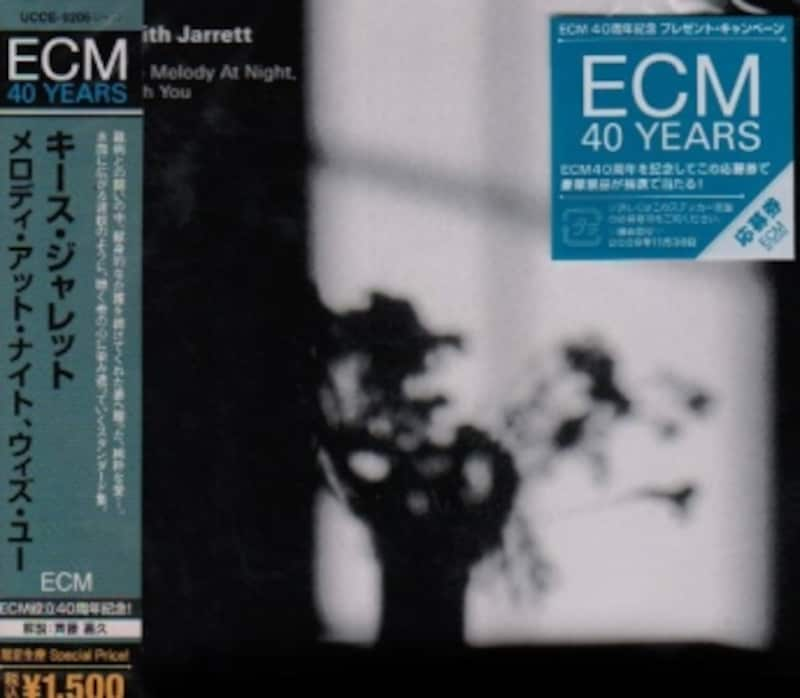
「ザ・メロディ・アット・ナイト・ウィズ・ユー」より「ビー・マイラブ」(Amazon)
奔放でやんちゃだった若き日を送ったキースも、1996年51歳にして大病を患います。この病により、人との接触はもちろん、ピアノも全く触れない状態に陥りました。おそらくはこの病が、キースの人生において初めての挫折であったと思われます。その状態は二年間も続き、その二年間を支えたのが妻のローズ・アン・ジャレットでした。
ローズの献身によって立ち直り、ようやくピアノを弾くことができるようになったキースは、その妻に捧げてとても優しいソロ・アルバムを制作しました。それがこの「ザ・メロディ・アット・ナイト・ウィズ・ユー」です。
ここでは、名盤とされる「ザ・ケルン・コンサート」などに代表される饒舌さではなく、淡々と静かにメロディを弾く新しいキースの姿があります。そこには慈愛とよろこびに満ちたメロディを聴きとることができます。
全曲に渡って、墨絵を思わせる枯淡の味わいの美しいメロディが続きますが、特に9曲目の「ビー・マイラブ」を聴いたあとは、そのメロディが頭から離れず、キースの震えるような心情を感じ取ることができます。
妻の献身にふれ、これまでの人生でかかわったすべての人に対して、感謝と優しい気持ちを持つに至ったのでしょう。周りの力を借り、病を克服して、キースはさらに音楽家としてのステージを上げたようです。
「マイケル、きみは今ぼくたちが聞いてみたかった疑問をコルトレーンに聞けるようになったんだね。」デイヴ・リーブマン
この言葉は、現代ジャズ・テナー界の巨匠と呼ばれたマイケル・ブレッカーの2007年1月の死去にあたって、同じくコルトレーン派の逸材と言われたデイヴ・リーブマンによって言われた言葉です。マイケルよりも三歳年長で、ジャズ界でも先輩にあたるデイヴ・リーブマンは、マイルス・デイヴィスのバンドや、コルトレーン・カルテットのドラマーだったエルヴィン・ジョーンズのバンドで名をはせたテナー&ソプラノ奏者です。
一時期ソプラノサックスしか吹いていない時期があり、ファンにとっては残念な思いをしていたものが、ついにテナー・サックスで一枚のアルバムを制作したのが、次に紹介するこのアルバムです。
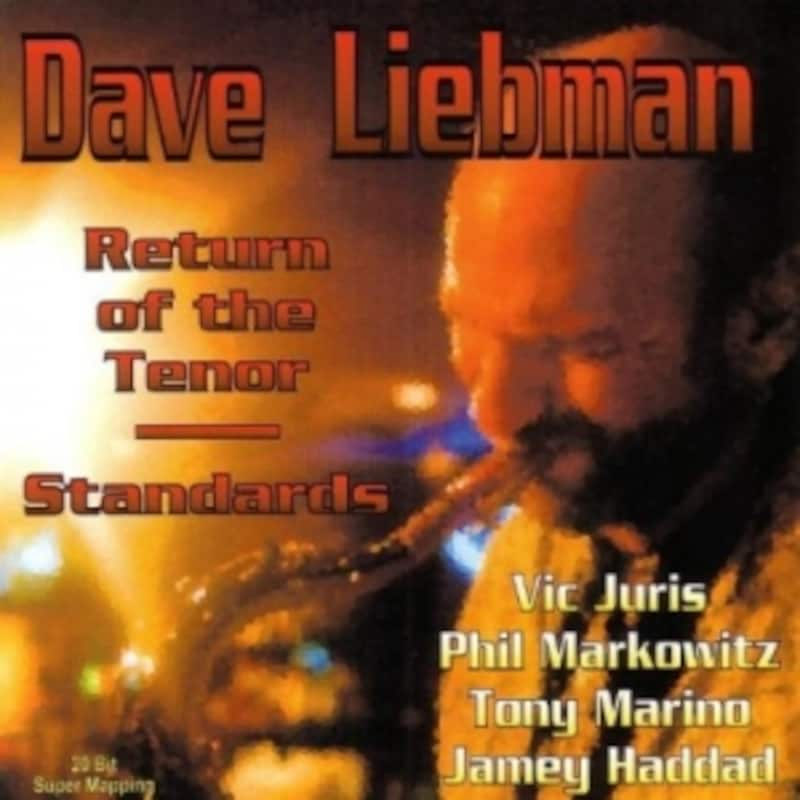
「リターン・オブ・ザ・テナー」よりオール・ザ・シングス・ユー・アー(Amazon)
長年に渡ってソプラノに専念し、テナーを封印していたデイヴ・リーブマンが、題名通りにテナーサックス一本でスタンダード・ソングに挑戦した好盤です。ハードで粘っこいテナーサウンドには、最近のジャズからは感じられない情念のようなオーラが漂い、聴きごたえがあります。
そのデイヴが選んだスタンダードが、大学のJAZZ研が喜びそうな馴染みのある選曲なのがうれしいところ。ジャズの教科書のようなスタンダード曲を、この1996年の吹き込み当時は丁度50歳を迎えたデイヴが、大人の男臭さ全開で奏でていきます。敬愛するコルトレーンにつかず離れず、自身の培ってきた歌を奏でるデイヴのサウンドは個性が際立ちます。
エルヴィン・ジョーンズのバンドでしのぎを削った盟友スティーヴ・グロスマンよりもややフリー・ジャズっぽく、後期コルトレーンの影響を感じさせ、その武骨なテイストが強烈にジャズを感じさせます。
そのデイヴが追悼を述べた、コルトレーン派の同門が、マイケル・ブレッカーです。
「僕は、キング・カーティスのようなサックスに惹きつけられるようになった。コルトレーンもファンクはやらなかったから(笑)」マイケル・ブレッカー
この言葉は、1980年にデイヴ・リーブマンと一緒にインタビューを受けた時のもの。マイケルはデイヴと一緒に、コルトレーンからの強い影響は認めながらも、自分なりのスタイルを模索している過程においてヒントとなったサックス、キング・カーティスについて言及しています。
キング・カーティスは、1971年に早逝してしまいますが、フュージョンの先駆けとなる斬新なアプローチを駆使した重要サックス奏者です。マイケルのソロの出だしを飾ることが多いファンキーなタッチは、自身でも語っているように。このキング・カーティスとキャノンボール・アダレイからの影響が明らか。
特にキング・カーティスからは、サックスにワウを使うことと、ブルーノート・スケールの使い方の特徴的な影響を受けています。フュージョン期のマイケルは、特にソロの出だしをブルーノート・スケールでブルース・ギターのようなベンディングを用いて始めることが多く、それは、キング・カーティスからの影響と言えます。
その上、この時期のマイケルのソロはロック・ギターからの影響も大きく、その点が他のサックス奏者と一味違う特徴となっています。それが顕著に表れた演奏がこの「ヘヴィー・メタル・ビ・バップ」からの「スポンジ」です。

ヘヴィー・メタル・ビバップ
ザ・ブレッカー・ブラザーズ「ヘヴィー・メタル・ビ・バップ」より「スポンジ」
この1978年の人気ライブ盤では、ギター奏者のバリー・フィナティと双子のようなソロを取るマイケルの姿が捉えられています。当時のバリー・フィナティは大変粋が良く、絶頂期ともいえる乗りのよさ。その上、フランク・ザッパで共演したドラムのテリー・ボジオも絶好調。ザッパ出身だけあって変拍子はお手の物の強力なドラミングで鼓舞します。
このアルバムは、このバンドの頂点ともいえるライブアルバムです。彼らの中でも特にロック寄りの内容になっており、マイケル・ブレッカーのファンキーさの本領発揮ともいえる快演です。後年ジャズの巨匠と呼ばれるようになるマイケルがサックスにワウをかましてやりたい放題大暴れする痛快な名盤と言えます。ロック好きにぜひ聴いてもらいたいアルバムです。
デイヴとマイケルの対談では、二人は謙遜してコルトレーンがサックスのすべてをやりつくしたと語っています。しかし、このギンギンのファンク・ロックのサウンドによって、マイケルはマイケルなりのサックスの新境地を切り開いたと言えます。そして、それはジャズ・サックス界においては新境地開拓の偉業と言ってよいでしょう。
ジャズメンのホンネ、名言・迷言集はいかがでしたでしょうか。心に響く言葉はありましたか?この他にもまだまだたくさんの金言がジャズ界には眠っています。機会を見て、どんどんご紹介していきますね。
【関連記事】








