税金・公的手当 人気記事ランキング(7ページ目)
2026年01月08日 税金・公的手当内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
61位医療費控除の対象になるもの・対象外のものとは?【動画で解説】
医療費控除の対象になるもの・医療費控除の対象外であるものをまとめました。インフルエンザなどの予防接種、コンタクトレンズ代、歯の矯正費用、感染症対策のPCR検査やマスク購入費まで……対象になるかどうかの基準とは?「医師の判断による、治療目的なら医療費控除の対象」ということになります。
 確定申告ガイド記事
確定申告ガイド記事62位医療費控除の確定申告はいつからいつまで?還付申告は「2024年1月」からできる【動画で期間・書類・やり方を解説】
2022年分の所得税について申告する2023年の確定申告期間は、2024年(令和6年)2月16日(金曜)~3月15日(金曜)です。1年間に医療費を多く払った人の税金が戻る「医療費控除」については、払い過ぎた税金が戻る還付申告なので確定申告期間ではなくても、1月から受け付けています。税務署が混まない1月中に申告してしまうのがオススメです。
 確定申告ガイド記事All About 編集部
確定申告ガイド記事All About 編集部63位確定申告書、扶養控除の「区分」欄には何を書く?
近年、税金の申告漏れを防ぐために、確定申告書の用紙には「区分」欄が増えています。扶養控除の記入欄にも、「区分」欄が設けられています。この欄に記入が必要となるのは適用対象扶養親族が国外居住親族である場合だけです。つまり国外留学、ホームステイ等をしている親族がいる場合に記入が必要となるわけです。
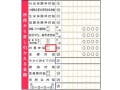 確定申告ガイド記事
確定申告ガイド記事64位老人扶養控除とは?祖父や祖母が対象「老人扶養親族」の要件【動画でわかりやすく解説】
70歳以上の祖父・祖母がいる人は、老人扶養控除の適用が可能かどうか確認し、適用ができるのであれば「扶養控除等(異動)申告書」に記載する必要があります。年末調整時の記載例も含め、「老人扶養親族」の仕組みや基準について解説します。
 年末調整ガイド記事
年末調整ガイド記事65位年末調整後、子どもの年収が扶養の範囲を超えてしまったら?
アルバイトする大学生の子どもがいるなど、子どもの年収が103万円以下であれば、親の「扶養」に入れていると思います。これにより親の税金負担が安くなっていますよね。ところが、年末調整書類を提出した後に、子どもが2つ以上のアルバイトを掛け持ちするなどして、103万円の年収を超えてしまったことが判明した場合は、税務署から会社に連絡がくる可能性があります。扶養是正となり、親は税金を追加で納付しなくてはなりません。
 年末調整ガイド記事
年末調整ガイド記事66位【配偶者控除】150万円の壁で家計はどうなる?
2018年1月から所得税の配偶者控除が変わりました。配偶者の年収上限「103万円の壁」が150万円に引き上げられたのです。この新制度で、私たちの家計にどのような影響があるのでしょうか?妻のパート年収と夫の年収条件などもチェックしておきましょう。
 税金ガイド記事
税金ガイド記事67位住民税課税証明書って何に使う?入手方法と申請方法
住民税課税証明書が必要となるのは、例えば扶養申請、児童手当の申請、あるいは子どもを保育所等に預けたりする場合など、住んでいる市区町村から何らかの行政サービスを受けるときです。この記事では、課税証明書には何が記載されているか、どこで申請するか、具体的な申請・請求方法、「納税証明」との違いなどについて解説します。
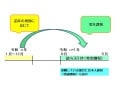 税金ガイド記事
税金ガイド記事68位住民税はいくら引かれる? 月収20万円の場合の住民税の計算方法
住民税がいくら引かれるのか知っていますか? 所得税と違って住民税の税額を把握している人は少ないもの。実際、月収20万円の人は、どれくらいの住民税を払うことになるのでしょうか? 独身の人と妻が専業主婦のケース別に住民税の均等割、所得割とを計算してみます。
 税金ガイド記事
税金ガイド記事69位一時所得を受け取ったときの確定申告はどうする?Go Toキャンペーンの助成金は?
生命保険の一時金、懸賞金や福引の当せん金、競馬や競輪の払い戻し金は「一時所得」とされ、確定申告の対象となる場合があります。一時所得の定義や計算方法、確定申告書の書き方を解説します。ふるさと納税の返礼品は?Go Toキャンペーンの助成金は?最新の一時所得事情についてもコチラで。
 確定申告ガイド記事
確定申告ガイド記事70位株の譲渡損失を繰越控除するには?申告書の記入例
株式の譲渡損失があれば、株式の譲渡益や配当所得と相殺でき、差し引き切れない場合には、翌年以降3年間、繰り越せます。同一の源泉徴収選択口座内であれば、上場株式の譲渡損失と配当所得を自動的に差し引きしてくれるのですが、譲渡損の繰越まではしてくれません。そんなケースの申告書の書き方を解説します。
 確定申告ガイド記事
確定申告ガイド記事