メンタルヘルス 人気記事ランキング(5ページ目)
2026年01月07日 メンタルヘルス内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
41位大切な人や身近な人の死を乗り越えるまで
大切な人を失ってしまったとき、通常はショック症状の強い時期、故人の事が頭から離れ難い時期を経て回復していきますが、その過程でうつ病などの心の病気が生じてしまうことがあります。大切な人や身近な人の死を乗り越える。喪失体験からの回復過程について医学的に解説します。
 死別・失恋・喪失感ガイド記事
死別・失恋・喪失感ガイド記事42位衝撃的な体験は心をどう変えるのか
交通事故、自然災害、暴力事件など生死に関わる体験をしたり、目撃した際の恐怖や無力感によって、心が大きなダメージを受け、急性ストレス障害が出現する事があります。
 強迫性障害・不安障害・パニック障害ガイド記事
強迫性障害・不安障害・パニック障害ガイド記事43位人前で演じてしまう自分に気付いていたら?
他人の注意を引きたいと思う事は誰にでも時にある事でしょうが、この傾向が強くなり過ぎた場合には心の問題がその傾向に拍車をかけている可能性がある事を詳しく述べます。
 その他の心の病気ガイド記事
その他の心の病気ガイド記事44位伝説のロック歌手の破滅への衝動
カリスマ的ロックシンガー、ドアーズのジム・モリソンは27歳の若さで急死しました。アルコールにドラッグと彼の私生活は破滅的でしたが、その背後には彼の人生に対する病的な絶望感がありました。
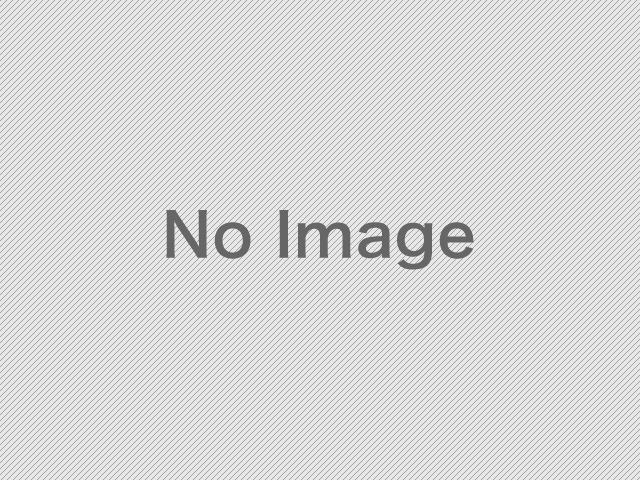 (読み物) 有名人と心の病気ガイド記事
(読み物) 有名人と心の病気ガイド記事45位統合失調型パーソナリティ障害の特徴・症状・治療法
統合失調型パーソナリティ障害は統合失調症と同様、現実認識力に問題が生じやすくなる病気。周囲の人からエキセントリックな印象を持たれがちです。統合失調型パーソナリティ障害の特徴、症状、治療法を詳しく解説します。
 パーソナリティ障害(人格障害)ガイド記事
パーソナリティ障害(人格障害)ガイド記事46位強迫性パーソナリティ障害の特徴・症状・治療法
【医師が解説】強迫性パーソナリティ障害は完璧主義的傾向が強くなり過ぎる、心の病気です。現実適応力が低下し、心の苦しみが大きくなってしまいます。強迫性パーソナリティ障害の特徴、症状、治療法を詳しく解説します。
 パーソナリティ障害(人格障害)ガイド記事
パーソナリティ障害(人格障害)ガイド記事47位自然災害への恐怖感が強すぎるとき
地震、台風など、自然災害に対する、心の備えは重要! とは言え、場合によっては、杞憂という言葉もあるように、不安、恐怖が不合理に近くなってしまう事があります。今回は、地震など自然災害に対する不安、恐怖感が強すぎる時の、対処法を詳しく解説します。
 心の病気の治療法・セルフケアガイド記事
心の病気の治療法・セルフケアガイド記事48位あなたも負のスパイラル?スマホ依存症の症状・治し方
現代の日常生活において、携帯、スマホはもはやなくてはならないツール。一方で、スマホをしすぎて実際の人間関係に問題が生じたり、健康な生活が損なわれている場合、「依存症」の状態に近くなっていることも考えられます。スマホ依存症の原因、症状、治し方について解説いたします。
 依存症(薬物依存症・アルコール依存症等)ガイド記事
依存症(薬物依存症・アルコール依存症等)ガイド記事49位焦る気持ちを落ち着かせる方法・心の不調の整え方
【医師が解説】気持ちが焦ると、日常生活でも思わぬ失敗をしてしまうもの。なぜか焦りが強くなってしまう理由と対処法を、精神医学的な側面から解説します。焦る気持ちを自覚して原因を見つけ、落ち着いた心を取り戻しましょう。
 心の病気の原因・症状・セルフチェックガイド記事
心の病気の原因・症状・セルフチェックガイド記事50位“見えない友達”、イマジナリー・フレンドとは?
イマジナリー・フレンドは、本人にしか感じることのできない想像上の友人です。しかし、本人はその友人が実際にいると信じています。イマジナリー・フレンドとは何なのか?病気との境目は?について解説します。
 その他の心の病気ガイド記事
その他の心の病気ガイド記事