暮らしの歳時記 人気記事ランキング(9ページ目)
2026年01月09日 暮らしの歳時記内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
81位二十四節気「啓蟄(けいちつ)」とは?2025年はいつ・意味や風物詩を解説
二十四節気のひとつ「啓蟄(けいちつ)」とはどんな日でしょう? 2025年の啓蟄の日はいつ? 啓蟄の虫って何? 春の季語としても使われ、季節を感じる啓蟄の意味や豆知識を紹介します。
 春の行事・楽しみ方(3~5月)ガイド記事
春の行事・楽しみ方(3~5月)ガイド記事82位「天高く馬肥ゆる秋」とは? ことわざの意味と実は怖い由来
「天高く馬肥ゆる秋」ということわざは秋の素晴らしさを表す意味で使われていますが、なぜ馬が登場するのでしょう? このことわざには怖い由来があり、秋になるとやってくる敵を警戒することばでした。今と昔では全然違う「天高く馬肥ゆる秋」の意味、由来、使い方について解説します。
 秋の行事・楽しみ方(9~11月)ガイド記事
秋の行事・楽しみ方(9~11月)ガイド記事83位【和食の豆知識】赤味噌・白味噌・合わせ味噌の違いとは? 沸騰させてはいけない味噌といい味噌がある?
【和文化研究家が解説】よく見聞きする「赤味噌」「白味噌」「合わせ味噌」にはどんな違いがあるのでしょうか? 「味噌汁を沸騰させてはいけない」といわれていますが、本当でしょうか? 「手前味噌」や「味噌を付ける」などのことわざの由来は? 日本の代表的な食文化である味噌の、知っておきたい豆知識を紹介します。
 ガイド記事
ガイド記事84位いつから流行ったの?節分の「恵方巻き」の由来・起源を解説
節分にいつのまにか定着した「恵方巻き」の由来・起源・発祥は? いったい誰がいつ流行らせたのか、節分に恵方巻きを食べる理由とともに解説します。
 冬の行事・楽しみ方(12~2月)ガイド記事
冬の行事・楽しみ方(12~2月)ガイド記事85位七草粥の由来や春の七草の意味・覚え方、七草の日はいつ?
七草粥を食べる「七草の日」は1月7日。七草粥の由来や意味を知って、無病息災で過ごしましょう! そもそもなぜ七草粥を食べるのか? 本来の「人日の節句」とは? 七草粥には春の七草を入れないといけないの? 子どもたちに七草粥を伝えていってくださいね。
 正月の行事・楽しみ方(年末年始)ガイド記事
正月の行事・楽しみ方(年末年始)ガイド記事86位招き猫の意味は? 右手・左手・高さ・色によるご利益【Q&A解説】
縁起物の招き猫は、あげている手(前足)の左右、また手のあげ方が高いのと低いのでは、その意味に違いがあります。さらには、白・黒・赤・金などといった色でその意味に違いがあったり、海外での呼び名があったりもします。そんな招き猫の豆知識をQ&A形式で解説します。
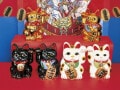 日本のしきたり・マナー・ことばガイド記事
日本のしきたり・マナー・ことばガイド記事87位小正月はいつ?どんど焼き(左義長)の意味・由来、食べ物「小豆粥」と「餅花」の作り方
1月15日は小正月。行事食の小豆粥を食べ、餅花を飾り、門松・しめ飾り・書初めなどを左義長(どんど焼き)で燃やします。 別名「女正月」と呼ばれる小正月の習わしや意味、電子レンジを使った餅花の作り方などを解説します。
 ガイド記事
ガイド記事88位【時候の挨拶・例文付き】12カ月の季節の挨拶と結び文、やわらかい表現からビジネス向けまで
手紙やメールの「時候の挨拶(季節のあいさつ)」に何を書けばいいのか迷うもの。12カ月の季節を表わすキーワード、それぞれの月の特徴、書き出しと結びの例文をまとめたので参考にしてください。
 日本のしきたり・マナー・ことばガイド記事
日本のしきたり・マナー・ことばガイド記事89位「松竹梅」の順番は平等で「ピンキリ」の上下ランクは逆?
松竹梅の順番といえば、松が1番上のランクというイメージの方が多いはず。また「ピンからキリまで(ピンキリ)」はどっちが上かといえば、慣用句ではピンが最高を表すとされています。しかし、その由来や本来の意味を知ると、今まで常識だと思っていたことと逆かもしれません。「松にして」「ピンでいいわ」は高いの? 安いの? 上下を勘違いしていると思わぬ失敗を呼ぶので要注意です!
 粋な振る舞い・和文化の楽しみ方ガイド記事
粋な振る舞い・和文化の楽しみ方ガイド記事90位「寝正月」は幸福のもと・早起きは“貧乏”のもと!? 元日は“朝寝坊”してゴロゴロ過ごして縁起かつぎ!
「寝正月」とは、お正月にどこにも出かけず家でゆっくり過ごすこと。「朝起き貧乏、寝福の神」ということわざもあるように、寝正月はじつは理にかなっているのです。寝正月の意味・由来や、お正月の過ごし方について解説します。
 ガイド記事
ガイド記事