治療・介護
漢方・漢方薬 新着記事一覧(2ページ目)
「漢方薬を飲んだら太る」は本当?
【国際中医師・中医薬膳師が解説】「漢方薬で太ることはありますか?」という質問を受けることがあります。漢方で健康的に痩せるお手伝いをすることはありますが、太るというのはどういうことでしょうか? 「太った」と感じやすい3つの体質を挙げて、疑問の真偽に迫ります。
 漢方の基礎知識・体質チェックガイド記事
漢方の基礎知識・体質チェックガイド記事生理前のイライラ、だるさ……PMSに効く漢方薬
【漢方薬剤師が解説】下腹部痛や頭痛、ニキビ、肌荒れ、食欲増進、イライラやだるさなど、様々な症状を伴うPMS(月経前症候群)。排卵後の黄体ホルモンによる心身の不調が原因と考えられており、ストレスや血行不良、タバコやカフェインで悪化するケースも。PMSの症状軽減に効く漢方薬一覧と、今日から始められる効果的な生活のコツについて解説します。
 ガイド記事
ガイド記事柴胡加竜骨牡蛎湯の効果・副作用……精神症状改善にも用いる代表的漢方薬
【漢方専門薬局の管理薬剤師が解説】柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)は精神症状を改善する代表的な漢方薬。動悸や食欲不振などのストレスによる身体症状にも有効です。具体的な効果や副作用、注意点について解説します。
 ガイド記事
ガイド記事眠れない・目が覚める・夢見が悪い…不眠の悩みに効果的な漢方薬
【漢方薬剤師が解説】「眠れない」「何度も目が覚める」「疲れが取れない」「夢見が悪い」など、日々の漢方薬における相談業務では、不眠症や眠りの質に関する悩みをとても多く伺います。不眠症によく使われる抑肝散、酸棗仁湯、帰脾湯などの効果、即効性の有無、睡眠導入剤(睡眠薬)との違い、漢方薬ならではのメリット、また、生活習慣の改善ポイントについて解説します。
 ガイド記事
ガイド記事半夏厚朴湯とは……憂うつ感や喉の不快感、消化器の不調の改善に
【漢方専門薬局の管理薬剤師が解説】半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)は気の巡りを改善する代表的な漢方薬です。具体的にはストレスを緩和して喉や消化器の不調などを取り除きます。憂うつ感にも効果的な半夏厚朴湯の薬効、向いている方、服用方法、副作用や注意点などを解説します。
 ガイド記事
ガイド記事体が冷える、手足が冷たい…冷え性に効果的な主な漢方薬
【現役薬剤師が解説】冷え性(冷え症)は血行の悪化から他の体調不良を引き起こすこともあり、放置は禁物です。冷えとあわせて起こる生理痛や生理不順、ひどい手足の冷えやしもやけ、食欲低下、軟便、体力低下や腰痛、頻尿、抜け毛などの症状に合わせて、上手に漢方薬なども活用してみましょう。身体を温めて冷えを解消する主な漢方薬と日常生活における改善点のポイントを解説します。
 ガイド記事
ガイド記事授乳中の産後うつ治療に…主に処方される漢方薬と効果
【不妊クリニック・漢方外来薬剤師が解説】産後うつで辛くても、心療内科の受診をためらう産後ママは少なくありません。産後うつに処方される十全大補湯、補中益気湯、抑肝散などの主な漢方薬の種類と効果、心療内科を受診すべき目安、授乳中の服薬について解説します。
 ガイド記事
ガイド記事ウィズコロナ時代の漢方薬…抵抗力の向上や不安感の軽減
【漢方薬剤師が解説】瞬く間に世界中に拡がった新型コロナウイルスは私たちの日常生活を一変させました。ウィズコロナ時代に役立つ漢方薬、特に抵抗力の向上やストレスによる憂うつ感の改善などに役立つ漢方薬について解説していきます。
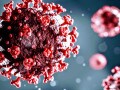 ガイド記事
ガイド記事逍遥散とは……更年期障害や血の道症にも効果
【漢方専門薬局の管理薬剤師が解説】逍遙散(しょうようさん)は、気分の沈みやイライラ感、不眠症などに有効な漢方薬で、更年期障害や女性ホルモンの変動による心身の不調である「血の道症」などでもよく使用されます。逍遥散の効果・副作用を始め、効果が出るまでどれくらいか、男性も服用メリットはあるのか、市販薬でも購入できるのか、加味逍遥散との違いは?などの疑問にお答えします。
 ガイド記事
ガイド記事心身の不調の原因は「気滞」?憂うつ感に処方する漢方薬・効果
【漢方薬剤師が解説】憂うつ感やイライラが続き、体にも頭痛、肩こり、消化器症状などの不調が出ている場合、精神的ストレスが蓄積し、全身の気の流れが悪くなっている「気滞(きたい)」の状態かもしれません。気滞を改善する代表的な漢方薬である半夏厚朴湯、逍遥散、加味逍遥散、柴胡加竜骨牡蛎湯、抑肝散のそれぞれの特徴と効果について解説します。
 ガイド記事
ガイド記事