二人だけで演奏するデュオ(二人)・ジャズのおすすめ

二人だけで演奏するデュオ(二人)・ジャズ
それだけに、二人の息がピタリと合ってハマった演奏になった時の素晴らしさは、また格別のものがあります。今回は、その二人だけの世界、デュオ・ジャズの名演をご紹介します。
<目次>
ニールス・ヘニング・オルステッド・ペデルセン(b) ジョー・パス(g) 「チョップス」より「オレオ」
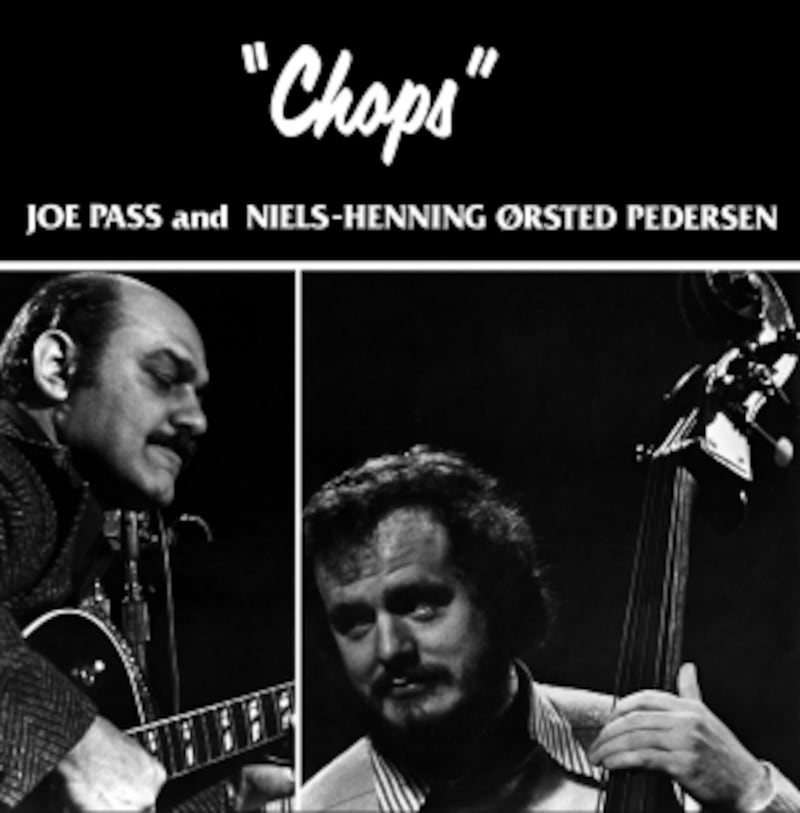
Chops
第一にはやはりそれぞれの楽器を演奏する技量が高いものでなければならないということ。その上で、第二に表現するアイディアや曲想をしっかり持ち、第三には二人の呼吸を合わせ、より高い次元を目指すものでなければなりません。
そういった意味で、この1978年録音の「チョップス」は、代表的なものと言えます。ここに展開されるのは、それぞれの楽器のヴァーチュオーゾ(達人)同士が火花を散らす真剣勝負です。
ニールス・ヘニング・オルステッド・ペデルセンは、デンマーク出身のベース奏者です。10代のころからその名はヨーロッパ中に知れ渡り、本場アメリカのミュージシャンに驚かれるほどのテクニックを持っていたベースのヴァーチュオーゾです。
対するジョー・パスはアメリカのギター奏者。ジョーもまた、代表作が「ヴァーチュオーゾ」という名のアルバムを出すほどの名人。その二人ががっぷり四つに組んで、それぞれの持ち味と唄心を競ったのがこの「チョップス」です。
このアルバムは、私が大学のジャズ研に入ったばかりの頃に、ギターの先輩に教えてもらったアルバムです。「すごいぞ、ジョーパスが押されてるよ、このベースに」と笑いながら聴かせてくれたのがこのアルバムでした。
ご紹介する曲の「オレオ」はテナーサックス奏者のソニー・ロリンズの代表曲。「アイ・ガッド・リズム」という曲のコード進行をもとに作られたものです。
大学のジャズ研では、「ブルース」や「枯葉」とともに演奏されることが多い、「循環コード」と呼ばれるコード進行です。その参考にと聴かせてもらった時は、あまりのテクニックに衝撃を受けました。
テーマ部分は二人のユニゾンで奏されます。すぐに、ニールスによってアドリブが展開されます。今回、久しぶりに聴きなおしてみて、ここに展開されているベースソロのアイディアが、エレキベースの天才と言われた「ジャコ・パストリアス」にどこか似ていると思いました。
この曲ではやっていませんが、「ヤードバード組曲」など他の収録曲ではニールスはハーモニクスを多用しています。エレキ・ベースのジャコの専売特許のように思われていた奏法が、ここではウッド・ベースによって披露されています。
二人が参考にしあっているという話は聞いたことがありませんし、ウッドベースとエレキベースの違いはありますが、二人の着想は非常に似ていると思えます。
ジャコより四歳上のニールスは早熟で60年代初頭から第一線で活躍していました。おそらくは、参考にしたとしたらジャコの方でしょう。
しかしながら、この1978年当時は、ジャコもソロアルバムや「ウェザー・リポート」での活躍により、世界中で有名になっていましたので、名人ニールスがアイディアのヒントをジャコから得ていたとしてもなんら不思議ではありません。名人、名人を知ると言ったところでしょうか。
演奏では、ジョーとニールスのソロが終わって、いよいよフォーバース(4小節のアドリブの掛け合い)が始まります。前半部分は良い勝負ですが、後半に行くにつれ、ニールスのアイディアがあふれだしてきます。
ギターの名人ジョー・パスが、本当に押されっぱなしに聴こえるのが、可笑しいところです。音楽の勝負に勝ち負けはありませんが、皆さんの耳にはどう聴こえるでしょうか?
このアルバムは、全編二人の真剣勝負と言った趣の曲が並んでいます。それぞれの曲で、どちらが優勢か? などと聴いていくのも楽しいものです。
Amazon
ビル・エヴァンス(p) ジム・ホール(g)「アンダー・カレント」より「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

アンダーカレント
演奏されるのは、甘口のスタンダード・ソングとして有名な「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」。このスイートな曲を、二人は緊張感あふれるビターな演奏へと昇華しています。
出だしのビルによって奏されるテーマのテンポとタッチやそのメロディに絡みつくように演奏されるジムによるバッキング。最初からこの曲が決して甘いものではないという二人の意図が感じ取られます。
ジムのアドリブのバックでのビルの硬質な音色。お返しとばかりのビルのバックでの、ジムによる切れの良いカッティングなどスリリングな二人の演奏は続きます。
通常は、スローでじっくりと歌いあげられることが多い、この「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」。二人の協演は、曲の違う面を見ることができる、ある意味もっともジャズ的なデュオ演奏と言えます。
Amazon
デューク・エリントン(p) ジミー・ブラントン(b)「ザ・ジミー・ブラントン・イラ」より「ピター・パンサー・パター」

The Jimmy Blanton Era
デュークは、1920年代から1970年代まで文字通りキングとして君臨した大物です。デュークの元からは、ジョニー・ホッジス、クーティ・ウィリアムス、ベン・ウェブスターといったキラ星のようなスターが数多く育っています。
その中には、才能に見合うだけの活動期間がなかった不運のミュージシャンもいます。ベース奏者のジミー・ブラントンは、特筆すべき存在として、歴史にその名をとどめています。
ジミー・ブラントンは、1918年生まれで、結核によりその絶頂期にあった1942年に、24歳で早逝してしまうベース奏者です。その短い活動期間の間に、スウィング・ジャズ当時としては珍しい、デュークのピアノとのデュオ演奏や、エリントン楽団での貴重な名演を残しています。
志なかばにして病に倒れたジミー。そのアイディアは、すぐ後に続くチャールズ・ミンガス、レイ・ブラウンといったモダン・ベース奏者へと受け継がれました。人々はジミーをして「モダン・ジャズベースの開祖」と呼んだのです。
ここで聴かれるデュークとのデュオ「ピター・パンサー・パター」は、そのモダンな奏法が随所に捉えられ、いかにジミーが進んでいたかがわかる内容です。
これまでの、ベース奏者はみな、一音一音が短く、四分音符を半分の長さの八分音符のように弾いていました。これは、もちろんそれまでの主流だった跳ねるシャッフル・ビートの影響が大きいですが、弾けなかったという見方もできます。
ジミーは、4ビートの基本の四分音符をその長さで引くことができた初めてのベース奏者と言えます。それにより、それまで跳ねていたビートに、糸を引くようなねばりが生じ、現代につながるウォーキングベースの基本形ができたと言えます。
ジミーは、ピチカート(指で弾いて音を出す奏法)のウォーキングベースの音の長さを始めて意識して演奏することができたイノベーターなのです。
エラ・フィッツジェラルド(vo) エリス・ラーキンス(p)「ピュア・エラ(ガーシュイン・ソングス)」より「スーン」

Pure Ella
エリス・ラーキンスのピアノはここでは、控えめな伴奏に徹しています。しっとりとした歌いだしのエラをやさしく包み込むようにオブリガートを入れて、良い雰囲気です。
このアルバム全体を通してのエラは、いつもの元気いっぱいなスキャットなどは控え、一語一語をかみしめるように丁寧に歌っています。そこを、物足りないとみるか、おしとやかで良いとみるかは、好みの分かれるところ。この曲では、途中ミディアムテンポに転じて、メリハリをつけて楽しませてくれます。
伴奏のエリスも軽快なテンポに切り替わるところが見事。エラはピタリと寄り添い、しっとりと歌い切ります。名人二人にかかれば、歌い手を選ぶこの難曲も難なく名演に変わってしまいます。
Amazon
スタン・ゲッツ(ts) ケニー・バロン(p)「ピープル・タイム」より「ジ・エンド・オブ・ラヴ・アフェア」

People Time
そんな都会的な歌にスタン・ゲッツほどハマるサックス奏者はいないと言ってよいでしょう。ここでのスタンは期待通り、まるで粋なシンガーのように恋の終わりを歌いあげます。
まず初めに驚くのが、そのスタンのサックスの音のピュアさと美しさ。スタンの声ともいえるサックスの音は、ますます高音が冴え、美しさで圧倒されます。それとともに、マイクが捉えたスタンのブレス(息継ぎ)がとてもセクシー。
「ジャズは結局ナイトミュージックなのさ」と言ったとされるスタンの面目躍如といったところです。そして実はこの演奏が、長年にわたって病と闘い続け、この三か月後にはついに召されてしまうスタンの白鳥の歌ともいえる演奏だという事実。
その真実には、再度驚かされ、また心の底からの感動をおぼえます。
白鳥が病をおしながら大空へと羽ばたく姿。ここでのスタンの雄姿は、そんな情景を思い起こさせます。マイクに入ったブレスの音は、そのままスタンと病との戦いの証でもあったわけです。
スタンは、1950年から69年までの20年間で、15回もジャズ専門誌「ダウンビート」の人気投票でテナーサックス部門第一位に輝いた大スターです。
そのクールなサウンドと、狷介な性格、ハンサムなルックスまでもが、人間味あふれるスターたる条件を備えた巨人です。そして、スタンほど、聴衆のことを考え、聴衆の聴きたいものを提供してくれたプレイヤーはいません。
その上、人生の最後の最後まで、スターとして、ジャズサックスプレイヤーとしてその矜持を全うした稀有の存在です。
このアルバム「ピープル・タイム」での、ピアノの名人「ケニー・バロン」との珠玉のデュオは、ジャズの神様に祝福された一握りの天才によってしかなしえない、まさに奇跡として記憶されるべき名演と言えます。
今回の二人だけの世界、深遠なるデュオ(二人)ジャズは、いかがでしたか? 素晴らしい才能と研鑽が垣間見えるジャズの高度な演奏の世界。
聴くほどにさらにあなたも深遠な世界へと誘われることでしょう。それでは、また次回お会いしましょう!
Amazon
【関連記事】







