エンタメ
歌舞伎 新着記事一覧(2ページ目)
歌舞伎の「見得」の意味や種類とは?知っておきたい歌舞伎のルール
歌舞伎を見ていると、効果音に合わせて役者が身体の動きを止め、首を回すように振って最後にグィッとにらんだ目をして静止する、いわゆる「見得」というのが気になるのではないでしょうか。色々な見得に関するお話をいたします(図解付き)。なお「見得を切る」という表現は本来は間違いで、「見得をする」というのが正しいそうです。
 歌舞伎の基礎知識ガイド記事
歌舞伎の基礎知識ガイド記事歌舞伎の楽しみ方レシピ「鳴神」……色っぽい神話劇
「鳴神」は、歌舞伎十八番の一つ。長らく上演が絶えていたものを、二代目市川左團次が復活したのが近年上演されているものの原型。この演目は主要人物が二人だけでありながら、十分にドラマチックかつユーモアもある大変人気のある芝居です。
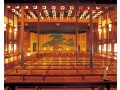 はじめての歌舞伎観劇ガイド記事
はじめての歌舞伎観劇ガイド記事大向うは応援コール? 歌舞伎とアイドルの意外な共通点
歌舞伎では舞台で演じる役者に向かって「成田屋!」「中村屋!」と声を掛ける文化が江戸の昔から残っていて、この掛け声や声を掛ける人たちを「大向う(おおむこう)」といいます。その本質は驚くほどアイドルやアーティストへの応援コールに似ている部分があります。
 ガイド記事
ガイド記事知らざぁ言って聞かせやしょう! の意味とは? 歌舞伎の「七五調」
有名な七五調のセリフ、「知らざぁ言って聞かせやしょう!」の意味とは? 歌舞伎の世話物というのは比較的リアルな芝居。当時の江戸の風俗をリアルに描写している場面も多く、親しみやすい演目も。けれど、そうした世話物でも突然様式的な世界に飛躍することがあります。
 歌舞伎の基礎知識ガイド記事
歌舞伎の基礎知識ガイド記事「女形」とは?歌舞伎では、なぜ男が女役をするのか
女形は決して「女性」をそのまま写しているわけではありません。歌舞伎における女形は「女性」というものを客観視し、中でも重要な部分を取り出し拡大化して見せる技術だといえます。「女らしさ」を表現するための技術が洗練され、注ぎ込まれてきたものです。
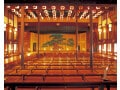 歌舞伎の基礎知識ガイド記事
歌舞伎の基礎知識ガイド記事歌舞伎由来の言葉がいろいろ! ドロン、差し金、黒衣など……
「だんまりを決め込む」「大詰めを迎える」「大向こうをうならせる」……そんなチョッピリレトロな言い回しを聞いたことはありませんか? これみんな、歌舞伎の専門用語から出てきた言葉なのです。一つずつ解説します!
 歌舞伎関連情報ガイド記事五十川 晶子
歌舞伎関連情報ガイド記事五十川 晶子歌舞伎の「型」とはなにか……型のある演技について
歌舞伎には「型」と呼ばれるものが厳然と存在しています。これは代々の役者さんたちが時間を掛けて洗練させてきた工夫であり、知恵だと言えます。ひとによっては、このために歌舞伎を「型通りの演技」として、現代的な演劇に比べて劣っているかのように言うこともあるようです。
 歌舞伎の基礎知識ガイド記事
歌舞伎の基礎知識ガイド記事初めて歌舞伎を観るなら、役柄を知ろう!
今度、初めて歌舞伎を観てみようという方へ。「役柄」が分かれば歌舞伎はぐんと面白く観やすくなります。役者は化粧しているし誰がどの役なのか分かりにい。パンフレットなどでストーリーを追うのも良いですが、今回は、こちらの記事でわかりやすく解説します。
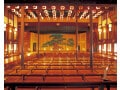 歌舞伎関連情報ガイド記事五十川 晶子
歌舞伎関連情報ガイド記事五十川 晶子歌舞伎の黒衣(くろご)とは?
歌舞伎は知らなくても、その姿は殆どの人が知っている黒衣(くろご)。読み方は「くろこ」と誤解されているケースをよく見ますが「くろご」と濁るのが正解です。この見慣れた姿の黒衣。歌舞伎におけるその役割について、ご説明します。
 歌舞伎の基礎知識ガイド記事
歌舞伎の基礎知識ガイド記事100両って現在ではいくらの価値?江戸時代のお金事情
江戸時代のお金で100両というと、現在ではいくらの価値があるのでしょうか。江戸の人にとっては、ごく当たり前の感覚が、今の私たちにはわかりません。しかし、この基本的な感覚がある程度わかるようになると、歌舞伎や大河ドラマの面白さが違ってきます。
 歌舞伎の基礎知識ガイド記事
歌舞伎の基礎知識ガイド記事