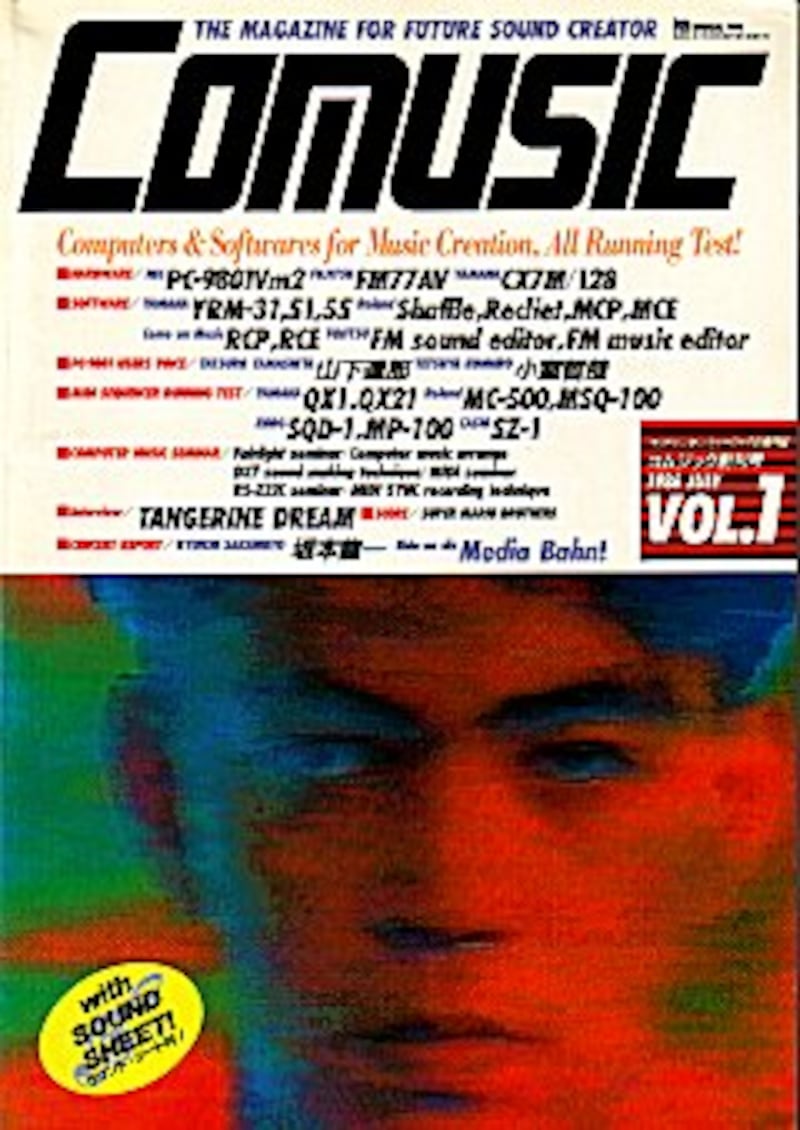 さて、話を元に戻しましょう。その次に登場してきたのが今は倒産し、なくなってしまった立東社のCOMUSIC(コムジック)。これは創刊号のVol.1が発行されたのが86年7月で、まあ、TECHIIとほぼ同じ時期です。まさにコンピュータ・ミュージックの略の名称で発行されただけに、私個人的にも非常に期待した雑誌でした。実際、中身のほうもDTMそのもの。ただこれはまだ、WindowsやMacなどが登場するはるか昔のことです。国内ではNECのPC-8801という8ビットのマシンや富士通のFM77なんてマシンが健在だった時代です。今から考えれば本当に原始的なシーケンスソフトと音源をつないでなんとか音を出すための記事がいろいろと掲載されていました。この表紙を見ると「with SOUND SHEET」と書いてあります。そう、そのソノシートといわれていたビニールのレコードがサンプル音として付いていたんです。これを見るとやはり時代を感じますよね。また、記事のほうはソフトの紹介やシンセの紹介はもちろんですが、まだDTMなんて言葉も生まれる前のことだったので、製品もほとんどなく、ハードウェアの自作記事なども結構出ていたのです。ただ、そんなにマニアックな雑誌、そうそう売れるわけもなくVol.4で終了してしまいました。
さて、話を元に戻しましょう。その次に登場してきたのが今は倒産し、なくなってしまった立東社のCOMUSIC(コムジック)。これは創刊号のVol.1が発行されたのが86年7月で、まあ、TECHIIとほぼ同じ時期です。まさにコンピュータ・ミュージックの略の名称で発行されただけに、私個人的にも非常に期待した雑誌でした。実際、中身のほうもDTMそのもの。ただこれはまだ、WindowsやMacなどが登場するはるか昔のことです。国内ではNECのPC-8801という8ビットのマシンや富士通のFM77なんてマシンが健在だった時代です。今から考えれば本当に原始的なシーケンスソフトと音源をつないでなんとか音を出すための記事がいろいろと掲載されていました。この表紙を見ると「with SOUND SHEET」と書いてあります。そう、そのソノシートといわれていたビニールのレコードがサンプル音として付いていたんです。これを見るとやはり時代を感じますよね。また、記事のほうはソフトの紹介やシンセの紹介はもちろんですが、まだDTMなんて言葉も生まれる前のことだったので、製品もほとんどなく、ハードウェアの自作記事なども結構出ていたのです。ただ、そんなにマニアックな雑誌、そうそう売れるわけもなくVol.4で終了してしまいました。実はこの立東社は、当時からロッキンfやKB SPECiAL(キーボード・スペシャル)といった雑誌も発行していましたが、そのころ注目していたのがロッキンf。知っている方は知っているとおり、これはまさにジャパニーズ・ヘビメタ雑誌であったのですが、まだそのころは、ずいぶんいろいろな記事があり、中には、コンピュータ・ミュージック関連やエフェクター関連の製作記事なんかが掲載されていたんです。それらをまとめた、「エフェクター自作&操作術」というのはわれわれ一部のコンピュータ・ミュージック・マニア(?)、電子楽器製作マニア(?)にとってはバイブル的なものでもありました。一方のKB SPECiALはリットーミュージックのキーボードマガジンとともに、時々内容によって買ってはいたものの、やはり基本はキーボード雑誌であり、そのころはあまりDTM色はありませんでした。創刊はKB SPECiALが85年、キーボードマガジンが79年と古いのですが、いずれも途中からDTM色を強めてきたという歴史があります。が、この辺については、私もよくチェックできていなかったので、この2誌のDTM的詳細は割愛します。
■ソフトバンクが出したCOMPUTER SOUND
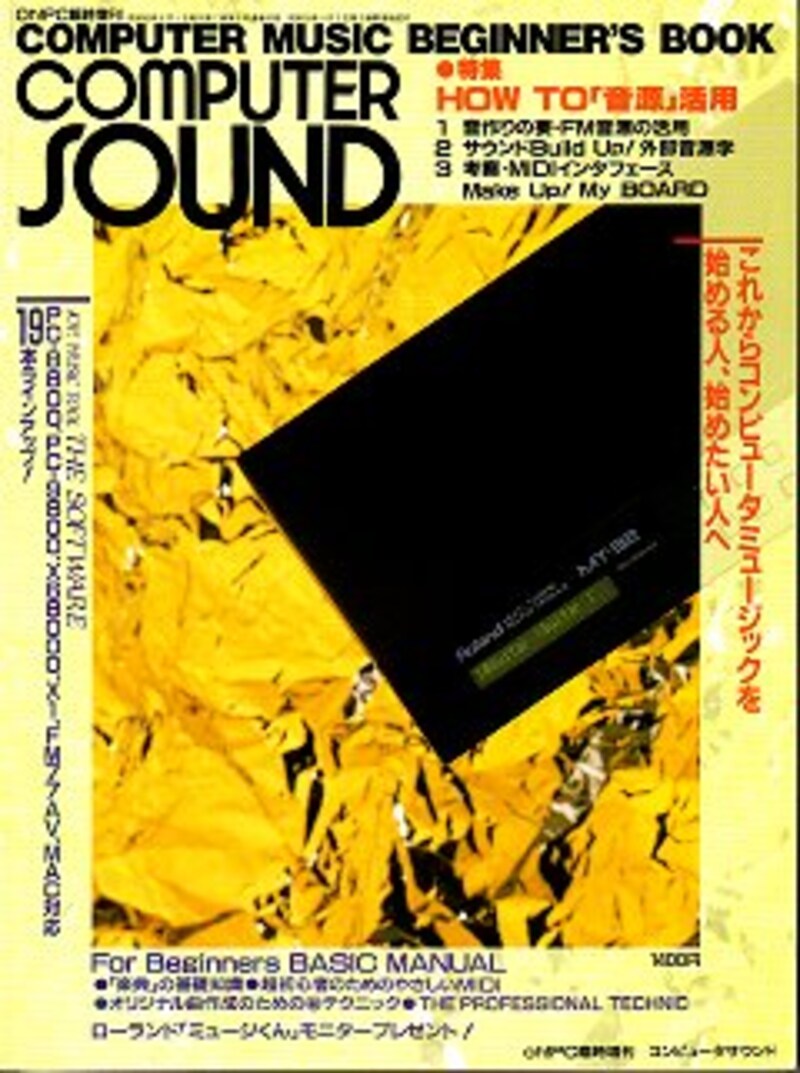 ここまで登場してきた出版社を見ると、リットーミュージック、音楽之友社、立東社といずれも音楽系の出版社ばかり。やはりコンピュータ・ミュージックというからには、コンピュータ系の出版社が登場してもおかしくないはずです。そんな中、はじめてコンピュータ系から登場してきたのが日本ソフトバンク(現ソフトバンクパブリッシング)でした。当時の人気パソコン誌であったOh!PCの臨時増刊という形で、88年8月にCOMPUTER SOUNDという本が誕生したのです。恐らく、これが発行された時点では、単発のムックという位置付けだったのだと思われますが、やはりその後、4号まで登場し、終了しています。どうも、どの雑誌もコンピュータ・ミュージックの本は4号でオシマイというのが決まりだったようなんですね。ちなみに、この創刊号の記事としてはHOW TO 「音源」活用というもので、FM音源の音色作りについてやMIDIインターフェイスを通じて各種音源をコントロールするためのプログラムなどがリストで掲載されていました。また、このDTMの世界においては大きな歴史の節目となったRolandの「ミュージくん」が発表された直後に出た本だったこともあり、ミュージくんに関する情報も掲載されていました。
ここまで登場してきた出版社を見ると、リットーミュージック、音楽之友社、立東社といずれも音楽系の出版社ばかり。やはりコンピュータ・ミュージックというからには、コンピュータ系の出版社が登場してもおかしくないはずです。そんな中、はじめてコンピュータ系から登場してきたのが日本ソフトバンク(現ソフトバンクパブリッシング)でした。当時の人気パソコン誌であったOh!PCの臨時増刊という形で、88年8月にCOMPUTER SOUNDという本が誕生したのです。恐らく、これが発行された時点では、単発のムックという位置付けだったのだと思われますが、やはりその後、4号まで登場し、終了しています。どうも、どの雑誌もコンピュータ・ミュージックの本は4号でオシマイというのが決まりだったようなんですね。ちなみに、この創刊号の記事としてはHOW TO 「音源」活用というもので、FM音源の音色作りについてやMIDIインターフェイスを通じて各種音源をコントロールするためのプログラムなどがリストで掲載されていました。また、このDTMの世界においては大きな歴史の節目となったRolandの「ミュージくん」が発表された直後に出た本だったこともあり、ミュージくんに関する情報も掲載されていました。以上、80年代の黎明期におけるDTM関連雑誌の歴史について見てきましたが、いかがだったでしょうか?次回は、私、藤本自身も大きく関わったコンピュータ・ミュージック・マガジンやDTMマガジン誕生の背景などについて紹介していきたいと思います。







