症状・病気
糖尿病 新着記事一覧(10ページ目)
予測が大事な糖尿病治療に!食物と血糖値のサイエンス
完治しない糖尿病の治療は、常に先を予測しながら管理していくものです。医師は病気がいかなる介入でどのような経過をたどるかを考えながら患者の5年先、10年先の合併症リスクを予測しています。患者も将来に漠然とした不安を抱えながらも毎日の血糖コントロールに努めています。糖尿病治療のキーワードは予測(prediction)ではないかと思っています。
 糖尿病の原因・基礎知識ガイド記事河合 勝幸
糖尿病の原因・基礎知識ガイド記事河合 勝幸糖尿病の隠れ神経障害の早期発見と治療 (2)
体の奥深いところで神経は心臓の拍動から呼吸、食物の消化、排尿、発汗など生命を維持するすべてのことを統率しています。これらは自分で意識してコントロールしているわけではないので自律神経といわれますが、糖尿病はこれらの神経も障害します。
 その他の糖尿病の合併症ガイド記事河合 勝幸
その他の糖尿病の合併症ガイド記事河合 勝幸糖尿病の隠れ神経障害の早期発見と治療 (1)
糖尿病患者の3人のうち2人にあると推定される糖尿病神経障害は、しばしば自覚症状がないままに進行していきます。持続する高血糖がいろいろな原因によって神経細胞を障害するのですから、早期の発見と適切な治療やケアをすれば、痛みやしびれを最小限にし、足の大切断を防ぐことも可能です。
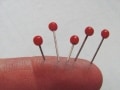 その他の糖尿病の合併症ガイド記事河合 勝幸
その他の糖尿病の合併症ガイド記事河合 勝幸入院時の医療ミスから糖尿病患者を守る心構え
高齢社会の糖尿病患者がさまざまな病気で入院するときのトラブル防止は、患者自身が心得ておくべきことがいろいろあるのです。
 糖尿病の治療法・病院ガイド記事河合 勝幸
糖尿病の治療法・病院ガイド記事河合 勝幸アメリカ糖尿病協会も推奨! 活用したいスマホアプリ
もし、あなたが糖尿病のような慢性病を抱えていて、いつもスマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)が手元にあるのなら、いろいろなアプリが手助けしてくれるでしょう。日本でも糖尿病のアプリが増えてきましたが、時代のトレンドを読むために先進国アメリカのポピュラーな糖尿病アプリを紹介します。
 糖尿病関連ニュース・最新情報ガイド記事河合 勝幸
糖尿病関連ニュース・最新情報ガイド記事河合 勝幸糖尿病の足病治療に関する調査で見えてきた現実 (2)
足病変には必ず潰瘍(かいよう)の話が出てきます。潰瘍とは、普通は足底やつま先、足指の背などにできる痛みのない傷口の開いた傷のことです。加齢による足の変形や、たこ、魚の目が肥厚して強く圧迫して虚血になったり、「とげ」や靴擦れ、深爪などが炎症を起こして傷口が治りにくくなったりします。そんな時、あなたは最初にどの診療科へ相談に行きますか?
 糖尿病の合併症(痛み・冷え・足の異常等)ガイド記事河合 勝幸
糖尿病の合併症(痛み・冷え・足の異常等)ガイド記事河合 勝幸糖尿病の足病診療に関する調査で見えてきた現実 (1)
日本で初めて実施された『足病治療に関する患者・医師調査』で改めて浮かび上がったのは、わが国の臨床現場で直面している医師と患者の困惑と、足を守るための集学的治療を担う糖尿病内科、腎臓内科、循環器内科、血管外科、形成外科、整形外科、皮膚科などの連携の不十分さでした。
 糖尿病の合併症(痛み・冷え・足の異常等)ガイド記事河合 勝幸
糖尿病の合併症(痛み・冷え・足の異常等)ガイド記事河合 勝幸カーブ(カーボ)カウンティングの基本
糖尿病の食事療法のメソッドとしては食品交換表など幾つかありますが、カーブカウンティングは米国ではとても一般的なもので、食事とインスリン投与を状況に応じて柔軟に変更できる、実生活向きの方法です。特にインスリンマルチショットの1型/2型糖尿病者には1800ルール・500ルールと組み合わせることによって血糖コントロールを容易にしてくれる心強い手段です。
 糖尿病対策の生活・運動療法ガイド記事河合 勝幸
糖尿病対策の生活・運動療法ガイド記事河合 勝幸糖質制限食と糖尿病
食後の血糖上昇のほとんどが食品成分の炭水化物(糖質)によるものですから、糖尿病の人がそれをある程度制限するのは当然のことです。ただ、医療プロバイダーの栄養指導で、まず理想体重を基準にしたエネルギー摂取量を決めて、一律にエネルギー比で50~60%を炭水化物で取るように指示するのは、元になる考えはよく分かりますが少し安易すぎるような気がします。
 糖尿病対策の生活・運動療法ガイド記事河合 勝幸
糖尿病対策の生活・運動療法ガイド記事河合 勝幸強化インスリン療法の1,800ルールと500ルール
インスリンのベーサル/ボーラス投与による精密な血糖コントロールのスタートは、過去2-3ヵ月の平均血糖値を示すHbA1cの目標をまず決めて、それを達成するためのポイントとして空腹時血糖値と食後2時間値、就寝時血糖値の範囲を設定し、それぞれの目標ゾーンに血糖自己測定の結果を少なくとも75%は収めるように食事(特に炭水化物)とインスリン投与量、運動のバランスを取ることから始まります。
 糖尿病の経口薬・インスリンガイド記事河合 勝幸
糖尿病の経口薬・インスリンガイド記事河合 勝幸