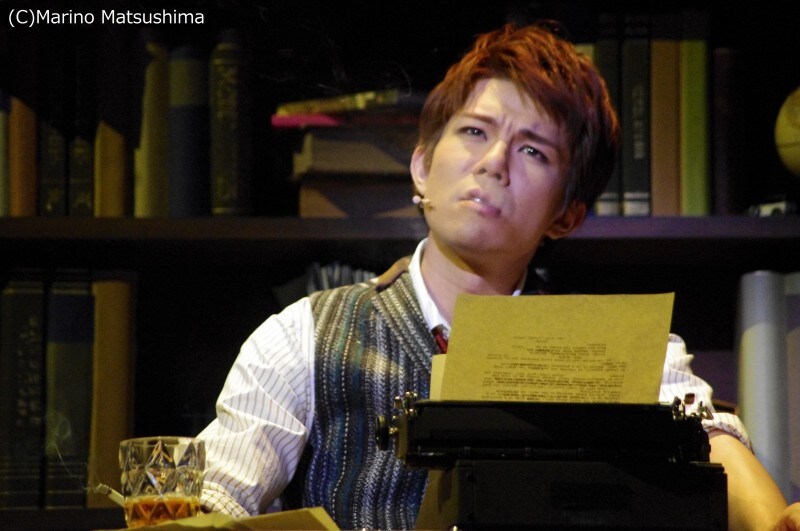(筆者Marino Matsushimaをツイッターでフォローいただけますと、記事更新時にお知らせします)
【9月の注目!ミュージカル】
『シティ・オブ・エンジェルス』←福田雄一さんインタビュー&観劇レポートをUP!(本頁)
『マリー・アントワネット』←観劇レポート(2頁)&製作発表レポートをUP!(3頁)
『ジャージー・ボーイズ』←観劇レポートをUP!(4頁)
『マイ・フェア・レディ』←観劇レポートをUP!(5頁)
【別途特集したミュージカル】
『タイタニック』←藤岡正明さん、相葉裕樹さん、鈴木壮麻さん、渡辺大輔さんはじめ出演者インタビューをUP!
『ノートルダムの鐘』←佐久間仁さん、清水大星さん、光田健一さんインタビューをUP!
『シティ・オブ・エンジェルス』
9月1~17日=新国立劇場 中劇場、その後静岡・大阪で上演『シティ・オブ・エンジェルス』見どころ
1940年代のハリウッドを舞台に、脚本家の世界と、彼が執筆中のシナリオの世界が交互に登場。周囲の人々に脚本家が振り回されるうち、何かがおかしな方向に。現実と虚構が交錯するなかで彼は、そして彼が描くキャラクターたちはどうなってしまうのか?!
サスペンスとコメディを巧みに織り交ぜた台本をサイ・コールマン(『スウィート・チャリティ』)の粋な楽曲で包み込み、作品賞を含め90年のトニー賞6冠に輝いた『シティ・オブ・エンジェルス』。長く日本での上演が待たれましたが、遂に、日本人キャストで上演されます。
演出は、ふんだんに笑いを盛り込んだ独特の演出でミュージカル界に旋風を巻き起こしている福田雄一さん。『フル・モンティ』でミュージカルに初出演した山田孝之さん、『タイトル・オブ・ショウ』で福田演出を経験済みの柿澤勇人さんと強力タッグを組み、個性的な共演陣とともに、一瞬も目の離せない舞台を創り上げてくれそうです。
観劇レポート:笑いと華々しさの奥に潜む“表現者の心意気”
ステージ中央に吊り下げられているのは、いわくありげな男女が描かれた「City Of Angels」の看板。新作映画の予告らしい。アンサンブルがオープニング・ナンバーを華麗に歌い踊ると、ステージ上には男の死体が。彼、私立探偵のストーンが銃で撃たれるまでの顛末を振り返る形で、物語はスタートする。
発端は、探偵事務所を訪ねて来た美女アローラからの、義理の娘の捜索依頼。いかにも肋骨を折りそうな“やばい”依頼を彼は一度は断るが、高額な報酬の誘惑には勝てず、陰謀(?)に巻き込まれてゆく。
……と突然、舞台上手からタイプライターに向かう人物が登場。彼が何行かを打ち直すと、それまで会話をしていたストーンと秘書のウーリーが動きを止め、違う台詞で同じシーンを演じ始める。実はこれまでの光景は、脚本家のスタインが今、まさに書いている作品世界だったのだ。
そこにプロデューサーのバディが電話をかけ、脚本へのダメ出しを始める。はじめはバディの求めに応じながら執筆を続けるスタインだったが、次第にフラストレーションが募ってゆき、のみならず映画の中のストーンまでもが、スタインに話しかけて来る……。
脚本家スタインの現実世界と、彼が描く探偵ストーンの虚構世界がパラレルで描かれ、ある一点で交錯。今回が初となるその日本版は、ストーン役の山田孝之さんはじめ、主に映像世界で活躍するキャストと、スタイン役の柿澤勇人さんら、ミュージカルでお馴染みの面々それぞれの輝きが、存分に引き出されているのが魅力。風刺味の強い作品ですがシリアスになりすぎず、何より皆、心から楽しんで演じていることが伝わってくるのは、福田雄一さんの愛情あふれる演出によるところが大きいのでしょう。
特に同じ言葉を何度も繰り返すことで、時間の流れをストップさせ、小さな混乱を生じさせる佐藤二朗さん(今回が初ミュージカル)のギャグがちょっとした場面を大いに盛り上げ、”日本版ならではの味わい”に貢献しています。
山田孝之さんの力強い存在感と鋭さ、山田優さん・木南晴夏さんのまっすぐでひたむきな歌唱、渡辺麻友さんのコケティッシュなオーラに対して、柿澤勇人さんは野心家の脚本家をエネルギッシュに体現。一瞬ではありますが、明らかな観客サービスとして(!)その肉体美を見せる場面もあります。
また“ただ者ではない”美女、アローラ役の瀬奈じゅんさんが登場シーンを華やかに染め上げ、終盤、それまで賑やかかつミステリアスに進行していた舞台をしゅっとまとめ上げているのが流石です。
ハリウッド業界の内幕をクリエイターの生きづらさをシニカルに描く本作ですが、最後には“破壊的な大団円”で、表現者の心意気が炸裂。爽やかな後味を残す舞台です。
演出・福田雄一さんインタビュー “僕にとって一番新しいメディアがミュージカル”

福田雄一 栃木県生まれ。大学時代に劇団を立ち上げ、劇作家・演出家として活動を始める。映像にも進出し、ドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズ、映画『銀魂』等の話題作を発表。2012年、『モンティ・パイソンのSPAMALOT』で初ミュージカル演出、以降『フル・モンティ』『エドウィン・ドルードの謎』『ブロードウェイと銃弾』などミュージカル演出でも活躍。(C)Marino Matsushima
――福田さんは様々なメディアで活躍されていますが、ミュージカルはご自身にとってどんな位置付けなのでしょうか?
「もともと大学時代から舞台をやってきて、30過ぎで映像の仕事に飛び込んだので、舞台へのこだわりはずっと自分の中にありました。ただ、栃木県出身で、演劇と言うと学校に回ってくる『巌窟王』というようなイメージがあって、歌や踊りが好きでも、その嗜好性がミュージカルというものと結びつかなくて。それが14年前、家族で劇団四季の『ライオンキング』を観て大ショックだったんですね。うわ、こんな楽しい舞台があるんだ、これまで敬遠してたけどミュージカルってこんなに楽しいんだって。自分が今、唯一積極的に楽しめるものがミュージカルかもしれないですね。観ても、(演出を)やっても楽しいというのは、ドラマや映画でも味わえない感覚です」
――それは音楽という要素ゆえでしょうか?
「音楽的なものであったり、視覚的なものであったり。自分にとって一番新しいメディアなんですよね。ドラマや映画を観るときには、生意気ながら若干、監督の目線で観ることはあるけど、ミュージカルではそれがなくて、単純にお客さん目線で観れちゃう。純粋に100パーセントってミュージカルだけですね」
――“ここはもうちょっとこうだったら……”と思いながら観ることはない、と?
「ないんですよ。批判する能力が全くない(笑)。だからいつも妻に“もうちょっとましな感想言わないと、いつまでたってもバカだと思われるよ”と言われてますね。“あそこはこうだったね”ではなくて、だいたい“面白かった~!”か“つまらなかった~”しかないですから(笑)。自分のポリシーでもあるのだけど、(作品って)全体を通して面白いかつまらないかのどっちかしかない、そういう見方しかしないんですよ。いろんなことがわかってきちゃって分析するようになると、今と同じような楽しみかたはできなくなるんじゃないかなと思います」
――ミュージカル演出にあたって、既存のミュージカルの作り方に対するチャレンジを意識されることは?
「全くないですね。役者さんはいろいろな演出家の方とお仕事されるけど、僕は他の先生方が演出しているところを観たことがないから、ミュージカルはこう作るということもわからない。だから、基本的には映像を作るときと同じような作り方してるんですよね。楽譜も読めないし、ダンスも自分ではつけられないし、キャリアを考えた時に僕が振付家の先生を上回ることは絶対にないので、先生に“こういうイメージで”というものを伝えてお願いします。
福田組は”餅は餅屋”方式で、僕がわからないことは全部お任せする分業制。だから例えば“上島(雪夫)さんがこんな面白い振付作ってくれた、うわ~!”と感激できる。それと、ミュージカルではある段階でダンスが加わり、オーケストラが加わっていくけど、ストレート・プレイにはそういう段階がないんですよね。ダンスやオーケストラが加わった時のテンションは半端ないです(笑)。もうミュージカルじゃないと楽しめないな、とこの前モテリーマン(「スマートモテリーマン講座」)をやってて思った(笑)」
――例えば既存の作品への、ふんだんなギャグの入れ込み方は、斬新に映ります。
「よく“ミュージカルに対するテロ行為”だとか“黒船”だとか言われるんですけど(笑)、単純にミュージカルというものを小劇場の感覚でやってるのが、僕だけなんじゃないかな。学生時代に第三舞台とかを観て影響を受けた小劇場の遊びみたいなものをミュージカルに持ち込むと、それはミュージカルの世界ではご法度なものばかりなんですよね。なんでこの時代にこんなこというのとか。例えば『モーツァルト!』で急にスマホを使ったらびっくりすると思うけど(笑)、そういうことを気にしないでやってしまうのが僕のやり方だから。それはミュージカルを観てきた方にとってはびっくりだと思うけど、“俺がミュージカルを変えてやる!”みたいな意識は全くないんですよ」
――面白い、楽しいと思えることをやってみた結果でしかない、と?
「そうなんですよ。ただ、日本のミュージカル界が自ら入口を狭めて来た歴史はあるような気がするんですね。ブロードウェイに行くとラブストーリーにコメディにと、いろいろなミュージカルがあるけれど、日本では従来の客層がお好きなタイプのものを選んで上演している、というのが僕の中の認識。
そういうものばかりじゃないだろうというところで、初めて演出したミュージカルが(スラップスティック・コメディ的な)『モンティ・バイソンのSPAMALOT』。これも『フル・モンティ』も『ヤング・フランケンシュタイン』も、老舗は手を出してこなかった作品で、avexであったりフジテレビさんであったり、インディペンデントなところとご一緒しました。東宝さんが僕を雇ってくださるのは、最初の『タイトル・オブ・ショー』からして“誰か知ってる?このミュージカル”というタイプの作品(笑)。
でもそれは嬉しいことで、“これ、日本では知名度ないけど福田だったら何とかするんじゃないか”と思ってくださったんだと思うんですね、おそらくは。おかげで、希望した人とのお仕事もかなって、『エドウィン・ドルードの謎』ではずっとご一緒したかった山口祐一郎さんに出ていただけて、“山口祐一郎さんがこんなことしてしまうのか!”と新鮮に受け止められた。そういうことがあっていろいろ(ミュージカル界から)声をかけていただけるようになったと思うんですね」
――そして今回の『シティ・オブ・エンジェルス』ですが、発案は福田さんでしょうか?
「ホリプロのプロデューサーが、長年やりたいと思っていたそうです。台本を読む前に、コンセプトを聞いた段階で(演出の)遊びどころがわかって、面白いと思えました。で、読んだらその通りだった。映画の脚本家の周辺の物語と、彼が書く台本の世界の二重構造になっていて、現実世界で文章を書き換えると、映画世界の流れが変わるというのが、絶対面白くなると想像できましたね」
――ブロードウェイ・ミュージカルではありますが、往年のTV番組『8時だヨ!全員集合』のシチュエーション・コメディのようなハチャメチャさもありますね。
「稽古では台本のレベルではおさまらなくて、既に凄いことになっています。途中からもうぐっだぐだ(笑)。でもテンポはすごくいいですよ、場面転換も早いし。
キャスティングについては今回どうしてもプロデューサーの役にコメディ・スターがほしくて、(佐藤)二朗さんを口説きました。今回は二朗さん、木南晴夏(さん)、山田優ちゃんの3人が初ミュージカルで、初めての役者さんが3人もいるって最高ですよ。“どうしよう、これ……”っていう新鮮さ。(今回、w主演を勤める)山田(孝之)君が『フル・モンティ』の時にそうだった。“じゃあ、ゆっくり粗立ち(注・ざっくりとした立ち稽古)してこうか”といったら、(心配そうに)“その粗立ちって、どのくらい粗いですか……”って(笑)。で、舞台だと客席に向かって喋るけど、映像だったら共演者が横にいれば絶対そっちを向くから、すごく違和感があったらしくて、一つ一つが新鮮。
今回の優ちゃんや木南も、舞台は見慣れてるとはいえミュージカルの何たるかは経験していないので、そこの新鮮味はあると思う。お客様に、彼女たちもミュージカル出来るんだ~、やっぱりミュージカルっていいよね、面白いよねという目で観てもらえると最高です」
――演出、あるいは台本に関してこだわった部分はありますか?
「(劇中劇が)ハードボイルドものなので、洋もののかっこよさが欲しいと思って、翻訳家さんが上げてこられた台本の口調を少し残しました。翻訳台本って、洋画の字幕のような、ふだんの会話では出てこないような独特の語調で書かれているので、それを適宜書き直して上演台本にしていくんですね。『SPAMALOT』の時には全部僕のほうで口語体に直したけど、『フル・モンティ』ではミュージカル風の口調として、4割くらい残してみたら、“(福田は)ちゃんとミュージカルを作れるんだな”と見ていただけたようで、それから火が付いたようにミュージカル演出の依頼が来るようになりました。今回も、翻訳台本の語調を少しだけ残しています」
――ギャングものという点で、今年手掛けられた『ブロードウェイと銃弾』との連続性を感じる方も多いかと思いますが。
「 (『ブロードウェイ~』とは)構造的にちょっと違っていて、人間ドラマとしてヘビーなのが『ブロードウェイ~』。浦井(健治)君のやった役って、つらいじゃないですか。戯曲を自分で書いてないのに書いたふりして、それをどんどん受け入れざるをえなくなるというのが人間の業だし、ウディ・アレンらしいですよね。
今回はそれほどの重さはなく、いろんなキャラクターが集まってひとつの物語が出来ていくという状況なので、たぶんそこまで重厚ではないと思う。カッキー(柿澤勇人さん)演じる脚本家がプロデューサーに言われて、台本を直す、直さないの連続で、『ブロードウェイ~』ほどには葛藤しない。本作は完全な二重構造なので、ヒューマン・ドラマをそこまで追っていくとたちゆかなくなる、ということもあるんじゃないかな」
――クリエイターの性(さが)を描いた部分もありますが、同じクリエイターとして感じるところがありますか?
「脚本家に対してその妻が口を出す様子が、我が家に似すぎていて、上演台本を書いてて辛かったですね~(笑)。あの場面は3倍にも、4倍にも膨らませられます。僕の背後には嫁がいてその存在がかなりでかいというのは世間に広まりつつあって、ツイッターで、“福田監督、ナイスキャスティング。というか嫁か”というつぶやきが来たこともあった(笑)。
彼女は勘がよくて、キャスティングをだいぶ彼女に頼ってます。例えば映画『銀魂』の沖田役って、原作ではすごい人気があって、下手な奴は入れられない状況だったけど、うちの嫁が絶対、吉沢亮じゃないとダメだと。当時、吉沢君はそこまで有名じゃなくて、僕としては勇気が出なかったけど、それから快進撃で今や完全な売れっ子じゃないですか。
ミュージカルについても、まず彼女と息子がNYに行った時にたまたま『ライオンキング』を観て完全にノックアウトされた状態で帰ってきて、野球にも何にも興味なかった息子が“僕はライオンキングになる!”と言いだして、ダンスと歌を始めたくらい(注・ご子息はその後実際に劇団四季『ライオンキング』にヤングシンバ役で出演)。その勢いに巻き込まれて僕もミュージカルを観るようになって。全部、嫁の指令で動いているようなものです(笑)」
――ミュージカルでこういうことをやっていきたい、というビジョンはお持ちですか?
「ミュージカルと映像をどっちもやってる演出家は今のところ僕だけだと思うんですが、ミュージカルって、日本で認識されてきたものの、やっぱり少し敷居が高いと思われがちですよね。そういうなかで、映像の世界からミュージカルができそうな人をつれてきて、ミュージカルの見え方が少しでも変えられたらとは思っています。“ドリフターズの公開収録みたいな感じで観に来ていいんだぜ”というものに落としこんでいくというのは、一個の目標というか。
“使命”とまではしょいこんでいないけど、やろうと思って実際やれるのは今の時点では僕だけだと思うので。例えば小栗旬君がミュージカルに出るなんて誰も思ってなかったと思うけど、僕が誘ったから(『ヤング・フランケンシュタイン』に)出てくれたと思う。そういうことはこれからもやっていきたいです」
『シティ・オブ・エンジェルス』公式HP
*次頁で『マリー・アントワネット』をご紹介します!