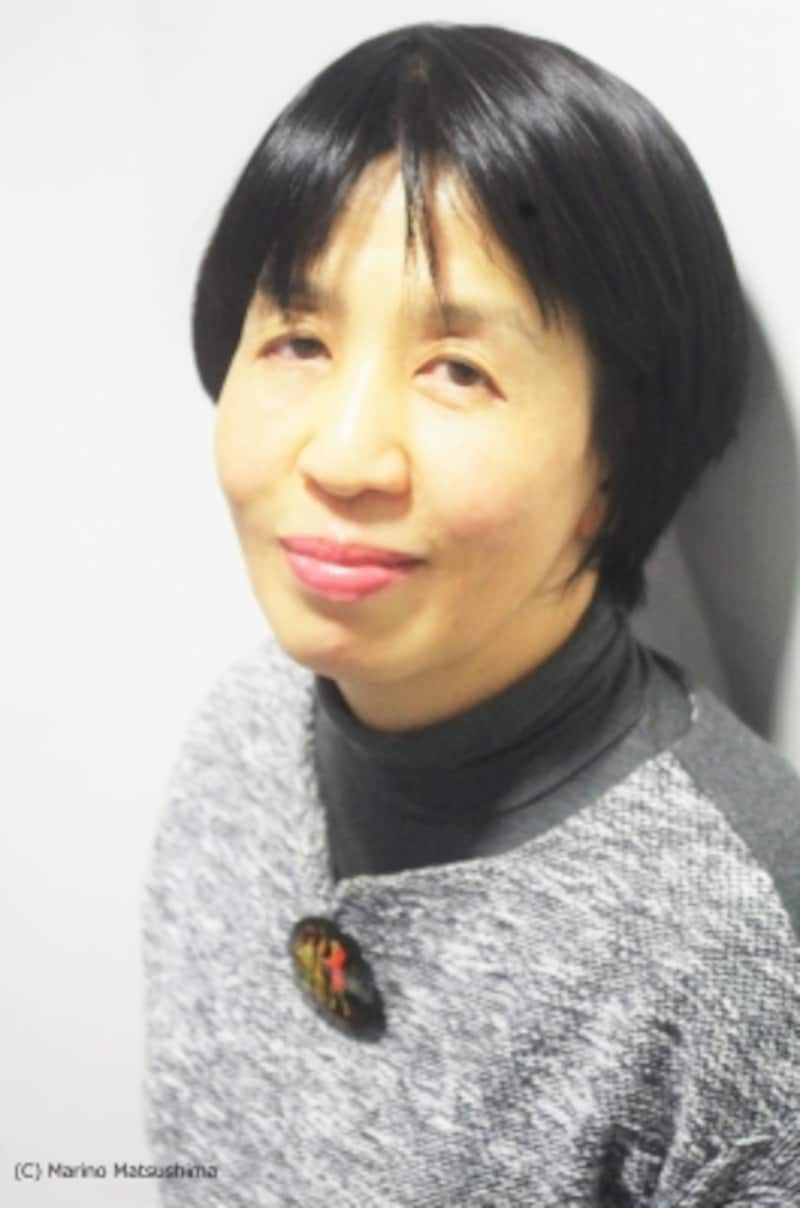
高橋知伽江 新潟県出身。東京外国語大学ロシア語学科卒業後、一般企業を経て劇団四季に入社。秘書兼演出助手、広報、国際などの業務をこなしながら台本執筆や翻訳(『クレイジー・フォー・ユー』等)にも携わる。97年に独立以来、様々な戯曲の執筆、翻訳、訳詞を手掛ける。13年より水戸芸術館演劇部門芸術監督。(C)Marino Matsushima
唯一の肉親である兄が人を殺め、突然犯罪者の家族となってしまった高校生、直貴。それからの彼の心の軌跡を丁寧に描き、直木賞候補となった小説が東野圭吾さんの『手紙』です。幸せを掴もうとするたび運命に阻まれ、煩悶の中で生きてゆく主人公の物語は極めて重く、およそミュージカルという表現形態には縁遠くも感じられますが、その「まさかのミュージカル化」が実現! 直貴役に三浦涼介さん、兄・剛志役に吉原光男さん(『レ・ミゼラブル』)というキャストを得て、間もなく開幕します。
年末のある日訪れた稽古場では、獄房をイメージしているらしいセットの前で、一つのシーンが形作られていました。3人の男女が真剣な表情で語りあい、時折、位置を確認するように動いていますが、語りあう内容までは聞こえて来ません。「では行きます!」と演出助手の声がかかると、そこから一人――演出の藤田俊太郎さん(14年『The Beautiful Game』)――が抜け、直貴と工場の同僚・由実子のシーンがスタート。大学進学を諦め、心を閉ざした直貴に由実子は一つの可能性を提案するものの、彼の頑なな心は容易には解けない…。
絶望の中にわずかな光明を見出す重要なシーンであることが、三浦さん演じる直貴の発する張り詰めた空気、北川理恵さん演じる由実子の切々とした歌声から伝わってきます。じっくりと、入念に一つ一つの場面が作り上げられていることを感じながら、スタッフ席で稽古に参加していた高橋知伽江さんと取材室へ。あの『アナと雪の女王』の訳詞で知られ、昨年開幕した劇団四季の『アラジン』でも訳詞を担当。水戸芸術館演劇部門の芸術監督でもある彼女が、このプロジェクトの発案者にして脚本を担当しているのです。
ミュージカルならではの手法で描く「他人事ではない、自分にも起こりうる物語」
――ミュージカル版『手紙』を発案された経緯からお話いただけますか?ミュージカル『手紙』
――ミュージカルでは森羅万象、様々な物語が表現されますが、それでも今回の『手紙』は極めて重く、およそミュージカル化が想像できない素材です。ご自身の中ではどんな「勝算」があったのでしょうか?
「ミュージカルには似つかわしくないと思う人もいるとわかっていましたので、ミュージカルの手法を駆使して、原作のメッセージがきちんと伝わるものを作らないとだめだ、と認識していました。確かに一般的なミュージカルは、結末の白黒がはっきりしていたりとか、明るく楽しいものが多いですね。でも、ミュージカルは歌が入ることで飛躍が可能になります。
たとえば先ほどご覧いただいたシーンも、リアルに(会話の内容をストレートプレイで)やったら30分でもおさまらないと思いますが、ああいうふうに歌を使えば短い時間で描くことが可能ですし、別々の場所にいる兄弟の感情も、デュエットさせることで同時に表現できます。こういった手法をフルに使えば、この作品はうまくミュージカルとして立体化できると、最初から思っていました」
――しかし「犯罪者の家族」がその十字架を背負い、絶望の中でどう生きてゆくかという物語は非常にシリアスですよね。
「映画を観たときに、私は“これは誰にでも起こりうる悲劇だ”と思いました。お兄さんだって殺そうと思っていたわけではなく、なりゆきでそう追い込まれてしまったわけですし、弟はそのためにある日突然、人生が裏返ってしまう。こういうことは誰にでも起こりうる、他人事ではないと思えました。
特に昨今はテロというものが日常の中に入り込んできていて、本当に人生いつ裏返ってしまうかわかりません。今回の作品にテロは出しませんが、そういう状況はこの原作が書かれた時よりもっと起こり得ることになっていると思うので、原作はしばらく前の話だけど、この舞台は「今」の話だということは、俳優たちにも稽古でお話しました」
ミュージカル『手紙』
「原作との違いという点では、原作は弟の視点からしか書かれておらず、お兄さんがどう思っていたかというのは手紙からしかわかりません。東野さんはエッセイで、本作が直木賞候補に挙がったが受賞できなかったのは、お兄さんの手紙の内容が暢気すぎると受け止められたためだと書かれていました。でもそれは、刑務所では手紙にも検閲が入るので、当たり障りのないことしか書けないせいなのです。それを知らないと、“弟がこんなに苦しんでいるのにお兄さんは暢気すぎる”と思われてしまう。けれどお兄さんの暢気な手紙の裏には苦悩があったはずだと思いましたので、今回の脚本には弟の視点、兄の視点が両方入っています。お兄さんも10年間何を思って生きてきたかを描いていて、そこが一番原作と違うところだと思います」
――配役は台本が書きあがった後のことだそうですが、役者さんからインスピレーションを受けて手をいれたりは?
「稽古場の中で役者たちがいろいろ発言しますので、それを取り入れた部分もあります。吉原(光夫)さんはじめ、皆さん感じたことは自由に言いますね。黙って演出を受けているような現場ではなく、みんなで話し合って芝居を作っています」
――作曲は深沢桂子さん。今回はどんな音楽でしょうか。
「もう何本もご一緒している方ですので、私のほうから“こういうものを”というリクエストはせず、基本的には彼女が台本から受けたインスピレーションで書いていただきました。今回は非常に多彩な音楽で、彼女が好きなロックが基調ですが、バラードもサンバもあり、激しいものから悲しいものまで、いろいろな曲をお聴きいただけると思います」
――どんな舞台になりそう、あるいはしたいと思っていらっしゃいますか?
「観る人に“これは今の自分たちが生きている世の中のことだな”と感じてもらえるといいですね。その中で自分たちがどういうふうに生きるのかということを、観終わった後にいろんなふうに考えていただけたら嬉しいです。結末について、あの兄弟があの後どうなっていくかについてはお客様に委ねていますので、一緒に観た人と話したり、思い返したりしていただければ。そういう意味では、一般的なミュージカルとは一味違うミュージカルです。その人の心に波紋を残す作品になるかなと思っています」
*次頁から高橋さんの「これまで」を伺います。なりゆき(?)で劇団四季に入社し、ある日脚本執筆の喜びを知った高橋さん。しかし実際に大作に携わるようになるまでには、長い下積みがあったそうです。








