高校受験の入試過去問はいつから、何年分解けばいい?
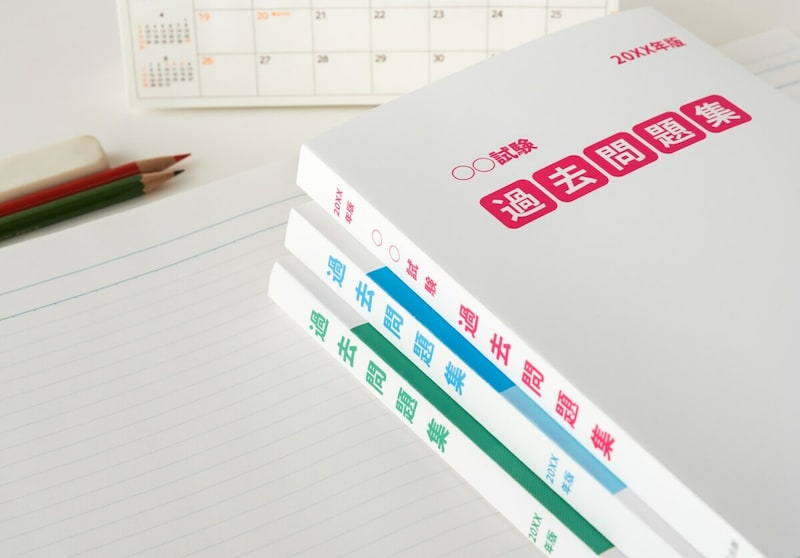
高校入試の過去問を解くことで、入試までにそれぞれの科目をどのように勉強すればいいのかがはっきりしてきます
過去問を解くことによって、高校入試までにそれぞれの科目をどのように勉強すればいいのかがはっきりしてきます。志望校合格につなげる過去問の解き方を紹介します。
<目次>
高校入試の過去問活用コツ1:単元学習を終えた科目から解く
過去問は、単元学習を終えた科目から解きましょう。すぐに取りかかることができるのは国語です。まずは国語から解くのがいいでしょう。単元学習を終えていない科目の過去問を解くと、全くわからない問題が出てきます。そうすると解き終えた後に採点しても、合否の判断材料としての目安にならなくなります。単元学習を終えた科目から解いて採点し、その学校と年度の入試合格者最低点とつき合わると、その学校と今の自分の得点力との差がどれくらいかがはっきりします。高校入試の過去問活用コツ2:古い年度の入試問題から解く
市販の高校入試過去問題集にはたいてい5年分くらいの過去問が入っています。過去問は最初のページの最新年度から解きがちですが、新しい年度ほど実際に受ける入試の出題傾向に近づきます。まだ入試問題で要領よく点数を取る訓練ができていないうちには、最も古い年度の問題で慣れてください。最新年度の過去問を解くのは、高校入試直前の年明け、受験勉強総仕上げのときのために取っておきましょう。高校入試の過去問活用コツ3:実際の入試時間と同じ制限時間内で解く
過去問を解く際は、タイマーを用意しましょう。そして実際の入試と同じ制限時間内で解いてください。時間内に解き切れなくてもそこでいったん終了してください。鉛筆、シャーペンから青ペンに持ち替えましょう。制限時間を超えて解いた問題の答えは青字で書き、時間内に解いたものと区別できるようにしておくといいです。制限時間内に解いた得点と、時間を超えて解いた総得点の、それぞれ点数を出しましょう。その差を埋めるには時間配分をどうすればよいか。解く時間を短縮するにはどうすればよいかを工夫していくことが今後の課題です。高校入試の過去問活用コツ4:問題の復習はあとまわしOK
「過去問で分からなかった問題をできるように復習しないと」と考えがちですが、もっと先にやった方がいいことがあります。それは「分かっていたけれどできなかった問題」、すなわちケアレスミスの見直しです。問題の意味を取り違えたり、答え方が問題で指定されている答え方とずれていたりすることはよくあることです。問題のどこに線を引けば、そのミスを防げたのか。次似たようなミスをしないようにするにはどうすればよかったのか、ミス撲滅にむけて対応策をとりましょう。各科目のケアレスミスをすべてなくせば数十点分になります。わからない問題を解けるようにするのはもちろん大事ですが、時間がかかります。入試まで残された期間でできるようにしてください。
高校入試の過去問活用コツ5:塾通いの人は授業で扱う入試問題を聞く
塾に通っている人は、授業で扱う高校入試問題を聞いておきましょう。2学期以降は授業の中で過去問を扱うことがあります。その問題を自分で先にやってしまうと、得点を出しても合否判断基準としての目安にならなくなります。その問題は授業まで解かないでおきましょう。今後授業で自分の第一志望の学校の過去問を扱う予定があるか、扱うのならどの年度の問題を使用するのかを各担当の講師に聞いておくといいでしょう。いかがでしたでしょうか。過去問は入試に合格するための「切り札」です。高校入試までに第一志望校の過去問は何度も解き直しをすることで合格の確率を上げることができます。志望校の入試の専門家になるような姿勢で過去問に取り組みましょう。よくなかった模試の合格判定をくつがえす結果を出している受験生の共通点です。応援しています。
【関連記事】






