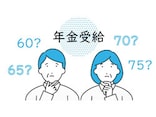離婚時の年金分割制度 よくある誤解
離婚時の年金分割制度の関心の高さもさることながら、誤解の多さもよく指摘されています。そこで、ここで誤解の多いポイントを整理しておきます。■分割されるのは、あくまで厚生年金部分のみ
平成19年4月スタートの制度については、年金分割の対象はあくまでも厚生年金部分のみです。例えば、夫がずっと自営業を営んでいて、厚生年金に全く加入していないような場合は、分割する年金がありません。逆に妻が厚生年金に加入している場合は、妻の厚生年金が夫に分割されることも有り得ます。
■自分自身で年金受給権を満たす必要がある
離婚して年金の分割が決まったといっても、年金が支給されるのは原則65歳からです。また、自分自身が保険料を滞納したりして原則25年の受給資格期間を満たしていない場合は、年金は支給されません。分割される部分とは別に、自分自身で受給資格を満たす必要があります。
■死亡や再婚で権利は消滅しない
離婚後、年金を受け取るまでに分割した相手である元配偶者が死亡したり、あるいは本人が再婚したりしても権利は消滅しません。これはありがたいですね。
離婚時の年金分割制度の手続方法
■3号分割(平成20年4月からスタート)当事者(第3号被保険者である人)からの請求により、強制的に2分の1に分割される(強制的に2分の1に分割されるものの、請求がなければ分割は行われないことに注意が必要です)
■合意分割(平成19年4月からスタート)
まず夫婦間の同意が必要となる。夫婦間の同意を証明するために公正証書等の作成が必要。同意が得られない場合は、裁判手続により家庭裁判所で分割割合を決められることになります。同意あるいは裁判所の決定があったとしても、年金事務所に請求の手続をしなければ実際の分割は行われません。
また分割割合を証明する書類を添付して年金事務所に分割請求する必要があります。この分割手続については、離婚時に行うことが必要です。離婚成立後2年以内に請求する必要がありますのでご注意ください。
【関連記事】
・離婚時の年金分割を検証
・年金を受け取る手続と注意点
・主婦のための年金アレコレ