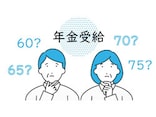「保険料水準固定方式」とはどんな方式
 |
| 今後100年安心できる年金制度にするたもの改正らしいが、実際は苦肉の策のオンパレードのように見えるのは何故? |
この方式を採用することで、保険料の引き上げはある一定の段階で押さえられますので、「給付水準維持方式」のような際限ない保険料のアップはまぬがれます。しかし、保険料収入の範囲内でしか年金給付を行わないわけですから、年金を受け取る人が確実に増えている日本においては、一人当たりの年金給付の水準は当然下がってしまうことになります。
平成16年年金法改正によると国民年金の場合、現在月額13,860円の保険料を毎年280円ずつ引き上げ16,900円で固定します。また厚生年金の場合、給料や賞与に対する保険料率を平成29年までに段階的に引き上げ、18.30%(現在14,80%)で固定することになりました。
「保険料水準固定方式」の大きな問題点
制度の説明を見ればわかるように、この「保険料水準固定方式」は保険料収入が上がれば給付水準は引き上がり、収入が減れば水準が下がりますので、将来の給付水準が不透明になったという問題点があります。この問題に対し、国は、モデル世帯(夫サラリーマン、妻専業主婦)で、現役世代の収入の50%は確保されると宣言していますが、甘い出生率予想に基づくもので、この約束を守れるかどうかについても非常に危うい状況です。
また、固定される保険料についても、そもそも現在よりもかなり引き上げた状況で固定しますので、現在よりも負担が増えます。また改正で保険料額に物価や賃金上昇率に応じた「改定率」を乗じることとなったため、固定されたといっても、改定率によっては、支払額が増える可能性もあります。
現役世代の負担を減らすために導入された「保険料水準固定方式」ですが、結局減るであろう年金水準を受け入れるもの今の現役世代であるという皮肉な結果になってしまうんでしょうね。
これからの日本の年金財政の危機的状況をソフトランディングするために保険料を徐々に引き上げ、給付を徐々に引き下げるという折衷案として導入された「保険料水準固定方式」ですが、「問題の先送り」でいかにも日本的な処理に思えます。
根本的な問題が残る限り、このような日本的な処理がずっと続くのでしょう。
【関連記事】
良くなったこともあった!年金法改正を検証
国の言う「モデル年金」の問題点を検証