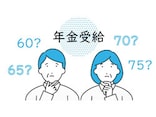50年代は水準の維持、60年にとうとう引き下げが
 |
| 今回の記事は、厚生労働省のデータ「給付水準の推移」からの検証だが、記事にもあるように前提がコロコロ変わっているため注意が必要 |
詳しく見てみると
昭和48年 平均加入年数 27年
所得代替率 62%
昭和51年 平均加入年数 28年
所得代替率 64%
昭和55年 平均加入年数 30年
所得代替率 68%
昭和60年 加入年数 40年
所得代替率 69%
となっています。48年、51年、55年と所得代替率は高くなっていますが、同じようにモデル年金の加入年数が伸びています。加入年数が多くなれば、それだけ年金額も多くなって当たり前なので、これは「改善」というより「維持」と言った方が正しいでしょう。
それが昭和60年になると、加入年数が40年となり、55年よりも加入年数が10年も多くなっているのに、所得代替率はほとんど変わりません。
ここで、事実上の「給付の引き下げ」が行われたことがわかります。
60年に続き、平成12年に大きな引き下げが
この昭和60年と言う年は基礎年金制度の導入等抜本的な制度変更があったのですが、データのモデルについても大きな変更がありました。昭和55年までの年金額は、「夫に支給される厚生年金」での数字だったのに対し、昭和60年からは、「夫婦2人の基礎年金(国民年金)と夫の厚生年金の合計」、要は現在の「モデル世帯」での水準に何故か変更されています。
ですから、所得代替率はここでも一見維持しているように見せかけていますが、実はかなりの引き下げがあったことがわかります。
また、平成12年には給付乗率の5%適正化(要は厚生年金の引き下げ)というものを行っています。平成12年の所得代替率59%は、計算方法を変えたもので、それまでの計算方法で算出すると約65%となります。加入年数は変わりませんので、ここでも給付の「引き下げ」を行っていることになります。
今回検証した、厚生労働省が試算している「給付水準の推移」というデータからわかることをまとめると、
■大まかなイメージとして
昭和40年代 「給付水準の改善」
昭和50年代 「給付水準の維持」
昭和60年以降 「給付水準の引き下げ」が行われた。
そして、
■公的年金の「絶頂期」は
夫のみの年金、加入期間30年で所得代替率が68%あった「昭和55年」だった。
しかし「推移」と言いながら計算根拠が連続していない、いかにも「お役所データ」ですね。このあたりもう少し改善していただきたいものです。
【関連記事】
国の言う「モデル年金」の問題点を検証
30年後、俺達が受け取れる年金は月17万円!