仕事・給与 人気記事ランキング(2ページ目)
2026年02月20日 仕事・給与内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
11位SOHOでは「103万円の壁」はない?
SOHOや在宅ワークは家事や育児との両立がしやすい人気の働き方。配偶者控除や所得税のことを考えて年収103万円以内に……と思っていては大間違いですよ。在宅ワーカーには103万円の壁は通用しません!
 仕事・給与関連情報ガイド記事
仕事・給与関連情報ガイド記事12位全額還付になる人ってどんな人? 給与所得のみの中途退職<3>
世の中には確定申告さえすれば全額還付になる人もたくさんいます。そんな人たちに当てはまる人って?
 仕事・給与関連情報ガイド記事
仕事・給与関連情報ガイド記事13位ホワイトカラー、ブルーカラーって何?給与に違いは?
仕事内容や働き方でホワイトカラー、ブルーカラーと言われますが、そもそもどういう意味なのでしょうか?ホワイトカラーとブルーカラーで給料はどのように変わるのでしょうか?初任給や賃金で確認してみましょう。
 給与明細の見方ガイド記事
給与明細の見方ガイド記事14位地方公務員の手当は何がある?
国家公務員よりも給与水準の高い地方公務員。その理由のひとつが手当といわれています。かつてはトンデモ手当といわれるものもありましたが、現在はどうなっているのでしょうか? 総務省から発表された「令和3年地方公務員給与実態調査結果等の概要」の報告をもとに、地方公務員の手当事情についてご紹介しましょう。
 仕事・給与関連情報ガイド記事
仕事・給与関連情報ガイド記事15位厚生年金保険料が上がる?4月、5月、6月の給与にご注意
サラリーマンのみなさんは毎月の給与から厚生年金保険料が引かれているかと思いますが、この保険料を決めるのに4月、5月、6月の給与がかかわっていることをご存じでしょうか。今回はこの厚生年金保険料が決められるしくみについて解説してみたいと思います。
 給料・給与の基本ガイド記事
給料・給与の基本ガイド記事16位年収300万・400万・500万円の手取りはいくら?違いを分かりやすく解説
年収、所得、手取りの違いについて、皆さんは正しく理解しているでしょうか。今回はそれぞれの言葉の違いを解説し、会社員における年収別の手取り月額を計算してみました。※サムネイル画像: PIXTA
 ガイド記事
ガイド記事17位国家公務員の平均年収はどれくらい?
国家公務員には、国会や裁判所、財務省や文部科学省をはじめとした各省庁の職員のほか、自衛官や刑務官など実にさまざまな職種があります。一般的に「安定した職業」と言われますが、平均年収はどれくらいあるのでしょうか? 本記事では人事院の「国家公務員給与等実態調査結果」などをもとに、国家公務員の平均年収を詳しく見ていきます。
 ガイド記事All About 編集部
ガイド記事All About 編集部18位都道府県別「平均年収」ランキング! 1位は476万円の東京都、最も上昇幅が大きい2県は?【2025年最新】
パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda(デューダ)」は、「平均年収ランキング2025」を発表。各年代の前年からの上昇幅は20代、30代がアップ、40代、50代以上はダウン。最も平均年収が高かった都道府県は?
 ガイド記事All About 編集部
ガイド記事All About 編集部19位106万円の壁が消えた!? 最低賃金アップで社会保険の加入ラインが激変
「扶養内で働きたいから、月8万8000円を超えないように調整しなきゃ……」。こうした106万円の壁を意識した働き方をしている人は少なくありません。しかし近年、最低賃金が大幅に引き上げられたことで、社会保険加入条件のうち「賃金要件」は実質的に意味を持たなくなってきました。※サムネイル画像:PIXTA
 ガイド記事
ガイド記事20位超危険!フリーターの将来設計!
フリーター人口が10年前と比べると2倍、417万人もいるそうです。確かにフリーターも生き方のひとつ。しかし、フリーターの将来はこんなにシビア! それでもあなた、フリーターでいいの?
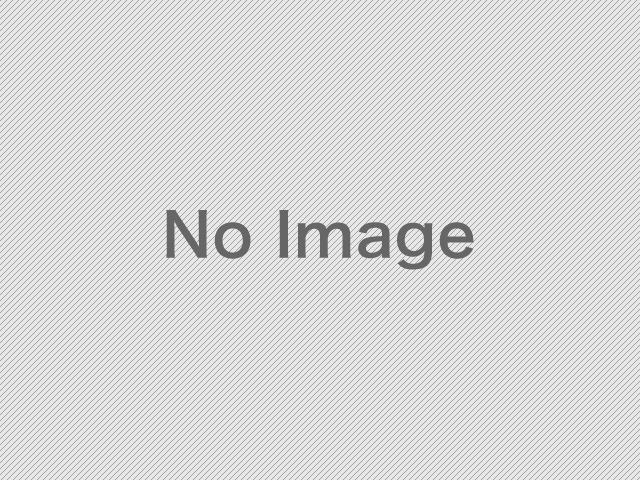 仕事・給与関連情報ガイド記事
仕事・給与関連情報ガイド記事