資格・スクール
建築・不動産・インテリア系の資格 新着記事一覧(7ページ目)
早めの対応が肝心!管理費滞納問題
築年数が進んだマンションほど発生しやすいのが、管理費等の滞納問題です。滞納の長期化、滞納金額の増加は管理組合の運営に深刻な影響を及ぼしかねないので、初期段階での対応が重要となってきます。
 マンション管理士とは・仕事内容ガイド記事
マンション管理士とは・仕事内容ガイド記事平成26年宅建試験 分析と正答率・次年度の傾向と対策
平成26年度の宅建試験を振り返り、問題ごとの受験者正答率、合格者であれば解ける可能性の高い問題等、今年の宅建試験の傾向をまとめました。また、平成26年の宅建業法改正に関連し、来年度の宅建士試験に向けた学習方法についても、最後に触れております。この記事で法改正による宅建試験の新傾向を知り、試験対策に役立てて下さい。
 宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事
宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事マンション管理士の仕事(8) 空き駐車場問題への対応
昨今では、マンションの駐車場に空き区画が目立つ例も珍しくありません。駐車場の稼働率が下がれば、おのずと管理組合の台所事情は厳しくなり、最終的には区分所有者の負担増となって跳ね返ってきます。稼働率低迷の理由はマンションによって多少異なるため、原因の分析から問題解決のためのアプローチの方法をご案内します。
 マンション管理士とは・仕事内容ガイド記事
マンション管理士とは・仕事内容ガイド記事平成26年度宅建試験 新判例に学ぶポイントと出題予想
宅建試験の問1から問14までは、民法、建物区分所有法、借地借家法、不動産登記法から出題されています。民法からは10問の出題があり、そのほとんどが判例(最高裁判所が理由付きで判断した判決や決定のこと)から出題されます。特に、新しい判例は実務で問題視されていたところなので、当然に宅建試験にもよく出題されます。この記事を通じて最新判例をマスターしましょう。
 宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事
宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事重要論点と求められるレベル4 管理適正化法
マンション管理士試験の最後に出題されるのが、マンション管理適正化法の5問です。管理業務主任者試験の合格者はこの5問が免除されますので、初挑戦の受験者にとっては不利と言えます。ただ、他の分野と異なり出題範囲が狭く、難問も出されないので、5点満点を目標に対策したいものです。
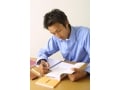 マンション管理士の試験・勉強法ガイド記事
マンション管理士の試験・勉強法ガイド記事平成26年度宅建試験 法改正と予想問題2~税法
平成26年宅建試験では、同年4月1日までに施行された法律が出題されます。特に、税法はほぼ毎年改正されているので、改正情報に注意しなければなりません。この記事では、所得税、印紙税の改正点について解説し、予想される出題内容を紹介しております。
 宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事
宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事平成26年度宅建試験 法改正と予想問題1~業法・民法
平成26年宅建試験では、同年4月1日までに施行された法律が出題されます。特に、法律が改正されたところは、実際の不動産取引実務で問題視されていたことなので、これから宅地建物取引主任者(宅地建物取引士)になろうとする人が知らないというのでは困ります。しっかりと改正点を整理して覚えておきましょう。まずは、宅建業法と民法の改正点からです。
 宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事
宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事マンション管理士の仕事(7)マンション保険の見直し
管理組合がマンション保険に加入する際、管理会社が代理店になるケースが多く見られます。ただ、実際の契約をチェックすると、保険料や補償プランについて必ずしも最適な選択になっていないことが少なくありません。今回は、マンション保険を見直すポイントについてご案内します。
 マンション管理士とは・仕事内容ガイド記事
マンション管理士とは・仕事内容ガイド記事平成26年度宅建試験 統計問題対策の資料
平成26年度(2014年度)宅建試験の免除科目で出題される不動産の需給に関する統計資料です。頻出分野の数字や傾向を暗記して、宅建試験会場に行ってください。
 宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事
宅建試験に合格するための勉強法ガイド記事重要論点と求められるレベル3 建築設備
マンション管理士試験で、管理の実務経験に乏しい事務系の受験者が苦労しがちなのが、建築設備分野です。都市計画法、建築基準法などの関連法規から、給排水・消防などの各設備知識、建物調査診断や修繕の方法まで幅広く、かつ奥が深いのが特徴です。ただ、高得点を狙うあまり深追いするのはお奨めしません。頻出テーマを中心に学習を進めて、7割以上の得点を目指して準備しましょう。
 マンション管理士の試験・勉強法ガイド記事
マンション管理士の試験・勉強法ガイド記事