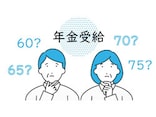今回は、繰り上げ受給を検討するときに知っておきたい基本と注意点を紹介します。
年金の繰り上げとは?
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取る仕組みですが、希望すれば60歳から受給を始められます。これが「繰り上げ受給」です。ただし、早くもらえる代わりに受給額は一生減額されたままになる点に注意が必要です。減額率は、1962年4月2日以降生まれの方で「0.4%×(65歳までの月数)」、最大で24%の減額となります。※1962年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%(最大30%)。
反対に、年金の受け取りを65歳以降に遅らせる「繰り下げ受給」を選ぶと、受給額が増える仕組みになっています。70歳まで繰り下げれば42%、75歳まで繰り下げると84%も増額されます。
「繰り上げ」「繰り下げ」は、どちらが得というよりも、今の収入・健康状態・ライフプランによって最適な選択が変わります。早めに年金を受け取る場合には、しっかりと注意点を理解してから判断することが大切です。
年金の繰り上げをする前に7つの注意点を確認しておこう!
年金の繰り上げを検討するときは、次の7つの注意点があります。①一度手続きしたら取り消しできない
繰り上げ受給は、手続きをした瞬間から年金額が確定します。減額された年金が一生続くため、「やっぱりやめたい」と思っても後から取り消しはできません。慎重に判断しましょう。
②任意加入や追納ができなくなる
60歳以降も、任意加入制度を利用して国民年金の納付期間を増やしたり、未納分を追納したりして将来の受給額を増やせます。しかし、一度繰り上げ請求をしてしまうと、任意加入も追納もできなくなるため、納付期間を増やしたい人は、繰り上げの前に確認が必要です。
③雇用保険との併給はできない
65歳前に失業給付や高年齢雇用継続給付金を受け取る場合、老齢厚生年金と同時にもらうことはできません。その場合、年金の一部または全額が一時的に支給停止になります。老齢基礎年金は停止されませんが、働き方や給付金の有無に注意しましょう。
④厚生年金に加入して働くと支給停止になることも
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与・賞与と年金の合計額によっては、老齢厚生年金が一部または全額停止になることがあります。老齢基礎年金は受け取れますが、「働きながら受け取れるか」は事前確認が必要です。
⑤遺族年金と併給できない
配偶者が亡くなった際に支給される遺族厚生年金や遺族共済年金を受け取っている場合、65歳未満の期間は老齢年金と同時に受け取れません。どちらか一方の選択が必要です。
⑥寡婦年金を受け取れなくなる
夫を亡くした妻が60~65歳の間に受け取れる寡婦年金も、繰り上げ受給をすると支給対象外になります。60歳以降に繰り上げを考えている方は、この点も忘れずに確認しておきましょう。
⑦障害年金を請求できなくなる
障害年金は、病気やけがで一定の障害が残ったときに受け取れる年金ですが、繰り上げ請求をした後は障害年金の新たな請求ができなくなります。治療中や持病がある人は、健康状態をよく考慮したうえで判断を。
参照:日本年金機構「年金の繰上げ受給」
年金を繰り上げ受給するのに向いている人の特徴は?
65歳から受け取るよりも受給額が減額されるため「損をする」と思われがちな繰り上げ受給ですが、状況によっては有効な選択になることもあります。例えば、
・老後資金がほとんどなく、すぐに生活費を補いたい人
・健康状態が不安で、早いうちに年金を受け取りたい人
・定年後に働く予定がなく、収入源が年金だけになる人
・家族の介護やローンの支払いなどで、早期の現金収入が必要な人
このようなケースでは、繰り上げによって生活の安定を図るメリットがあります。
ただし、長生きするほど受け取る総額は少なくなるため、「今の生活の安定」と「将来の年金額」のバランスをしっかり考えましょう。
まとめ
繰り上げ受給は、生活資金を早く得られる半面、一度決めたら元に戻せない“慎重な決断”が求められる制度です。今すぐお金が必要なのか、それとも数年後の安定を優先するのか。ライフプラン全体を見渡して判断しましょう。