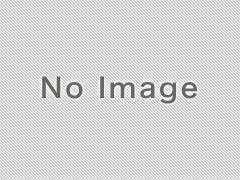各コートに審判員を配置するだけの人的、経済的余裕のない地域レベルの大会では、参加している選手が審判を務めることが多い。リーグ戦の場合は試合のない選手(チーム)が審判になり、トーナメント戦の場合は試合に負けた選手が審判を務める「敗者審判」で、運営のやり繰りをしているケースが一般的だ。
このシステムが混乱を来たす火ダネとなりかねない。
審判員の資格を持たない人間がジャッジを下すのである。
もちろん、それでもそのシステムが機能してきたではないか、という意見もあるだろう。だが、それは卓球のルールが比較的「白黒」のはっきりしたものだったからだ、と思うのだ。
過去の世界選手権の結果をみても明らかだが、サッカーなどでしきりに強調される「ホームアドバンテージ」が、卓球にはほとんど当てはまらない。強い者が勝っている。ルールに「解釈」の入り込む余地の少ない何よりの証左である。
乱暴を承知でいえば、誰が審判を務めても結果は変わらないと思われるほど、卓球はすぐれた判定マニュアルを備えているのである。それが、崩れかねない。
 レシーバーから「ボールが見えなかった」とクレームがついたとき、審判をしていた選手はどうするのか。ルール上は審判に判定を下す権限があるのだから、そこで毅然とした態度でジャッジできる人なら問題はない。
レシーバーから「ボールが見えなかった」とクレームがついたとき、審判をしていた選手はどうするのか。ルール上は審判に判定を下す権限があるのだから、そこで毅然とした態度でジャッジできる人なら問題はない。しかし、今回の場合、事が事だ。見えた、見えないという極めて個別的な感覚を判定しなければならないのである。しかも、視線の角度がおよそ「45度」違うのだ。
決まりごとを順守することに類いまれな能力を発揮する日本人は、一方で、責任の伴う判断を委ねられることが恐ろしく不得手である。日本人の気質を考えたとき、審判をする選手がたまたま審判員の資格を持っているという僥倖にでも恵まれない限り、「レット(やり直し)」などという判定が下されかねないような気もする。
誤解を恐れずに言おう。「誤審」はあっていいのだ。
人間という不完全な存在が判定する限り、誤りは常につきまとう。逆にいえば、人間に判定を委ねているということは、間違うこともあることを前提に、それでもその判定を尊重してゲームを進めていこう、ということなのである。そうでなければ、卓球というスポーツは成り立たない。
〈関連記事〉
02~03年スーパーサーキット開幕特集(1)夢の舞台を彩る豪華な役者たち
02~03年スーパーサーキット開幕特集(2)三田村宗明「極みへのルート」