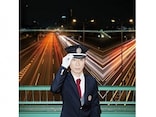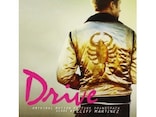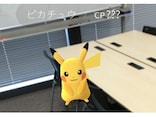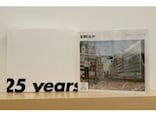伝統と革新
博士:じゃ、どうしたらいいのですか?
先生:
伝統と革新を両立させるのです。Perfumeが、本質的にPerfumeらしくあるための普遍的な部分というのはキープしないといけません。例えば、Perfumeのエクィティがテクノポップであるならば、テクノポップという部分はあくまでもはずさない(もちろん、それ以外の選択肢もあります)。しかし、Perfumeが売れたことで、Perfumeのフォロワーは当然出てきます。それはそれで上手く回れば、相乗効果もあるんですけどね。でも、下手をするとカテゴリー自体が陳腐化してなんだか終わったなみたいな感じになる危惧もあります。
博士:
フォロアーの登場は有名店の名前だけ模したカップめんの様に一つの“モデル”としてわかりやすいスタイルが確立してきたと言えるわけですね。 そこでは“驚き”自体もわかりやすい形でパッケージされ、驚きの本質が従来の常識からはみ出す事であった事を忘れてしまいがちになりますね。
先生:
だから、媚びるのではなく、驚かせる。いい意味で裏切る。それが革新です。しかし、あくまでもエクイティの中心にした革新です。もちろん、お遊びで意外なことをやってしまうといのはアリなんですけどね。この辺はセンスの問題です。期待と裏切りのバランスという意味で、プロデューサーの中田ヤスタカ氏の嗅覚はとても鋭いのではないかと考えます。
博士:
現在確認できる数組のフォロアー達はPerfumeの“テクノ”な部分をよく研究してきていますが、今一斬新さに欠けます。あるいは下手するとトランス系に逆戻りししている傾向も見えます。 『BCL』を初めて聴いた時、私自身も“ちょっと雰囲気変えてきたな”と思ってしまったのですが、それはPerfumeがテクノだけではなく、本来“渋谷系”でも有った・・という当たり前な事を失念しかけていた点にあります。
源流を理解した上で再認識すると、メジャーデビュー以降の揺らぎ無い一貫したコンセプトを依然感じます。フォロアーとの差はその部分だと思います。Perfumeは見ても中田ヤスタカを見ていない。 その流れ、方向自体がすでに凡人の理解を超えた“驚き”なのであり、実はなんら作為的でも無いように感じます。
先生:
ブランドたるもの売ろう売ろうと必死になるとかえって逆効果です。所謂、企業の匂いがぷんぷんする必死さです。これは聴き手離れを起こす原因になりかねません。Perfumeは苦節8年と言われながらも、必死さがないのですよね。こだわりをもちつつ、必死にならずにやっていく。これが提言です。