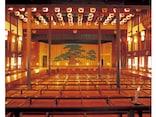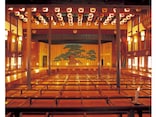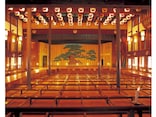3人のセリフがポイント⁉ 勧進帳をより深く楽しむ!

勧進帳は最初のセリフがポイント⁉
さて、『勧進帳』。観れば誰でもたいてい分かる面白いストーリーです。ところどころ「仏教用語か?」と思わせる聞きなれない言葉も出てきますが、観ていくうちにそんなことどうでもよくなるほど(?)良くできた、かつ分かりやすいドラマです。
ですが、富樫と義経と弁慶のこの三人についてはそれぞれ最初の台詞が重要な(他の台詞が重要でないわけではないですが)ポイントを含んでいます。それぞれの置かれた立場、現状、これからどうするかということがコンパクトに説明されているからです。
というわけで、観劇の際、より深く楽しむためのちょっとしたポイントとして、実際に冒頭の部分の三人の台詞を追ってみたいと思います。
富樫・義経・弁慶の登場
最初に登場するのは下手より富樫左衛門と軍兵三人。富樫と軍兵たちのやりとりあって、花道を源義経、四天王と呼ばれる一行と武蔵坊弁慶。ここでメインの゛御三方”が揃います。
富樫 いかにものどもあるか。
軍兵 御前に候。
(この二行は言われないケースが多い)
富樫 かように申すものは、加賀の国の住人富樫の左衛門にて候。さても、頼朝義経御仲不和となりたもうにより、判官殿主従、作り山伏となり、陸奥へ下向のよし、鎌倉殿きこし召し及ばれ、国々に新関を立てて、山伏をかたく詮議せよとの厳命によって、それがし、この関を相守る。方々、さよう心得てよかろう。
富樫は頼朝から命を受けて作られたばかりの安宅の関を護る加賀の国の役人です。とにかく山伏を見付けたら必ず厳しくチェックせよ、と頼朝に命じられているようです。さらにその命を軍兵にも命じます。当然ですが、富樫個人の必要に迫られて山伏を詮議するわけではなく、あくまでも彼の任務であり、責務であり、仕事です。これが強調されています。
三人の軍兵が「仰せの如く」と答え、富樫の命を受けます。
「旅の衣はすずかけの」……長唄が始まる
「旅の衣はすずかけの」と長唄が始まり、花道を、義経、そして常陸坊海尊、伊勢三郎、亀井六郎、駿河次郎の四天王、そして弁慶が登場します。義経 いかに弁慶、道々も申すごとく、かく行く先々に関所あっては、所詮陸奥までは思いもよらず。名もなき者の手にかからんよりはと、覚悟はとくに極めたり。さりながら、各々の心もだし難く、弁慶が詞にしたがい、強力(ごうりき)とは姿を替えたり。面々計らう旨ありや。
もちろん平家を壇ノ浦で陥落させた義経なのですが、もうこの時点ではかなり憔悴しているように感じられるんですがいかがでしょう。頼朝から追われ、死ぬ覚悟だけはきめている。だけど四天王や弁慶が「もっと頑張れ」とはげますものだから、弁慶のアイデアにしたがって強力となっている、(四天王に対して)君らはなにか考えがあるか、というわけです。
四天王のうち三人が、あくまで関所を武力で破ろうと、太刀に手をやり立ちあがろうとするのを年配の常陸坊と、弁慶が押しとどめ、
弁慶 やあれ暫く、御待ち候へ。先程も申すごとく、これは由々しき御大事にて候。この関一つ踏み破って越したりとも、行く先々の新関に、かかる沙汰のある時は、事を求めて破るの道理。たやすくは陸奥へは参りがたし。それゆえにこそ、兜巾(ときん)、すずかけを退けられ、笈を御肩にまいらせ、君を強力に仕立て候。とにもかくにも、それがしに御任せあって、御いたわしくは候へども、御笠を深ぶかと召され、何様にもくたびれたる御体にて、我々より後に引き下がって、御通り候わば、なかなか人は思いもより申すまじ。はるか後より御出であろうずるにて候。
自分たちは山伏姿で、義経はその荷物持ちに等しい強力に化けて、山伏達の行く修験道のルートで、過去義経と縁の深い奥州藤原氏の本拠地・陸奥まで逃げ延びることを提案します。義経は気弱になってるし、四天王はひたすら策もないのに血気盛んです。でも富樫一行は山伏であれば無差別に殺してもいいというお墨付きを鎌倉から得ているふしがある。そのことを弁慶は直接は知らないが、山伏の姿というだけで無事関所が越えられると思うほど甘くないと考えている。だからよもやと思う逆転の発想で、義経を強力姿に扮装させています。
でもふと義経を見ると、哀れな強力姿があまりにもいたいたしい。こんな姿をさせて申し訳ない。と義経に気をつかいながらも励ましているようです。義経は全精力を込めて破った平家なのに、兄に認められず追われる身となっている。不条理な、そして自己否定にも近い思いに傷心の体。とても源平戦のときのような圧倒的な指導力を失っています。弁慶は、自身がこの集団を引っ張っていかなければならないという責務をひしひしと受けとめていると思われます。
義経 ともかくも弁慶よきに計らい候へ。各々違背すべからず。
四人 かしこまってござりまする。
弁慶 しからば、皆々御通り候へ。
四人 心得てござる。
(『勧進帳』歌舞伎オン・ステージ10 白水社より。現在、実際に演じられる台詞とは若干異なる場合も多い)
「皆、弁慶にしたがえよ」と、自分にも言い聞かせるように義経は血気にはやる伊勢、亀井、駿河の三人を諌めます。
最初に花道を登場してきた軽やかな若者・義経は、ここでリーダーの座を弁慶に明渡すことを象徴するかのように、花道で弁慶は義経と四天王の横を通りすぎ、先頭に立ち、富樫の待つ関所へと向かいます。
この後、富樫と弁慶の丁丁発止の問答が始まり、いよいよ”本編”の始まり始まり。官能的とも言われる長唄の名曲をバックに、一種サスペンスフルなドラマが始まるわけです。
非常に無駄のない、そして華やかに構成されたこの最初の場面に、弁慶と義経、そして富樫の運命が凝縮されています。


参考文献・
『歌舞伎事典』平凡社
『歌舞伎オン・ステージ 勧進帳』白水社
『歌舞伎手帳』渡辺保 駸々堂 他
【関連記事】