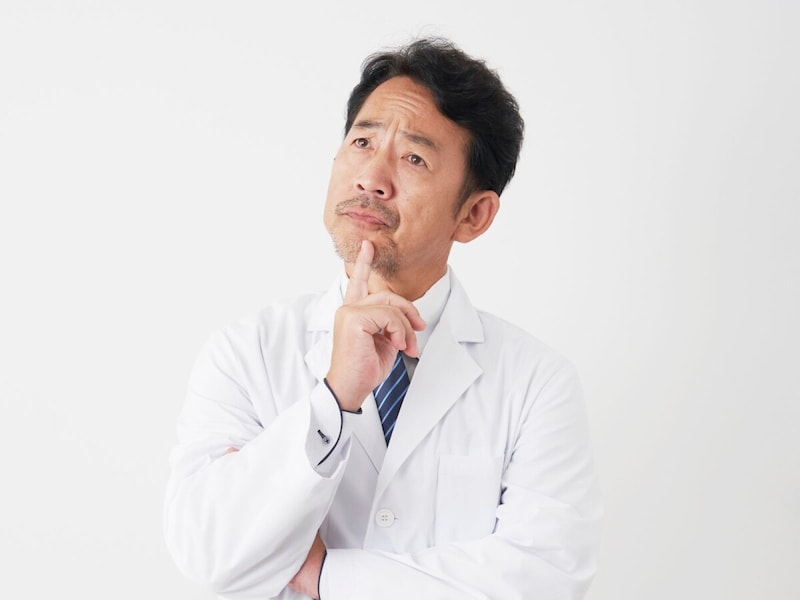
医師の敬称として使われる「御侍史」。本来の意味と、現代の医療現場での意外なメリットとは?
病院を受診した際、他院での精密検査を勧められることがあります。その際に渡される紹介状の宛名に、「〇〇先生 御侍史」と記されている場合があります。病院の先生への敬称だろうと察せられるものの、正確な意味までは知っている人は少ないのではないでしょうか? 「御侍史」の由来と現代での使われ方を、分かりやすく解説します。
「御侍史」の読み方は「おんじし」……「侍史」が持つ本来の意味
「御侍史」は「おんじし」と読みます。「侍史(じし)」とは、古い貴族社会において、貴人のそばに仕え、文書の作成や管理、伝達などを担った役職の人のことです。現代でいえば秘書にあたります。当時は、身分の高い人物に直接手紙や書類を渡すのは無礼と考えられており、必ず「侍史」を介するのが礼儀とされていました。この風習を受け、現代でも医療業界では、医師の名前の下に「御侍史」と添える(※いわゆる「脇付」の一種)ことがあります。
意味合いとしては、「先生はいつもお忙しいでしょうし、直接手紙をお渡しするのは恐れ多いので、侍史(秘書)を通じてお届けします」という気持ちを込めた表現と言えるでしょう。
現代において「御侍史」は過剰? 敬称への違和感と敬意の境界
しかし、現代の状況に当てはめると、やや不自然な表現であることも確かです。筆者自身は医師ではありませんが、医療関係者からのメールで、自分の名前の後に「御侍史」と添えられていることがあります。私には秘書はおらず、直接受け取っているにもかかわらず、「なぜ御侍史(秘書)に?」という疑問が湧きます。
また、「侍史」は身分の高い人に仕えられるほど信頼される特別な役職ですので、それだけでも十分に高い敬意がこもっている言葉です。この言葉にさらに「御」を加えることで、現代においては過剰な敬称に見える場合もあります。場合によっては、本来の受取人である医師よりも、その秘書を強く尊敬しているような表現とも受け取れます。
ただの敬称ではなく実務面でのメリットも? 「御侍史」を添える意外な効果
それでは、上記のような背景を考慮し、「御」を外した場合はどうでしょうか? 「〇〇先生 侍史」と書くと、これもまた不自然で、相手に違和感を与えてしまいそうです。結果として、現代社会においては不自然な点もあることは理解されつつ、「御侍史」という表現が使われることになります。本来の意味からは離れ、受取人に対する敬意を表すために慣用化した、敬称の形と理解するのがよさそうです。
また、実務面での意外なメリットもあります。「御侍史」と添えられた文書は、宛名の医師以外の秘書や医療事務の職員も、開封することができます。逆に、「御侍史」と添えられていない場合、宛名の医師以外が勝手に開封することは許されません。
紹介状や医療文書を円滑に扱い、病院内の業務をスムーズに進めることに役立つ工夫、という面もあるのです。







