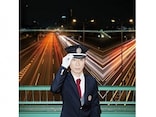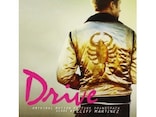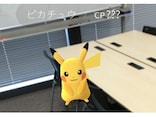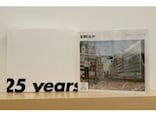海外での反応
――稲見さんは海外ツアーをかなりされていると思いますが、観客層や彼らの反応とかは日本とは違いましたか? ヨーロッパ各地、アメリカ西海岸等に何度か行きましたが、いつも思うのは、お客さんがまじめに聴いてくれるんですよね。僕は今、即興で抽象的な音楽をやっていますが、演奏をして日本と大きく違うと感じるのは、音楽を芸術としてとらえるレベルが日本とは全然違うというか、細かいところにこだわらず、直接的に表現、作品として受け取って評価してもらえるので、とてもやりやすいし、意志も伝わりやすいですね。客層とかもあんまり関係ないですし。芸術の分野だとやはり作品を通してそのアーチストの人間性に興味を持ってもらえるのが一番だと思いますし、僕はそれが目的のひとつだと思います。日本だと、ジャンルとか手法とか、それこそつまらないメディア操作とかが音楽を聴く前の先入観として大きく位置しているのが残念に思います。自分は別にアーチストだから、とお高くとまる気はないんですけど、国内でもシーンがもっと自然に、普通になればと思います。
ヨーロッパ各地、アメリカ西海岸等に何度か行きましたが、いつも思うのは、お客さんがまじめに聴いてくれるんですよね。僕は今、即興で抽象的な音楽をやっていますが、演奏をして日本と大きく違うと感じるのは、音楽を芸術としてとらえるレベルが日本とは全然違うというか、細かいところにこだわらず、直接的に表現、作品として受け取って評価してもらえるので、とてもやりやすいし、意志も伝わりやすいですね。客層とかもあんまり関係ないですし。芸術の分野だとやはり作品を通してそのアーチストの人間性に興味を持ってもらえるのが一番だと思いますし、僕はそれが目的のひとつだと思います。日本だと、ジャンルとか手法とか、それこそつまらないメディア操作とかが音楽を聴く前の先入観として大きく位置しているのが残念に思います。自分は別にアーチストだから、とお高くとまる気はないんですけど、国内でもシーンがもっと自然に、普通になればと思います。でもそう思う反面、じつはあきらめている部分もあって、日本では日本人はメロディーや日本語の歌詞を最初に聴いたり覚えたりする風潮があるし、また、古くから日々の生活の中に音楽が根付いているわけではないので、自分のような音楽の場合は、なかなか難しいと思っています。まぁ、商業的になるのであればいろいろやりクチはあるように思いますが、自分は畑違いです。(ちょっとしゃべりすぎでしょうか..)
 あと、特にヨーロッパだと、同じ方向性のアーチストたちが場所(建物やフロア)を共有、運営して、そこで自分たちのやりたい、または聴きたい内容に特化したイベントを行っているところが多く、そこから横のつながりや、小さいけどシーンが生まれたりしてるんですよ。C.U.E.を立ち上げたのはそれに共感してということもあるんです。C.U.E.も4年ほどやってきた中で、その筋(?)では認知されてきて、海外からのアーチストもよく出演してくれるようになってきました。小さいことなんですけど、音楽を通して知らないものどおしがお互いに認め合って少しずつコネクションが広がっていくというのは嬉しいし、やりがいもあります。
あと、特にヨーロッパだと、同じ方向性のアーチストたちが場所(建物やフロア)を共有、運営して、そこで自分たちのやりたい、または聴きたい内容に特化したイベントを行っているところが多く、そこから横のつながりや、小さいけどシーンが生まれたりしてるんですよ。C.U.E.を立ち上げたのはそれに共感してということもあるんです。C.U.E.も4年ほどやってきた中で、その筋(?)では認知されてきて、海外からのアーチストもよく出演してくれるようになってきました。小さいことなんですけど、音楽を通して知らないものどおしがお互いに認め合って少しずつコネクションが広がっていくというのは嬉しいし、やりがいもあります。