相続・相続税 人気記事ランキング(3ページ目)
2026年01月04日 相続・相続税内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
21位相続税とは
相続税とはどんな税金なのでしょうか?相続が発生するとどんなことが起きるのでしょうか?初めて相続と直面した時にお役に立つお話です。
 相続・相続税の基礎知識ガイド記事天野 隆
相続・相続税の基礎知識ガイド記事天野 隆22位跡を継いでもらいたいのだが 名字と相続の関係
娘さんに跡を継いでもらいたいときの方法は3つあります。「同居」と「姓が変わること」と「相続」とは異なります。同居して名前は変わっても、相続権がある場合と、無い場合があります。
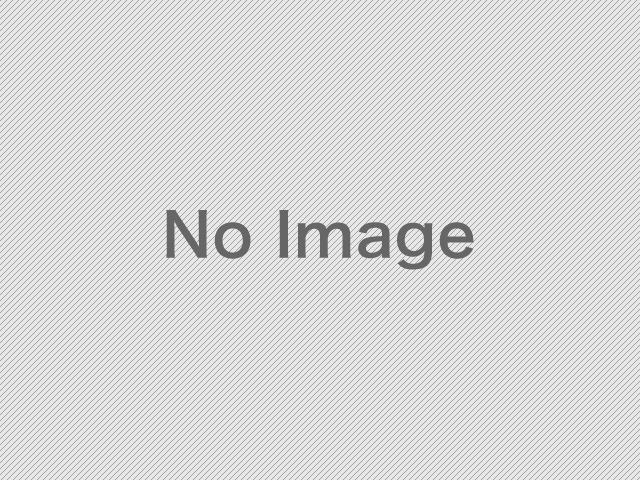 相続・相続税関連情報ガイド記事天野 隆
相続・相続税関連情報ガイド記事天野 隆23位相続税がかかる財産
相続税について最初にやることは、相続税がかかる財産を把握することです。相続税の対象となる財産は、本来の相続財産、生前の贈与財産、みなし相続財産の3つです。それぞれ個別に確認していきましょう。
 相続税の計算方法ガイド記事清水 真一郎
相続税の計算方法ガイド記事清水 真一郎24位相続放棄の期限と手続き
相続が発生し、被相続人(亡くなった人)の財産が債務超過の場合には、相続人は、債務を承継しない相続放棄の手続をします。相続放棄の期限や申請先、必要書類など……相続手続きについてまとめました。
 相続の手続きガイド記事加藤 昌男
相続の手続きガイド記事加藤 昌男25位相続税対策の不動産はタワーマンションが有利?
不動産による相続税対策の中でも、タワーマンションの購入は節税効果が高く、人気を集めています。ただ、今後は国税庁の監視強化により、従来のようにはうまくいかなくなる可能性もあります。そもそもの節税の仕組みと、注意すべき点とは。
 相続税対策ガイド記事
相続税対策ガイド記事26位先立ったのが夫か妻で変わる遺産分割・二次相続対策
遺産分割や相続対策は、一次相続が夫が先だったか妻が先だったかで変わってきます。将来を見据え、それぞれのケースにおける遺産分割や相続対策の考え方をご紹介します。
 相続の事例・トラブルと対処法ガイド記事
相続の事例・トラブルと対処法ガイド記事