耳・鼻・喉の病気 人気記事ランキング
2026年02月21日 耳・鼻・喉の病気内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
1位耳に水が入ったときの治し方・水抜き…ガサガサ音が取れない時の注意点
【耳鼻科医が解説】耳に水が入って取れない場合、水ならば無理に水抜きなどをせずに放置して大丈夫です。通常は数時間で自然に乾きます。もし耳に水が入った感じやガサガサ音が続く場合は、耳垢の溜まりすぎや耳管機能の異常などの可能性があるので、耳鼻科を受診しましょう。耳に水が入って抜けない場合の症状、水の抜き方、注意点などを解説します。
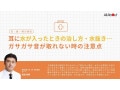 ガイド記事
ガイド記事2位Q. 耳掃除はなぜ気持ちいいのでしょうか?
【耳鼻科医が解説】「耳掃除をしてはいけない」と言われても、耳掃除が気持ちよくてやめられないという人もいるようです。なぜ耳掃除は気持ちいいのか、わかりやすく解説します。
 ガイド記事
ガイド記事3位耳管開放症に効く食べ物・サプリはある?日常生活でできる対処法
【耳鼻科医が解説】耳管開放症に効く食べ物や飲み物、サプリなどが知りたくて、調べている方はいませんか? 症状を緩和・治療する自分でできる対処法としては、いくつかのポイントがあります。耳管開放症改善のために日常生活でできることを解説します。
 ガイド記事
ガイド記事4位鼻水が止まらない…スッキリ止める方法は?
風邪や花粉症にかかると止まらなくなる鼻水。何回鼻をかんでもスッキリせず、困る人も多いと思います。鼻水はいったいどこから来るのでしょう? 鼻水を止める方法は? 効果的な鼻水の止め方、薬の副作用についてもご紹介します。
 鼻水・鼻づまりガイド記事
鼻水・鼻づまりガイド記事5位正しい鼻血の止め方・ティッシュではなく圧迫止血で
医師として正しい鼻血の止血法の基本は、小鼻をつまんで行う圧迫止血です。鼻にティッシュを詰める止血法をする人が多いようですが、オススメできません。また、救急車を呼ぶべきケースもありっます。鼻血が止まらない場合の病院受診の目安や、子供の鼻血の原因、白血病など病気と鼻血との関係について解説します。
 鼻血ガイド記事
鼻血ガイド記事6位メニエール病症状改善に日常生活でできること・再発予防法
【耳鼻科医が解説】メニエール病の症状改善、再発防止に効果的なことは? カフェインや飲酒・喫煙を控える、睡眠を十分にとる、ストレス・頭痛などをコントロールも有効です。いわゆる「メニエール病に良い食べ物」などを試してもよいですが、過度な健康食品依存には注意が必要です。病院での治療以外でできる日常生活の工夫のポイントを解説します。
 ガイド記事
ガイド記事7位低音難聴を治す生活習慣改善ポイント…タバコは禁煙、飲酒は控えめに
【耳鼻科医が解説】低音難聴の症状を早く治すために、リンパマッサージや岩盤浴、整体などを試す方もいるようですが、治療と並行して、まずは生活習慣を改善していくことが大切です。十分な睡眠、ストレス解消、カフェインやタバコ、アルコールの注意点など、見直しのポイントを解説します。
 ガイド記事
ガイド記事8位Q. 耳掃除を全くしないとどうなりますか?
【耳鼻科医が解説】「耳掃除をしてはいけない」と言われても、耳垢を放置するのも心配です。耳の中がかゆくなったり、聴こえが悪くなったりすることはないのでしょうか? 「耳掃除はしなくてよい」というのは嘘なのか、耳掃除をしない場合のリスクや注意点などを解説します。
 ガイド記事
ガイド記事9位夏フェス前に必読! 音響外傷の症状・後遺症・治療法
夏の音楽フェスティバル(夏フェス)、コンサート。注意したいのが音響外傷です。終演後に難聴に気づいて翌日には治っている事が多いですが、耳鳴りは治っても聴力が回復せず後遺症が残ることがあります。翌日に耳の違和感を感じた場合は直ぐに受診しましょう。
 突発性難聴ガイド記事
突発性難聴ガイド記事10位正しい鼻水の止め方は? 市販薬の選び方と注意点
どうしても鼻水を止めたいけれど、病院を受診して処方箋をもらって服薬する時間がない時もあるでしょう。そんなときは市販薬でもある程度は有効。ただし副作用には注意が必要です。
 鼻水・鼻づまりガイド記事
鼻水・鼻づまりガイド記事