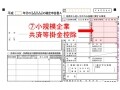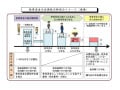税金ガイド税理士田中 卓也
たなか たくや税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。
ガイド記事一覧
パート・アルバイトでも年末調整は対象?掛け持ちの場合は?
勤務先から給料・賞与をもらっている人は、正社員・非正規雇用・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、勤務先で年末調整をしてもらうことで所得税の精算が完了します。では「複数のバイトを掛け持ち」「年末に在職していない」といった特殊なケースではどうなるでしょう?
掲載日:2019年10月08日年末調整iDeCo(イデコ)の年末調整・確定申告の書き方・記載例
2017年1月より加入対象者が大幅に拡大した個人型確定拠出年金iDeCo・イデコ。積立するとき、運用するとき、受け取るときの3段階で税制優遇が受けられます。積立するときに税制優遇が受けられるということは、もちろん、年末調整や確定申告すると税金が戻ってきます。
掲載日:2019年10月08日年末調整年末調整のメリット・必要性とは…何のため?誰のため?
年末調整の必要性がある人は、そのメリットを理解し、仕組みや手続きを知っておきましょう。「年末調整の書類なんてよくわからないし、面倒くさいから言われたことだけサッサと書いて提出してるよ」という人は、納めなくてもいい税金を納めていて損している可能性大です。
掲載日:2019年10月04日年末調整住宅ローンを借り換えした場合の年末調整ポイント!
住宅ローンを返済する際、借り換えや繰上返済などを行うこともあるでしょう。借り換えを行った場合、住宅ローン控除が適用される場合は、年末調整で対応することになります。住宅ローン控除が全額適用されない場合についても解説します。
掲載日:2019年10月01日確定申告固定資産税・都市計画税の計算方法と計算例
固定資産税・都市計画税は、賦課課税制度といって地方自治体が税額を計算しますが、誤った固定資産課税が行われていても、その誤りに気付かなければ、そのまま放置されることに注意しましょう。固定資産税・都市計画税の計算方法と計算例付きで解説します。
掲載日:2019年08月27日税金2019年10月、消費税が10%に上がるときの注意点!
消費税率はいつから上がるのかというと、8%から10%になるのは平成31年10月1日(2019年10月1日)が予定されています。消費者の立場からみれば、本体価格10万円のものを購入する場合、10万8000円だったものが11万円に値上がりするだけと考えがちですが、8%のままでもOKとされる取引形態や品目があるのです。どういったものが軽減税率の対象になるのでしょうか?
掲載日:2019年08月02日税金年収がバレる?意外と大変な2023年からの「日本型インボイス」導入
消費税に複数税率が導入されたあと、「適格請求書発行事業者登録制度」なるものの運用が開始され、免税事業者にとっては消費税が請求しにくくなり、おおまかに年商がバレてしまう時代がくるかもしれません。なぜ、そのようなことになるのかみていきましょう。
掲載日:2019年07月26日税金消費税8%と10%、複数の税率導入で請求書やレシートはどう変わる?
「どれが消費税率10%で、どれが消費税率8%なのか」。消費税率が複数になると、それがレシートや請求書で判別できるものでなくてはなりません。では、どのような様式ならOKで、どのような様式ならNGなのでしょうか。記載例で検証してみました。
掲載日:2019年07月18日税金教育資金贈与と結婚資金贈与が2年間の延長に
「60歳以上では2000万円を超える貯蓄高がある」とされる総務省のデータがあります。こういったことに着目して合計で2500万円もの贈与が無税で行うことができる制度があります。そのようなものが教育資金や結婚資金で活用できれば現役世代も助かりますよね。
掲載日:2019年07月09日税金消費税10%と8%区分、イートインとテイクアウトの違いって?
2019年10月、いよいよ消費税が10%にアップ予定です。ただ、食品と外食の区分をめぐってコンビニのイートイン、ファストフードのドライブスル―、カラオケボックスや映画館での飲食の提供など判断に迷うものも少なくありません。どのサービスが8%のままなのでしょうか?
掲載日:2019年07月08日税金
その道のプロ・専門家約900人
起用ガイドが決まっていない方はこちら