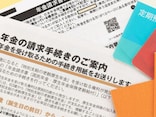振替加算は加給年金の支給停止後にもらえる給付金
加給年金や振替加算というのは、夫婦であることが条件でもらえる老齢年金の上乗せ給付金です。加給年金は、老齢厚生年金の受給者(夫)が65歳になったとき、年下の妻や18歳未満の子どもがいる場合、年下の妻が65歳になるまで、夫の老齢厚生年金に加算される家族手当金です。
このように夫が加給年金をもらうには、妻は年下である必要があります。
年下の妻が65歳になると、夫の老齢厚生年金に上乗せされていた加給年金は支給停止となります。年下の妻が65歳になり、老齢基礎年金をもらうようになった場合、今まで加給年金として加算されていた金額の一部が妻の年金に上乗せとなります。この上乗せ部分を振替加算といいます。
●加給年金と振替加算の切り替わり図 上述のたとえでは、夫が年上で、妻の生計を維持しているという仮定で紹介していますが、男女逆でも加給年金、振替加算は適用になります。
・出典:加給年金額と振替加算|日本年金機構
振替加算をもらうには、次に紹介する要件が必要になります。
●振替加算をもらうための主な要件
①加給年金の支給対象となっている配偶者である
加給年金が支給されるのは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方で、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)に、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときです。
振替加算は加給年金の支給停止後に配偶者に対して支給されます。そのため、振替加算を受け取る配偶者は、加給年金の支給対象となっている必要があります。
②大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
振替加算を受け取る配偶者は、1926年(大正15年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日生まれの方が該当します。
③配偶者の厚生年金保険および共済組合等の加入期間が合わせて240カ月未満であること
振替加算は、配偶者の老齢基礎年金に加算されます。その際、配偶者が老齢基礎年金の上乗せで老齢厚生年金などを受給する場合は、厚生年金保険および共済組合等の合計した加入期間が20年(240カ月)未満である必要があります。
●年上の妻は振替加算の申請もれに注意
加給年金は、夫よりも妻が年下であれば、夫がもらう老齢厚生年金に上乗せされます。一方、振替加算は、妻と夫の年齢差は関係なく、妻の老齢基礎年金に加算される給付金です。年上の妻であっても要件に該当すれば、振替加算をもらえます。
しかし、振替加算がつくタイミングは、夫が65歳になった時点。年上の妻であれば、既に老齢基礎年金をもらって、数年経過しているはずです。年上の妻が振替加算をもらうには、自身で手続きする必要がありますが、手続きすることを忘れていたり、そもそも振替加算を知らなかったりすれば、申請もれとなるケースもあります。
そうならないためにも、妻が夫よりも年上の夫婦は、夫が65歳になった時点で、お互いの年金について確認し合うようにしましょう。
年上の妻が振替加算をもらう場合は手続きが必要
年上の妻が振替加算をもらうには、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」と一緒に、次に紹介する書類をそろえ、年金事務所に提出しましょう。●振替加算の申請に必要な添付書類
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票※1
・妻の所得証明書※1
※1:マイナンバー(個人番号)を申請書に記載した場合、年金事務所が「世帯全員の住民票」「妻の所得証明書」「戸籍謄本」の情報を行政機関のデータベースから自動で取得・確認します。そのため、これらの書類を添付する必要はありません。
ただし、本人や加給年金額の対象者のマイナンバーを記載していても、内容に不備がある場合や照会できなかった場合などには、戸籍謄本などの原本提出を求められることがあります。
振替加算の金額
振替加算で上乗せされる金額は、妻の生年月日ごとに決まっています。振替加算は、昭和41年4月2日以降に生まれた妻はもらえないため注意しましょう。●振替加算額 妻の老齢基礎年金に上乗せされる振替加算は、夫が65歳になった時点から、基本的に一生涯受け取れます。