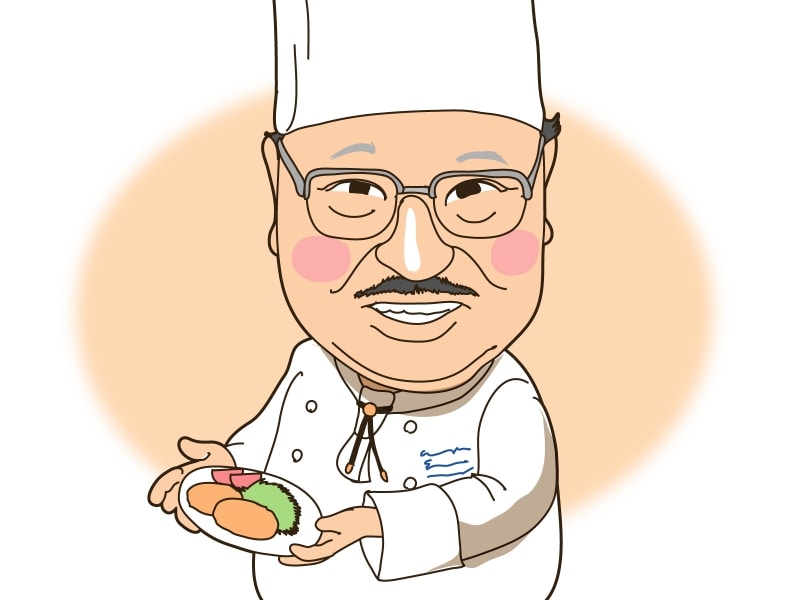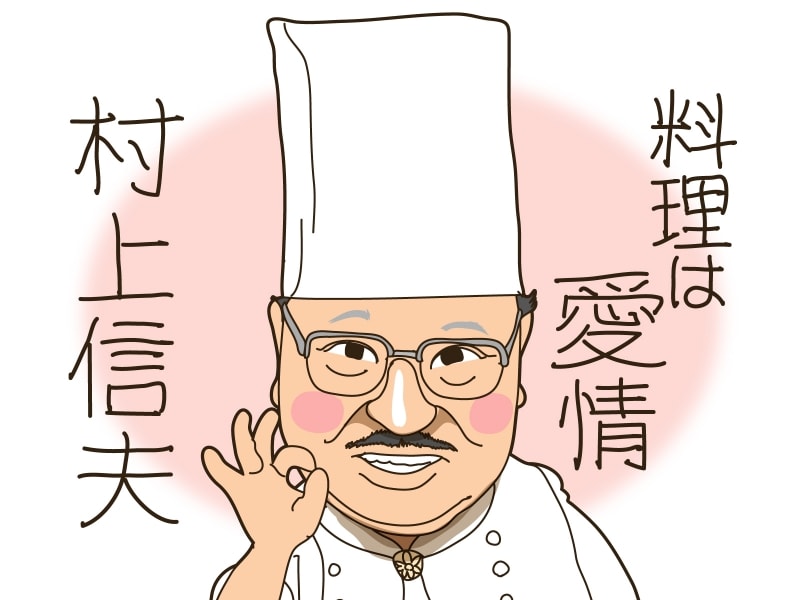日本の料理界を改革・創造し続けた「村上信夫」
「偉人」とは、コトバンクのデジタル大辞泉によれば「すぐれた仕事をなしとげ、多くの人から尊敬される人。偉大な人」と定義されています。「グルメの偉人」について思いを巡らせた時、優れた仕事を成し遂げたということであれば、たくさんの方を思い浮かべられます。しかし、それに加えて、多くの人から尊敬されるということも考慮するのであれば、私は真っ先にこの方のことを思い浮かべます。
それは、帝国ホテルで第11代料理長および初代総料理長を務め、「ムッシュ村上」と尊敬の念を込めて呼ばれた村上信夫氏(1921-2005)です。
村上氏は1921年東京・千代田区に生まれ、1933年浅草ブラジルコーヒーに入店。その後、銀座つばめグリル、新橋第一ホテル、糖業会館レストラン・リッツなどで働き、1939年帝国ホテルの見習いとなる。1964年の東京五輪では選手村「富士食堂」の料理長を務め上げ、1969年にヨーロッパに2度目の研修へ赴き、帰国して第11代料理長に就任。さらには1970年11月に取締役総料理長となり、以降1996年6月まで、帝国ホテルの総料理長という重責を担いながらもフランス料理を極めました。
大きな功績を評価されての受賞歴も数多く、その中でも特に、1987年にフランス料理界で最も権威がある「メートル・キュイジニエ・ド・フランス」を受賞、2000年には「フランス農事功労章」を受賞したという、輝かしい経歴を持つ料理人なのです。
もちろん、これらの素晴らしい経歴だけで「グルメの偉人」だというわけではありません。村上氏の日本の食文化への影響の大きさは計り知れず、それらは以下のような実績からも裏付けされており、それゆえに「グルメの偉人」であると考えるのです。
- 料理界の仕組みを改革
- 新しい料理の味やスタイルを創造
- 料理人のイメージを向上
料理界の仕組みを改革「400もの秘蔵レシピを体系化」
料理は技術の世界、腕一本の世界です。自身の料理の腕やアイデアによって昇り詰めていくことができ、いずれは独立して自分の店を持つこともできます。その厳しい競争に打ち勝つため、日々真面目に鍛錬していく料理人は多いのですが、ときに限度が過ぎてしまうこともありました。たとえば昔の料理界では、自分の味を守ることに固執して、後輩に料理を積極的に指導することはありませんでした。レシピもろくに残さず、配合や使う食材などは秘密にして、他の人に知られないようにしていたのです。しかし、これではせっかくの技術が属人化してしまうので、ホテルなどの組織ではよいことではありません。
1958年に新館料理長に就任した村上氏は、この構造的な問題を改革しました。それまでは帝国ホテルに共有されたレシピはありませんでしたが、村上氏がそれぞれの帝国ホテルの料理人たちが持っていた400もの秘蔵レシピを集め、整理し、体系化したのです。
「情報は独占するものではなく、共有するもの」ーー。
これまでの料理人の常識を変えたのは大きなことでした。この考え方を浸透させていった結果、第13代料理長となった帝国ホテル専務執行役員・現総料理長の田中健一郎氏が入社した1969年には「盗んで覚える」という因習はなくなっており、むしろ、先輩から様々なことを教えられるので「もっと早く料理を覚えなければならない」という雰囲気になっていたというのです。ちなみに田中氏は2015年11月9日、厚生労働省から、日本のものづくりを支え、優れた技能を持つ職人150人のうちの1人として、「現代の名工」に選出された料理人です。
帝国ホテルがこういった優れた料理人を輩出し、料理の味を高いレベルで維持・安定できているのも、レシピの共有化や料理人の考え方の効率化を図り、帝国ホテル全体で味の向上を目指した村上氏の改革が大きく寄与しているのだと私は考えます。
また村上氏は1975年頃に、料理長が全てのメニューを書くという伝統を改め、各レストランのシェフに裁量を与えて、メニューを自由に決められるようにもしました。全てがトップダウンであった時代と比べれば、現場は自由度があるのでやる気が持てますし、新しい料理を考えるのでトレンドにも敏感になるでしょう。
こういった先見性のある思い切った施策のおかげで、帝国ホテルでは各レストランが独自に試行錯誤するようになり、「敷居が高い伝統的なホテル」というイメージがありながらも、いつも新しい料理を食べられるホテルとなったのです。
そして、日本におけるフランス料理の第一人者である村上氏が率先して行った改革だからこそ、この取り組みやシステムが他のホテルやレストランでも取り入れられ、料理界のみならず、利用する客側にも大きなメリットをもたらすことになったのです。
新しい料理の味やスタイルを創造「バイキングを初めて導入」「肉と魚を一皿で」
帝国ホテル発祥の料理といえば、1934年に帝国ホテル「ニューグリル」料理長の筒井福夫氏が考案した日本独特のステーキ「シャリアピンステーキ」が特に有名でしょう。来日したオペラ歌手フョードル・シャリアピンは歯痛に苦しんでおり、柔らかいステーキを食べたいという要望を持っていました。そこで筒井氏が、肉をよく叩いてからタマネギでマリネすることによって、柔らかいステーキを創り出したのです。こういった新しい料理を創り出す帝国ホテルの遺伝子は、村上氏にもしっかりと受け継がれています。村上氏は1957年にパリのホテル・リッツで修行し、その時にオーギュスト・エスコフィエの直弟子であるアンリ・ル・ジュールから薫陶を受けました。エスコフィエは、1903年に刊行され、今もなおフランス料理のバイブルとして輝く『ル・ギッド・キュリネール』の著者であり、フランス料理にコースメニューを導入した偉大な料理人です。村上氏は、オーギュスト・エスコフィエからアンリ・ル・ジュールへと続くフランス料理の真髄を学び、その伝統と技法に重きを置きながらも、それだけにとどまることはありませんでした。
ホテル・リッツから帰国した1958年8月には、1番シェフを経験していないのに37歳という若さで帝国ホテルの新館料理長に大抜擢されました。通常は、宴会、アラカルト、グリルなどの1番シェフを経てから料理長に就任するものなので、異例の出世であることが分かると思います。ちなみに、ホテルにおける料理人の体制は上から順番に、総料理長、棟や料理毎の料理長、それから宴会やレストランの料理長、さらにはそれぞれのセクションの中で1番手、2番手というように組織化されているのが一般的です。
前述の新館がオープンすると同時に、村上氏は北欧で研究してきたスモーガスボードの料理や形式を楽しめる「インペリアルバイキング」(現在は「インペリアルバイキング サール」)オープンの立役者となりました。今では「バイキング」という言葉が当然のように使われていますが、これは和製英語であり、「インペリアルバイキング」が日本におけるバイキングの発祥だったのです。
当時は今に比べると冷蔵技術が発達していなかったので大量の氷で前菜を冷やしたりと苦労もありましたが、たくさんのホテルの一流料理を好きなだけ楽しめるということで大反響がありました。長嶋茂雄氏や力道山といった有名人も訪れたほどです。
(帝国ホテルから辿るバイキングの歴史や帝国ホテル「インペリアルバイキング サール」でも詳しくご紹介しています)
また、パンやサラダ、デザートを、アラカルトで提供されているメイン料理に加えてセットにできる定食方式も導入し、自由度を高めて客がより利用し易いように改善しました。当時では「街の食堂のようだ」と他の料理人から猛反発がありましたが、客には好評で成功を収めることができました。
他にも、パリで流行していた、陸(肉料理)と海(魚料理)を一皿で提供する「コスモポリタン」方式も取り入れましたが、これも当初は、性質の異なるものを一皿に合わせるなど、伝統的なフランス料理では受け入れられないと反発を受けました。しかし、牛肉とカキ、鶏肉とエビなど、一皿で肉も魚介も食べられるのは客にとって喜ばしいことでした。そのため、この試みも最終的には支持されたのです。
村上氏の創造はまだ続きます。1975年5月にイギリスのエリザベス女王が来日し、帝国ホテルで行われた日英協会主催の午餐会に参加されました。そこでエリザベス女王の好物が魚介類であることを鑑み、車海老と舌平目のグラタンを考案して提供したのです。すると、エリザベス女王はドーバー海峡の平目に勝るとも劣らないと評し、とても気に入りました。そして、「レーヌ・エリザベス(車海老と舌平目のグラタン エリザベス女王風)」というように、女王の名前を料理名に使うことを承諾したのです。
様々な料理人があらゆる料理を創造してきましたが、エリザベス女王の名前が付けられた料理は他にはまずありません。いかに貴重な料理であるかが分かることでしょう。
料理人のイメージを向上「多忙を極めるなか、NHK『きょうの料理』に出演」
村上氏は料理界の古き伝統を改革し、そして新しいメニューも創り出してきましたが、料理人自身のイメージも向上させました。特に注目したいのは、1960年からNHKテレビ『きょうの料理』へ出演したことです。「誰でもできます」「ベリーグッドです」と優しい言葉をかけながら、調理の行程を一つ一つ丁寧に説明する姿は、多くの方の記憶に残っているのではないでしょうか。これ以外にも、定期的に婦人雑誌へ寄稿し続けたりもしました。どちらも簡単なことのように聞こえますが、実際には大変なことです。なぜならば、帝国ホテルの総料理長というのは約400人の料理人を従える立場であり、その仕事は多忙を極めるからです。
しかし、村上氏は激務の合間を縫って継続的にメディアへ出演し、ホテルの料理やフランス料理を一般家庭にも分かり易く紹介してきました。この結果、日本の家庭における洋食のレベルを底上げしたことはもちろん、料理人のイメージを職人気質で堅苦しいというものから、品があって親しみ易いというものに変えたのです。
普段の振る舞いも、メディアに出演している時と全く同じで、温厚で丁寧でした。同じ帝国ホテル内の若いスタッフにも自ら積極的に挨拶し、敬語で話していたのです。穏やかな人柄ですが、一方では、確固とした信念と行動が垣間見られ、たとえば、1955年に当時社長の犬丸徹三氏から「フランスへ修行に行かないか」と打診された際に「よろしくお願いします」と即答し、「家族に相談しないでいいのか」と驚かれたエピソードがあります。料理の道を極めるという強い信念があったからこそ、一寸の迷いもなく道を定めることができたのでしょう。また、自身が料理人であることに矜持をもち、取締役になって役員会議に出席する際にも常にシェフコートを着用していました。
このように村上氏は、料理人としての実力があっただけではなく、穏やかで礼儀正しく、人間としての魅力を備えていたことで、料理人のイメージをよりよいものにしたのです。
料理は愛情
村上氏は2005年8月2日に心不全のため84歳で逝去しましたが、氏が遺したサインやメニューにはよく「料理は愛情」と記されています。この言葉の真意は、村上氏が前述の田中氏に「今まで食べたものの中で、一番おいしかったものは何ですか」と尋ねて、自身が示す答えとして「それは、お母さんが作る手料理です。なぜかと言えばよい材料がなくても、よい道具がなくても、子供においしいものを食べさせたいという気持ちが詰まっているからです」と述べた言葉によって、全てを説明できるのではないでしょうか。村上氏は「心を込めて作らなければ、絶対においしい料理はできない」という真っ直ぐな想いと「料理にこれでいいということはない。いくつになっても研究を続ける」という強い信念とを併せ持った、類稀なる料理人でした。戦後、シベリアで2年にも及ぶ抑留を経験し、何度となく生死の境を彷徨いながらも日本へ帰国できたのは、単に強運であったのではなく、人間の生命の源である食を支えて、戦後の日本人に活力を与えるために、食の神様から遣わされた「グルメの偉人」だったからなのではないかと私は思うのです。
■イラスト/エイイチ