消費しながら備える

備蓄量を考えて、ふだんから見やすく使いやすく収納
避難生活での食料はレトルト食品や缶詰など、ライフラインが復旧するまでの非常食。その後、状況が落ち着いたらインスタント食品、お菓子などが加わるといったメニューを想定して、備蓄する食品タイプを選びます。その際に、日頃から食べ慣れている食品を選ぶのがポイントです。
そしてふだんから消費する食品として、食べたら補充するというサイクルでキッチンに収納。いざというときには、そこにある食品を非常食として使えるようにします。いつも出し入れしている場所にあれば、慌てずにすむので安心です。
そのためにも、ふだんから種類別に分けて収納しておきましょう。やみくもにたくさん備蓄するのではなく、収納スペースとのバランスを見て、何がどのくらいあればいいのか、ストックを見直すいい機会です。
在庫の管理
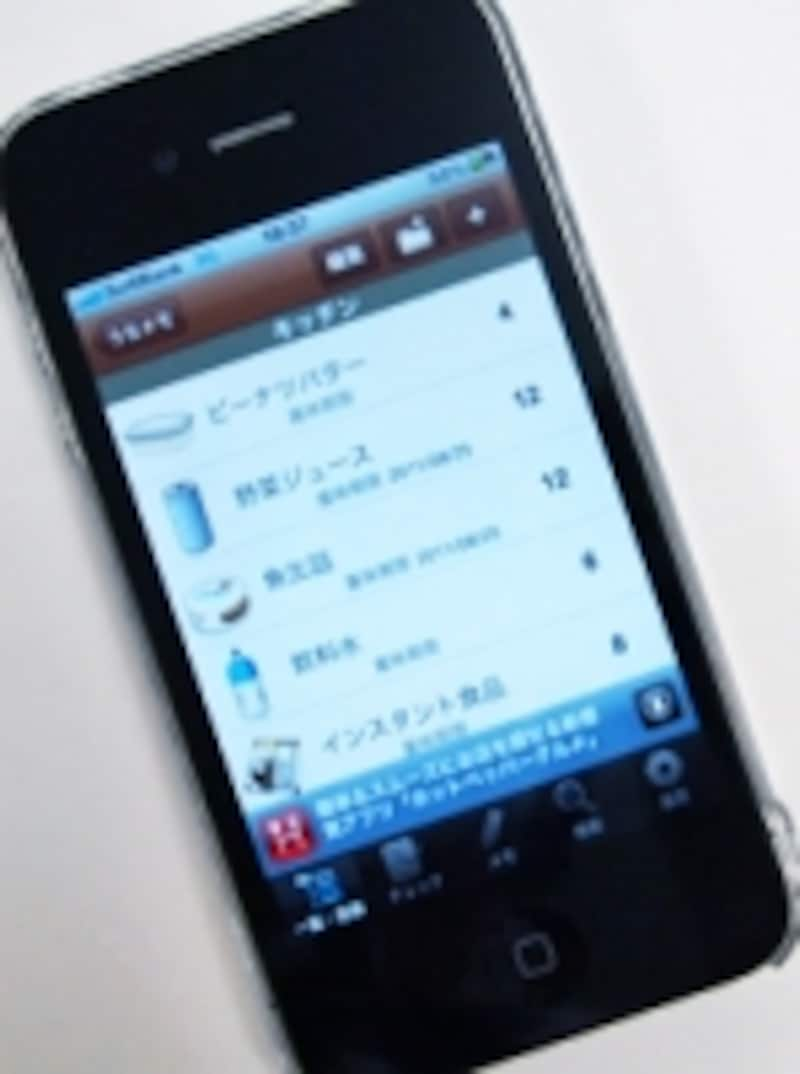
iPhoneのアプリ「うちメモlite」で場所別・食品別で管理できる
たとえば飲料水ならキッチンに1ケース、玄関に2ケース、納戸に2ケースといった具合。備蓄を意識するとケースで買うことになりますが、その際には重量と寸法を調べて、どこにどのくらい保管できるか計画を立てて収納場所を確保しましょう。
備蓄をするモノが多いと厄介なのが、消費期限の管理です。ふだんの生活で消費しながら補充すれば、期限前にいっぺんに食べきらなければならない事態は避けられますが、何がいくつ残っているのかが分かりにくくて、かえって不安になります。災害に備えるうえでも、備蓄食品のリストをつくっておくと気持ちに余裕ができて安心です。







