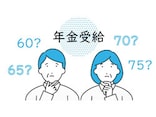遺族年金について

遺族年金の「遺族」はだれ?
遺族基礎年金は、死亡した人の要件と遺族の要件がそれぞれあります。死亡した人は次のいずれかに該当していることが必要です。
- 死亡日において、国民年金の被保険者であること。
- 死亡日において、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること。
- 老齢基礎年金の受給者か受給権を満たしていること
なお、1または2に該当する人は、死亡日の前日において死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと、または保険料の滞納期間が被保険者期間の3分の1未満であることも必要です。
また、遺族基礎年金の「遺族」は、18歳の年度末を迎えていない(一定の障害の状態にある場合は20歳未満)「子どもいる妻」と18歳の年度末を迎えていない(一定の障害の状態にある場合は20歳未満)「子ども」のみです。死亡した人にこの要件を満たす妻がいれば妻に、妻がいなくて子どものみの場合は子どもに遺族基礎年金が支給されます。「夫」は遺族基礎年金の遺族には含まれません。
年金額は、792,100円に子どもの加算額(1人目2人目の子どもには227,900円、3人目以降の子どもには75,900円)を加えた額です。
遺族厚生年金も、死亡した人の要件と遺族の要件がそれぞれあります。死亡した人は次のいずれかに該当していることが必要です。
- 死亡日において、厚生年金の被保険者であること。
- 厚生年金の被保険者であった者が、被保険者に資格を喪失した後、被保険者であった間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡した場合。
- 障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給者であること。
- 老齢厚生年金の受給者か受給権を満たしていること。
遺族厚生年金の「遺族」は遺族基礎年金に比べると範囲が広く、以下の要件に該当する人が遺族となります。
- 遺族基礎年金の支給対象となる子のある「妻」または「子ども」
- 子のいない妻
- 55歳以上の夫
- 55歳以上の父母
- 18歳の年度末を迎えていない(一定の障害の状態にある場合は20歳未満)孫
- 55歳以上の祖父母
数字は優先順位を表し、この遺族のうち最も優先順位の高い遺族が年金の受給者となります。なお。夫・父母・祖父母が遺族となった場合は、年金の支給が60歳からとなります。また、子のいない妻が遺族となり、夫の死亡の当時30歳未満だと年金の支給期間が5年間となります。
遺族厚生年金の年金額は、障害厚生年金と同様に、厚生年金の加入期間と保険料の計算の基礎となった標準報酬(月)額(給与と賞与)の平均額から計算します。死亡した人が上記の1~3に該当していた場合は、厚生年金の加入期間が300月未満だと年金額の計算上は300月として計算しますが、4に該当していた場合は実際の加入期間で計算します。
遺族年金は、年金を受給できる遺族の範囲が限られています。特に、遺族基礎年金は妻と子どものみが年金を受給できる遺族となるので、子どものいない妻や夫は年金が受給できません。また、夫の死亡時は遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できた妻でも、子どもが成長すると遺族基礎年金は失権してしまいます。
「もしも…」の場合の備えとして民間の医療保険や生命保険に加入する人も多いかと思いますが、公的年金は障害・死亡といったトラブルに対しても年金を支給します。現役時代でも公的年金が必要な時が来るかもしれません。「もしも…」の場合に備えて、公的年金の手続きをきちんと取っておきましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
◆関連リンク
あなたの年金額をシミュレーション
あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく
世代別の人気年金プランはコチラ