世界で最初に、しかけえほんが登場したのは1306年のことだとされています。円形で動かすことが出来る、羊皮紙製の手書きの占星術の本でした。
そして、いわゆる子ども向けのしかけえほんの出版が始まるのは、18世紀以降です。1765年のロンドンの書肆ロバート・セイヤー刊の道化絵本が始まりだと言われています。17世紀中頃のしかけ絵本は道化師(ハーレクイン)のパントマイムを扱ったものが多かったので「ハーレクィナード」 と呼ばれています。
現在のポップアップ絵本の前身とも言うべきもので、挿絵の描かれためくり(フラップ)を上げたり下げたりすることによって情景が変わったり物語が展開したりするものです。このフラップを使ったしかけは、しかけえほんの中で最も古いものです。
19世紀になると、西欧では、趣向を凝らしたしかけ絵本が大流行しました。
それは、本を開くと絵が飛び出す、つまみをひくと絵が変わる、絵が動く、めくりをめくると絵が現れるというようなものです。それらは、パノラマ本、覗き本、ハーレクィナード、フリッカーブック(パラパラ漫画のこと)などとよばれ、ぬりえや着せ替えなども含めて、「しかけ絵本」と総称して良いでしょう。
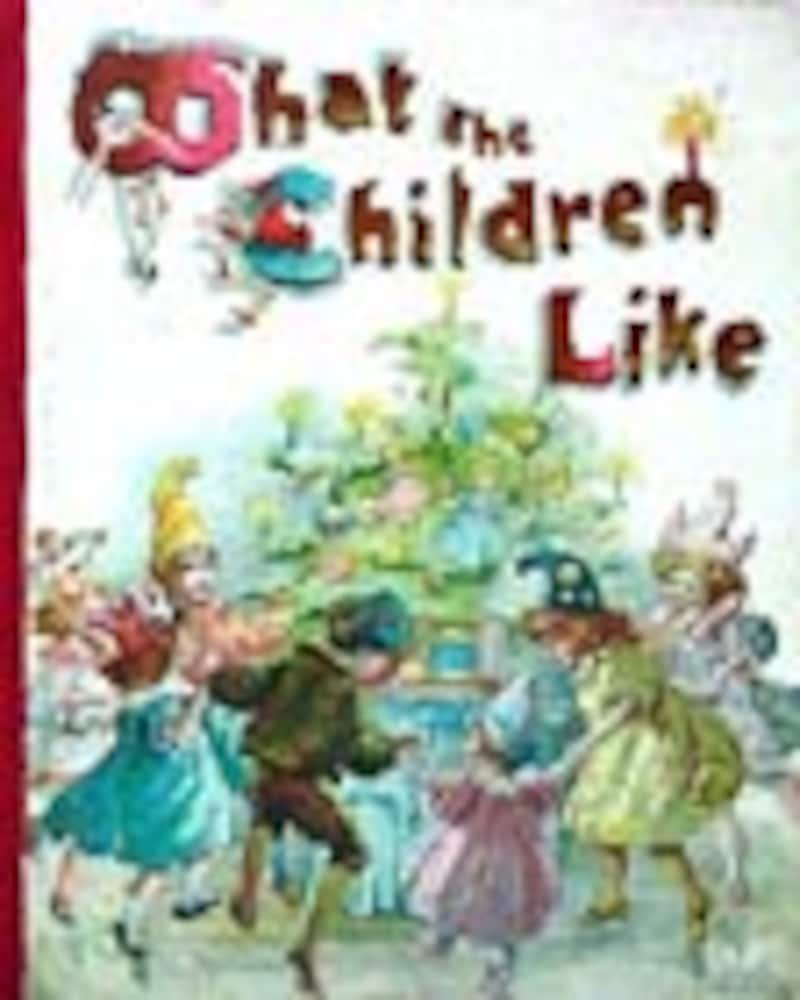 その時代、絵本とおもちゃが未分化であったことから、子どもも大人もこれらの絵本で楽しんだのです。
その時代、絵本とおもちゃが未分化であったことから、子どもも大人もこれらの絵本で楽しんだのです。 19世紀の終わり頃には、アーネスト・ニスターが、「回転する風景」という本を考案しました。紙を何層も重ねた広がりのあるしかけえほんの開発に努力を重ね、上下に絵が変わるブラインド式と、円盤回転式のかわり絵という2つの形式を生みだしたのです。
19世紀の終わり頃には、アーネスト・ニスターが、「回転する風景」という本を考案しました。紙を何層も重ねた広がりのあるしかけえほんの開発に努力を重ね、上下に絵が変わるブラインド式と、円盤回転式のかわり絵という2つの形式を生みだしたのです。






