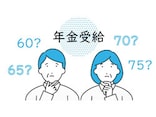文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
16年改正で、年金はどうなった?
 平成16年6月11日の官報で、16年年金改正法「国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されましたが、例によって法文は複雑怪奇です。そこで、私たちが最も気になる年金水準がどのように変わるのかを、おおざっぱに表現してみました。それが、これです↓
平成16年6月11日の官報で、16年年金改正法「国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されましたが、例によって法文は複雑怪奇です。そこで、私たちが最も気になる年金水準がどのように変わるのかを、おおざっぱに表現してみました。それが、これです↓| これからは、固定された保険料の範囲内で給付を行う仕組みに変更 |
日本の年金制度は、現役世代が負担する保険料を高齢者の年金給付にあてるという賦課方式(世代間扶養)が採用されています。
少子高齢社会化が進むわが国では、保険料収入が減り年金給付が増えることが見込まれるため、今後も賦課方式を踏襲していく前提に立つ今回の改正では、社会全体の保険料負担能力を年金額改定に自動的に盛り込むしくみが採用されることになりました。
 この社会全体の保険料負担能力というのは、公的年金制度に加入して保険料を負担している被保険者の減少率であり、一方で年金受給者の平均余命の伸びを勘案した一定率(0.3%)です。
この社会全体の保険料負担能力というのは、公的年金制度に加入して保険料を負担している被保険者の減少率であり、一方で年金受給者の平均余命の伸びを勘案した一定率(0.3%)です。これらを「スライド調整率」といい、新規裁定、既裁定年金の年金額を改定する場合に手取り賃金の伸び率や物価上昇率から控除されることになります。
これが「マクロ経済スライド」です。
マクロ経済スライドを簡単に表現すると、次のようになります↓
| マクロ経済スライドは、「年金の給付水準を、時間をかけて緩やかに切り下げていくしくみ」。 |
このような調整は、恒久的に続くのではありません。
固定した最終的な保険料水準による負担の範囲内で、年金財政が安定する見通しが立つまでの間適用される予定で、厚生労働省の試算(基準ケース)では、平成35(2023)年度に調整が終了し、その後は通常の年金給付か改定方式に復帰するとしています。

では、具体的にどれぐらい下がるかというと…