相続・相続税 人気記事ランキング(2ページ目)
2025年12月17日 相続・相続税内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
11位直系尊属と直系卑属とは?わかりやすく解説【税金ガイドが音声・動画でレクチャー】
相続でよく聞く「直系尊属」と「直系卑属」についてわかりやすく解説します。「尊属」とは、ある人を基準として、その人よりも世代が前の人、つまり父母や祖父母など、上の世代のことを指します。「卑属」とは、ある人を基準として、その人よりも世代が後の人、子どもや孫を指します。【税金ガイドが音声・動画でレクチャー】
 相続・相続税の基礎知識ガイド記事
相続・相続税の基礎知識ガイド記事12位リバースモーゲージの仕組みとは?老後資金対策になる?
リバースモーゲージとは、自宅不動産を担保にして借入を受けて、契約終了後、つまり死亡時などに、担保とした自宅不動産を売却するなどの方法により借入残高を返済するという制度です。最近では、人生100年時代と言われていることもあり、老後の資金対策として注目されているようです。今回は、その仕組みについて解説したいと思います。
 ガイド記事
ガイド記事13位葬儀後に必ずすべき5つの相続手続きとその流れとは
相続発生後に何かと手続きがあるなかで、相続税に関係する必ずすべき手続きがあります。これらは期限があるため、早めに進めることが大切です。
 相続の手続きガイド記事
相続の手続きガイド記事14位相続税申告時の平均7500万円。その実態は?
相続税の申告が必要な割合、取得額、納税額といった数値から相続税の実態を確認しましょう。また、相続が発生した場合の対処法についてまとめました。財産の把握方法、財産の評価、対処法、相続税の申告義務。
 相続・相続税関連情報ガイド記事天野 隆
相続・相続税関連情報ガイド記事天野 隆15位遺産分割協議の基礎を学ぶ
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の取得者・承継者を決めることです。取得者・承継者を決めたら、その内容を書面にします。これを遺産分割協議書と言います。
 相続・相続税関連情報ガイド記事清水 真一郎
相続・相続税関連情報ガイド記事清水 真一郎16位平成27年 贈与税改正のポイント
平成27年から、相続税制だけでなく贈与税制も改正されています。贈与税の最高税率が50%から55%へ引き上げられたほか、税率の区分が6つから8つに変更されています。ポイントを整理しました。
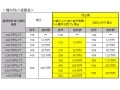 贈与税の計算・申告・納税方法ガイド記事加藤 昌男
贈与税の計算・申告・納税方法ガイド記事加藤 昌男17位遺書が存在しない場合の遺産分割の考え方
もめることも多い遺産分割において、遺言書がない場合の考え方について紹介します。話し合いで決めることになったら是非、活用してみてください。
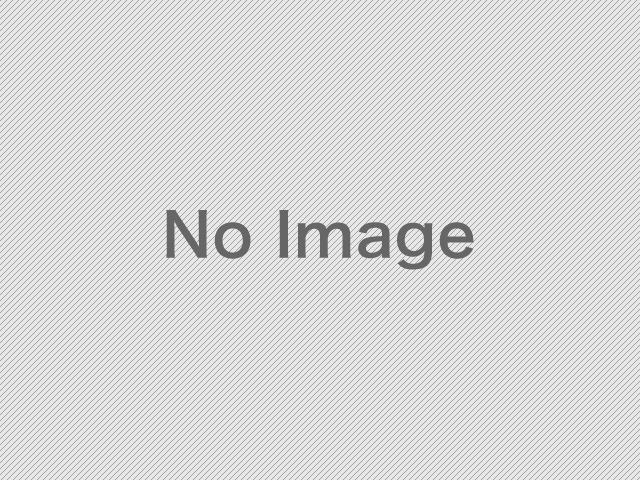 遺産分割でもめないためのポイント投稿記事
遺産分割でもめないためのポイント投稿記事18位思わぬ落とし穴も!? 孫への教育資金の一括贈与
平成25年4月に始まった教育資金の一括贈与制度。子や孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる制度です。相続税対策として人気を集めていますが、注意点もあります。実際に利用した人の声をもとに、制度のメリットとデメリットをまとめました。2019年度税制改正により、期間が「2021年3月31日まで」に延長されます。
 生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事
生前贈与・贈与税の基礎知識ガイド記事19位おひとりさま相続が急増中!? 思わぬトラブルも
おひとりさま相続に関する相談が増えてきました。自分の財産は将来どうなってしまうのか、元気なうちはなかなか本気で考えられないものですが、何もせず万が一があった際は手遅れです。今のうちからできる対策を確認しておきましょう。
 相続の事例・トラブルと対処法ガイド記事
相続の事例・トラブルと対処法ガイド記事20位所有者不明の土地が問題に。知らないうちに当事者に?
相続登記がされず放置状態となっている土地が大きな問題となっています。これは相続によって権利者が多数になってしまったなどの理由が考えられます。もしかしたら自分がいつの間にかこの当事者になっているかもしれません。
 相続・相続税の基礎知識ガイド記事
相続・相続税の基礎知識ガイド記事