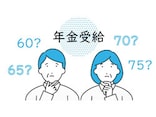年金の繰り下げ受給とは?
「年金の繰り下げ受給」とは、年金の受け取り開始時期を66歳より後に遅らせる制度です。受給開始時期を1カ月遅らせるごとに受給額が0.7%ずつ増額される仕組みになっており、例えば70歳から受け取ると42%、75歳※まで遅らせれば最大84%も増額されます。※昭和27年4月1日以前生まれの人は、繰り下げの上限年齢が70歳まで。
この制度は、「長生きすればするほど年金の総額が増える」点が特徴です。一方で、受け取りを遅らせる分、繰り下げ期間中の生活費を年金以外で賄う必要があるため、その間の手持ちの貯蓄や収入も確認する必要があります。
年金の繰り下げを検討する前に、確認しておきたい8つの注意点
年金の繰り下げは「少しでも多くの年金をもらいたい」と思う人にとっては魅力的な制度ですが、注意点もあります。①加給年金や振替加算は増額の対象外
繰り下げで増えるのは「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」本体だけです。加給年金や振替加算といった家族に関する加算は、繰り下げをしても金額が増えません。さらに、繰り下げている期間中は、これらの加算を受け取ることもできません。
②75歳を過ぎても増額率は上がらない
増額は75歳までが上限です。例えば76歳以降に請求しても、増額率はそれ以上上がりません。また、請求を遅らせた場合でも、増額された年金は75歳時点までさかのぼって決定されます(※1952年4月1日以前生まれの方は70歳までが上限)。
③厚生年金を複数もらえる場合は「同時に」繰り下げが必要
共済年金や厚生年金を複数受け取れる人は、全ての老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要があります。片方だけを繰り下げることはできませんので注意しましょう。
④障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は申請できないことも
65歳から66歳の間に障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合、老齢年金の繰り下げ申請ができないケースがあります。
ただし、障害基礎年金のみを受給している場合など、一部の例外もあります。事前に年金事務所などで確認しておきましょう。
⑤在職中は注意!所得との兼ね合いも
60歳以降に働きながら年金をもらう場合、在職老齢年金制度によって年金の一部が減額・停止される可能性があります。繰り下げ期間中(待機中)の老齢厚生年金も在職老齢年金制度の対象となり支給停止された年金は増額しません。
⑥他の年金が発生したら増額率が固定される
繰り下げ待機中に、配偶者の死亡などで遺族年金など他の年金を受け取る権利が発生した場合、その時点で増額率が固定されます。つまり、それ以降どんなに繰り下げても増額は止まり、翌月からその時点の金額で受け取りが始まります。
⑦保険料・税金への影響も
年金額が増えると、所得が上がるため、医療保険や介護保険の保険料、住民税・所得税などが上がるケースがあります。手取りが増えたと思ったら負担も増えた……ということがないよう、トータルで試算しておくことが大切です。
⑧繰り下げ請求は本人のみ
繰り下げ請求は本人が行う手続きです。待機中に亡くなった場合、遺族が代わりに繰り下げ請求をすることはできません。
参照:日本年金機構「年金の繰下げ受給」
繰り下げに向いている人の特徴
繰り下げは誰にでも向いているわけではありませんが、次のような人は、繰り下げによってメリットを得やすいといえます。・年金以外の収入がある人:繰り下げ期間中の生活をカバーできる蓄えや仕事収入がある人。
・健康状態がよく、長生きの自信がある人:受給期間が長くなるほど、増額のメリットを享受しやすくなります。
・税金や保険料の増加に対応できる人:年金が増えても、税負担が大きくなり過ぎない人は、繰り下げが有利になりやすいです。
まとめ
年金の繰り下げは、将来の受給額を増やせるチャンスです。ただし、「いつ請求するか」で得られる金額や負担が大きく変わります。また、繰り下げの可否や影響は、健康・家計・家族構成によって異なります。「少しでも多くもらいたい」だけではなく、「いつまで元気に過ごせるか」「生活費はどう確保するか」などもあわせて考えましょう。