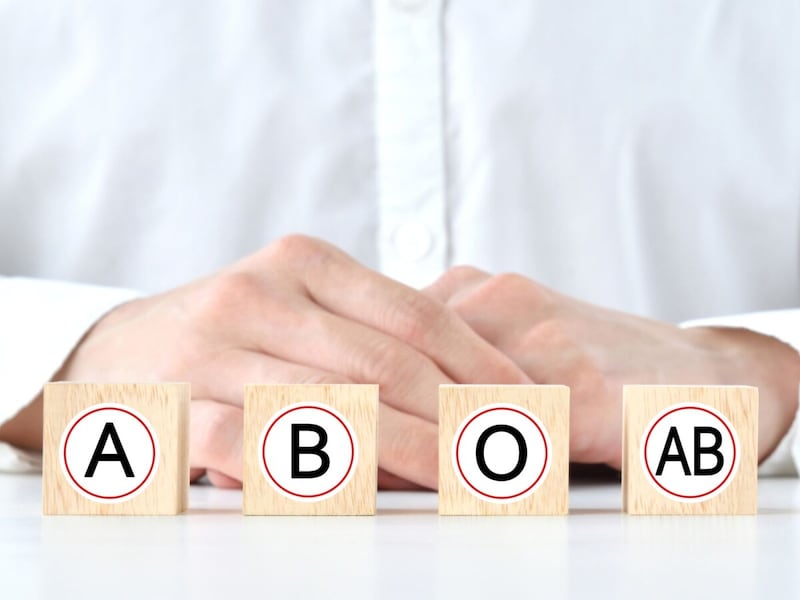
自分の血液型が分からない……緊急時でも大丈夫?
血液型は、1歳以降であれば、病院を受診し、調べることが可能です。ただし、輸血など医療上の必要がない場合は保険が適応されず、「自費診療」になります。費用は医療機関によって異なりますが、消費税込みで550円程度からが一般的です。
血液型を知らなくても問題なし! 輸血前に必ず行う「交差適合試験」とは
交通事故や手術などで輸血が必要になった場合、輸血用血液と患者の血液が合うかを調べる「交差適合試験(クロスマッチ)」が行われます。これは安全に輸血を行う上で欠かせない検査です。事前に血液型の申告があっても、必ず再確認のために検査が行われます。申告された血液型は、根拠が不明確な場合があり、誤った輸血には危険が伴うためです。そのため、血液型をあらかじめ知っているかどうかで、輸血時に問題が生じることはありません。
「不適合輸血」のリスクは? Rh型など多項目の検査が必要なワケ
血液型が不明で、輸血に一刻を争うような緊急時には、AB型の赤血球が使われることがあります。AB型の赤血球はA型・B型抗原を持たないため、ABO型に限ればどの血液型の人にも輸血可能だからです。ただし、ABO型以外の血液型(例えばRh型)が異なる場合は、不適合輸血となり、血管内で赤血球が壊れる「溶血反応」を起こしてしまうことがあります。溶血反応が起きると、血管痛、胸部の不快感や胸痛、腹痛、輸血部位の灼熱(しゃくねつ)感、発熱、悪寒、呼吸困難、血圧低下、嘔吐などの症状が現れ、重症化すると腎不全を引き起こすこともあり、危険です。血液型抗原にはRh型以外にも多くのタイプがあるため、医療現場では多項目で検査しています。
科学的根拠のないハラスメントリスクも……血液型を知るメリット・デメリット
自分自身の血液型を知っていれば、ちょっとした会話のタネになったり、血液型占いなどを楽しめたりというメリットがあるかもしれません。しかし、血液型と性格などに科学的な関連はありません。医療を受ける上で、血液型を知っているかどうかで差が出ることもありません。また、血液型をもとにした偏見や「いじり」など、いわゆる「ブラッドタイプハラスメント」につながるリスクもあります。結果を知ることで心理的にネガティブな影響を受ける場合もあるため、「知るかどうか」は個人の考え方次第と言えるでしょう。







