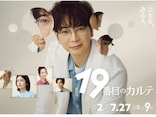今回の参院選では、いまひとつ争点として機能していない「原発」問題。各党とも少しずつ異なった立ち位置となっていますが、むしろ「脱原発」後のエネルギー問題において、どれだけ現実を捉えた公約となっているかに目を向けたいところです。
主な政党の原発問題に対するスタンスは以下の通り。
・自民党 「安全性の確認を条件に再稼働する」
原子力に依存しなくてもよい経済・社会構造の確立を目指しつつも、原子力発電については「安全第一主義」を前提に、すべての原発について3年以内の再稼働を目指す。
・公明党「原発に依存しない社会を目指す」
原発の新規着工を認めず、LEDなどの新技術で省エネを推進。太陽光・熱や風力などの再生可能エネルギーを推進し、現在の発電割合1%弱を2030年までに30%にまで引き上げたい。
・民主党 「2030年代の原発(稼働)ゼロ」
「40年運転制限制を厳格に適用」「原子力規制委員会の安全確認を得たもののみ、再稼働」「原発の新設・増設は行わない」の三原則を原則に適用し、2030年代の原発稼働ゼロを目指す。
・みんなの党、「電力自由化・原発ゼロ」
当面の電力需要には高効率の火力発電や再生可能エネルギーの普及・促進などで対応。電力自由化がもたらす市場原理による原発淘汰を促すとともに、廃炉に関する産業・ビジネスを推進する
現状で原子力による発電の最大のメリットはウランという手に入れやすい原料による「電力の安定供給」でしょう。推進派が理由としてあげる「CO2排出量」や「コスト」については、反対派から疑問符も投げかけられています。
いっぽう最大のデメリットと言えば、一度事故を起こしてしまったがゆえ疑問符がつきまとっている「安全」と「安全に対する恐怖」でしょう。ふだん快適だとしても、いったん大きな事故を起こすと国の将来に暗い影を落とすほどの過酷な事故になる。そのことを国民が許容するのかどうか。
いっぽうで「脱原発」を謳うにしても、現実問題、代替エネルギーはあるのか。あるとしたら何か。さらに原発にまつわる地元への交付金など、原発にはさまざまな人の思惑がつきまとっています。この国のエネルギー施策をどう考えるか、各党の政策を冷静に受け止めて、しっかりとした選択をしたいものです。
また、避けては通れないのが、原発事故問題。廃炉へのロードマップについては当初2021年末とされていた1~3号機の燃料棒の取り出しの着手が1年半前倒しされ、2020年6月頃にスタートすることになりました。4号機の燃料棒の取り出し目標も前倒しされ、今年の11月に開始し、来年末に完了となっています。しかし、増え続ける汚染水への抜本的な対策は急務で、2014年度末を目標とする注水の建屋内循環ループシステムの構築が待たれます。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。