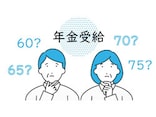何と言ってもラッキーだったのは、妻の年齢要件が1965年の法改正で撤廃されていたことでした。

彼女の夫が亡くなった当時の法律では、子が18歳になった時に妻の年齢が40歳未満であれば遺族年金の受給権を失うというものでした。
彼女が39歳の時に一人息子が18歳になったから、法律がそのままであったなら、遺族年金の受給権はその時点でなくなっていたのです。しかし息子の誕生日は12月でしたので、同じ年の6月に行なわれていた「妻の年齢要件の廃止」の法改正のおかげで、彼女の遺族年金の受給権は32年経っても消えることがなかったのです。
裁定請求に時間はかかったけれど、遺族年金は支給された!
しかし、受給権があっても裁定請求するのは容易ではありませんでした。30年以上前の死亡診断書や当時の生計同一の証明、すでに手元になかった夫の年金手帳の再交付、厚生年金加入中の死亡であることを証明するための被保険者期間の照会など、添付する書類を集めるのには時間がかかりましたが、本当に運よくすべてを揃えることができ、遺族年金を受給することができたのです。
遺族年金がもらえると知ったその日、「夫が急死した時に年金が受け取れていたら、もっともっと楽に生活できただろうに」と、遠い過去を振り返って涙を流した彼女でした。しかしその後で再開した時は、遡って受け取った5年分の年金440万円余りの一時金のほとんどを、同居している息子の住宅ローンの繰上げ返済にあてさせたという話をし、妙にさっぱりした表情だったのがとても印象的でした。
そして、一言
「私、70歳を超えた頃から目が見えにくくなってきて洋裁するのがきつくなってきたの。だから、お父さんが(夫)が天国からそんな様子を見ていてくれて、年金をくれたのだと思います」と。
やっぱり、遺族年金や障害年金はその額の多寡にかかわらず、人の心をほっと癒してくれる存在でもあるのですね。
◆関連リンク
あなたの年金額をシミュレーション
あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく
世代別の人気年金プランはコチラ