落語 人気記事ランキング
2026年02月03日 落語内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
1位落語の枕(まくら)とは?役割や演目、始まり方を予想する楽しみ方
落語には、本編に入る前におこなう「枕(まくら)」というものがあります。枕とは、落語の始まり方として定着している、落語を聞きやすくするための重要な手法で、より面白く聞くには枕を理解する必要があります。今回は、落語の「枕」を紹介します。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司2位噺家の「扇子」は見立て道具!その使い方とは
噺家の必需品といったら「扇子」と「手ぬぐい」。この二つを噺家は様々な小道具に見立てて、落語を盛り上げます。今回はその必須アイテム、「扇子」ついて紹介します。使い方などを理解し、注意して見てみると、きっと落語の面白みがさらに膨らむと思いますよ。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司3位落語を習うには? 落語の教室・身につける方法
落語を見ているだけじゃ物足りないと感じたら、落語を習うのはいかがでしょうか? 長い人生の趣味としてはうってつけの趣味だと思います。短い演目でも一席でも話せれば、余興の出しモノに困りませんよ。今回は落語の習い方を紹介します。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司4位隔週刊 落語百選 DVDコレクションは凄い!
分冊百科でおなじみのデアゴスティーニ・ジャパンより10月7日に発売される『隔週刊 落語百選 DVDコレクション』について取材してまいりました。前代未聞の落語の楽しみ方を変える凄い企画です。
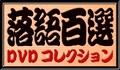 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司5位「時そば」の醍醐味はどこ?!特徴や手法など
「時そば」は、冬になるとあちこちの寄席や落語会で、いやというほど聴けるネタです。落語好きな方でもなくても、一度はどこかで聴いたことのある噺がこのネタではないでしょうか?落語ネタの中でも屈指のスタンダード「時そば」の本当の楽しみ方を紹介します。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司6位オススメ「落語映画」DVD
ここ数年、年に一本ペースで落語関連の映画が作られるれてます。どの映画も落語関係者が監修に入っており落語ファンでも楽しめる内容です。今回は落語を題材としたオススメの「落語映画」を紹介します。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司7位落語の真打とは?真打の意味と真打制度について
落語界における「真打」の意味と「真打制度」について解説。噺家にとって真のスタートであり最高の身分である「真打」。真打となると噺家の敬称である師匠と呼ばれます。それまでの険しくも充実した道のりと、真打の語源、真打昇進披露をあわせて紹介します。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司8位「上方落語」ってなに?
明石家さんま、笑福亭鶴瓶、桂三枝、桂文珍、彼らはみな落語家です(さんまのみ過去形)。彼らのトークの上手さや面白さの基礎は落語です。今回は関西のお笑いの原点である上方落語を紹介します。
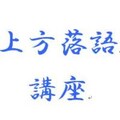 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司9位席亭に聞く:鈴本演芸場編/その1
今年で開席150年となる鈴本演芸場。この都内で最も歴史がある定席の六代目席亭である鈴木寧氏に寄席の魅力と、普段なかなか知ることのできない席亭のお仕事について伺ってきました。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司10位落語のオチとは? オチの種類を解説!
落語は「落とし噺」と呼ばれるため、どんな演目にもオチがあると思われますが、オチがない落語も数多くあります。落語=落し噺ではなく、噺にオチがなくても落語家が演じればすべて落語なのです。落語のオチにもいくつかのパタ-ンがあり、その種類ごとに分類されます。
 落語関連情報ガイド記事清水 篤司
落語関連情報ガイド記事清水 篤司