本記事では、リスクの高い物件を見抜くための具体的なチェックポイントを、株式会社さくら事務所の土屋輝之氏が解説します。
修繕積立金のリスクを見極める3つの特徴
家計を揺るがす「修繕積立金」のリスクは、購入前の段階でその兆候を見抜くことで、未然に防ぐことができます。将来の負担増という不測の事態を避けるために、特に注意すべき3つの着眼点をご紹介します。1:1平方メートル(㎡)の単価は「相場」に対して適正か
まず注意したいのが、販売時の月々の負担額を魅力的に見せるため、デベロッパーが意図的に修繕積立金を低く設定しているケースです。ここで重要になるのが、客観的な「相場」と比較する視点です。国交省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、建物の規模に応じた㎡単価の目安が示されています。例えば、多くのマンションが該当する「20階未満、延床面積5000~1万㎡」の場合、平均値は252円/㎡・月とされています。
加えて、検討物件の周辺エリアで、類似した条件のマンションが実際にどの程度の修繕積立金を設定しているのか、相場を調べてみることも有効です。
もし検討物件の金額がこれらの目安を大幅に下回るようであれば、その金額設定で将来の修繕が賄えるのか、納得できるまで具体的な説明を求める姿勢が大切になるでしょう。
2:長期修繕計画は真の意味で長期的視点に立っているか
次に、長期修繕計画書を精査しましょう。ここで見るべきは、単に30年といった期間が設定されているかだけでなく、その中身の妥当性です。◆計画の網羅性
1回目の大規模修繕だけでなく、エレベーター更新や給排水管更新といった巨額の費用が発生する2回目、3回目以降の工事費用が適切に計上されているか。また、見落とされがちな玄関ドアや窓サッシの交換費用など、必要な項目に抜け漏れがないかを確認します。
◆修繕周期の妥当性
例えば、大規模修繕工事が画一的に「12年周期」で計画されている場合、本当にそのタイミングで実施する必要があるのか、という視点も重要です。建物の状態によっては15年、18年へと周期を延ばすことで、長期的なコストを大幅に圧縮できる可能性があるからです。
3:将来のコスト要因を把握し、第三者の視点も活用する
マンションの設備は、将来の修繕コストに直結します。特に、維持・更新に多額の費用がかかる機械式駐車場が多く設置されている場合は注意が必要です。長期修繕計画に、それらの維持・更新費用が具体的に盛り込まれているかを確認しましょう。
また、管理会社が作成した計画をうのみにしない姿勢も大切です。マンションの形状や設備、これまでの修繕履歴は一棟一棟全て異なります。「他のマンションでもこうです」という説明が、必ずしもご自身が購入予定のマンションに当てはまるとは限りません。
もし少しでも疑問を感じたら、管理会社とは異なる第三者である専門家に計画の妥当性を診断してもらうことも、資産を守る上で非常に有効な選択肢となります。
将来を見据えた、賢いマンション選びの新常識
マンション購入で大切なことは、提示された情報をうのみにせず、「本当にこの計画は自分たちのマンションにとって最適なのか?」という当事者意識を持つことです。そして、目先の安さだけで判断するのではなく、長期的な視点でそのマンションにとっての適正水準を見極めることにあります。その主体的な一歩こそが、住宅ローンと修繕積立金の“Wコスト負担”からご自身の家計と大切な資産を守る、最も確実な方法となるでしょう。
【関連記事】
住宅ローンだけじゃない……マンション購入では「修繕積立金」の負担に備えよ
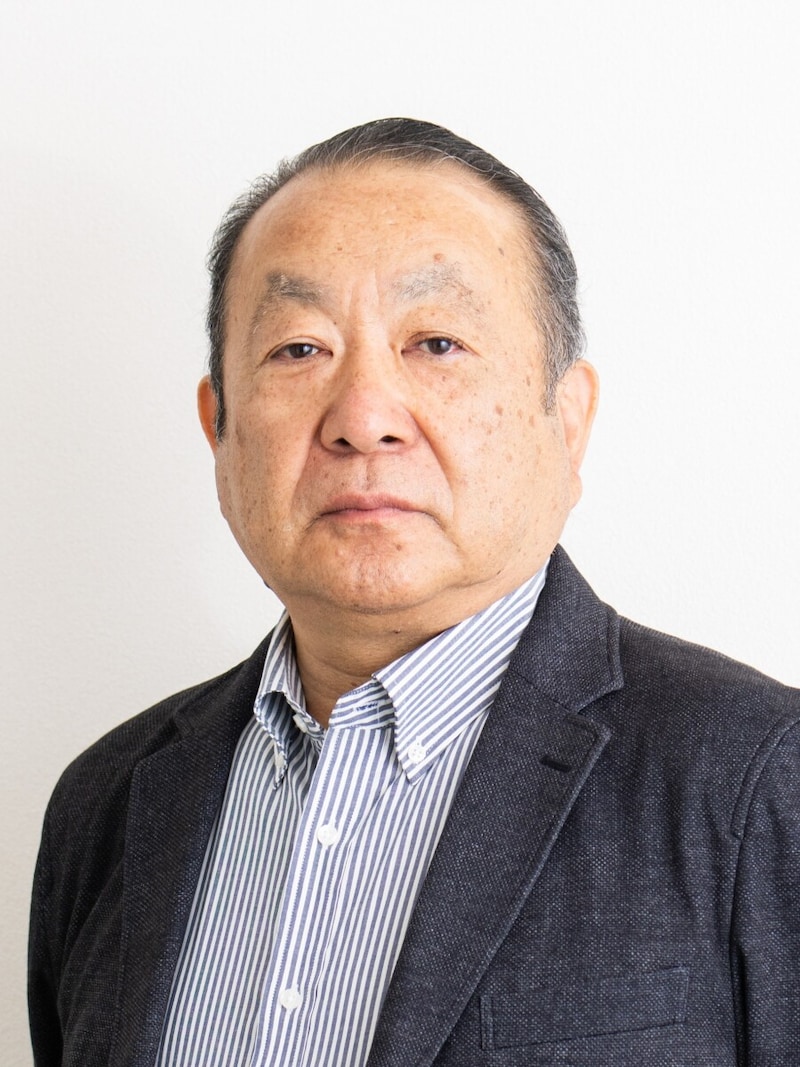
株式会社さくら事務所・マンション管理コンサルタント 土屋氏
株式会社さくら事務所 マンション管理コンサルタント
不動産売買及び運用コンサルティング、マンション管理組合の運営コンサルティングなどを長年にわたって経験。2003年に株式会社さくら事務所に参画。不動産、建築関連資格も数多く保持し、深い知識と経験を織り込んだコンサルティングで支持される不動産売買とマンション管理のスペシャリスト。メディア出演・講演経験多数。自身が取材協力した「マンションバブル41の落とし穴」(小学館)が発売中。






