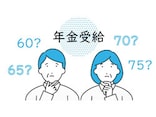とはいえ、「何から始めればいいの?」「どこに書類を出すの?」「必要なものは?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。今回は、年金の受給を初めて迎える方向けに、手続きの流れや提出書類、スムーズに進めるためのポイントなどをやさしく解説します。
初めての老齢年金、受給までの流れ
受給開始年齢に達したら、ご自身で請求手続きを行う必要があります。手続きの流れはしっかりと決まっており、65歳(または特別支給の老齢厚生年金の対象者であれば60~64歳)の誕生日を迎える3カ月前からスタートします。
ここからは、初回の年金受給までの手順を分かりやすく解説します。
・第1ステップ:事前案内を受け取る(65歳の約3カ月前)
日本年金機構は、受給開始年齢(通常は65歳、特別支給の老齢厚生年金の対象なら60~64歳)の約3カ月前に、基礎年金番号や加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」と案内ハガキを本人宛に送付します。この年金請求書には基礎年金番号や加入記録があらかじめ印字されていますので、内容に誤りがないか確認しましょう。
もし、加入記録に漏れ・誤りがある場合は、年金事務所や「ねんきんネット」に問い合わせをしましょう。
・第2ステップ:必要書類の準備
請求にあたっては以下の書類が必要です。
・年金請求書(届いたものを使用。電子申請も可能)
・確認書類(戸籍抄本・住民票・マイナンバーなど/省略可の場合あり)
・年金手帳(基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合)
・金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
書類の内容や提出先によって必要なものが異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
・第3ステップ:申請手続き
年金請求書は、65歳の誕生日の前日以降(または受給開始年齢到達以降)でなければ受け付けられません。それ以前の提出は無効です。
提出方法は、窓口・郵送・オンライン(ねんきんネット)から選べます。被保険者の種類に応じて書類の提出先が異なるため、案内を確認して正しい場所へ提出しましょう。
・老齢基礎年金だけをもらう人(第1号被保険者期間のみの方)は、お住まいの市区町村の窓口へ
・老齢厚生年金をもらう人や第3号被保険者は年金事務所へ
・共済組合などの加入期間がある人は、年金事務所または各共済組合などへ
また、すでに60~64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている方も、65歳になってから老齢基礎年金や65歳以降の厚生年金を受け取るには、改めて手続きをする必要があります。自動で切り替わるわけではないため、65歳の「年金請求書(ハガキ)」を必ず返送しましょう。
・第4ステップ:審査と決定通知
申請後、年金機構により内容の審査が行われ、およそ1~2カ月後に「年金決定通知書(年金証書)」が届きます。
・第5ステップ:初回支給と通知
その後、さらに1~2カ月ほどで「年金振込通知書」が送付されます。初回の年金は年金証書の受領から約50日後に口座へ振込されます。
以降は、通常通り、偶数月の15日に前2カ月分の年金が支給されます(15日が休日の場合は直前の平日)。
年金の初回受給には“手続き”が必要。早めの準備で安心を
年金の受給手続きは、誕生日の3カ月前から始まり、必要書類の準備や提出先の確認、申請タイミングの把握など、段階ごとにやるべきことがあります。「まだ先の話」と思っていると、いざというときに慌ててしまいがち。余裕を持って準備を進めておくことで、スムーズに初回受給を迎えられます。
人生の新たなステージを安心してスタートさせるためにも、年金受給の手続きは計画的に進めましょう。
参照:日本年金機構「老齢年金の請求手続き」