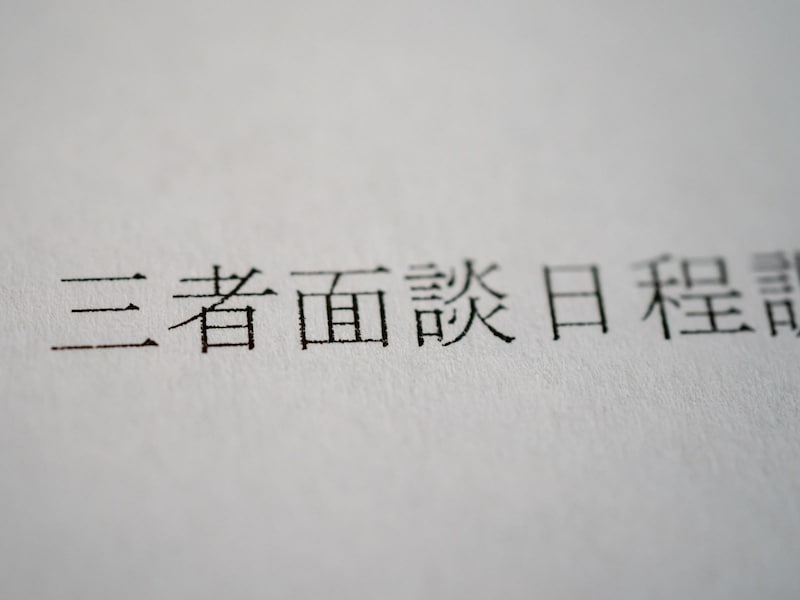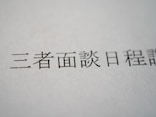『親の過干渉こそ最強の大学受験対策である。』(菅澤孝平著)では、激変した大学受験を乗り切るための、親の戦略的な関わり方についてお伝えしています。
今回は本書から一部抜粋し、「大学受験のシン常識」の1つ、なぜ「先生頼み」では成功しないのかについて紹介します。
「先生が何とかしてくれる」という危険な思い込み
親世代が現役のころは、大学受験は手続き一つ取っても今ほど細かくはなく、学校で調査書をもらい、願書を書きさえすれば出願できる時代でした。しかし、今はオンラインでの出願が主流ですので、ただ願書を用意するだけでなく、ユーザー登録をしたりコードを取得したりといった手間も要りますし、締め切り時間まで決まっていますが、学校や塾ではそこまで手伝ってはくれません。
学校の先生、塾や予備校は、昔はいろいろとしてくれたでしょう。
生徒1人ひとりに親身に接している先生もいたでしょうし、三者面談や二者面談ではとことん相談に乗ってもらえたことと思います。
もちろん今でも熱心な先生はいますし、先生が何もしてくれないわけではありません。ですが、2019年に施行された働き方改革関連法案は、高校の教員も対象です。
時間を意識した働き方を追求する結果、どこかに皺寄せが生じるのは無理もないことだと思います。
担任は20~30代、親世代と話が合わないのは当然
大学受験で誰かに相談をと考えたとき、真っ先に思いつくのはおそらく高校の担任の先生ではないでしょうか。しかし、担任の先生は20~30代。つまり、大学受験を経験したのは10年ほど前のことで、比較的新しい時代に大学受験を乗り越えている層なのです。
親が大学受験を経験したのはおそらく20~30年ほど前でしょうから、親と同世代の先生は主任以上になっているため、前提として担任の先生は親の発想とは異なると、思っていたほうが無難です。
よって、親の常識や当たり前に思うことを担任に伝えても、昔の話としか認識されない可能性が非常に高く、むしろ生徒側に近い価値観を持っているため親の思うような対応はまずしてもらえないでしょう。
親と担任の間で最も齟齬が生じやすいのは、「出願戦略の考え方」と「現状の成績に対する認識」です。
出願戦略については、先ほどお話しした通り大学のレベル感が変わっているため、それを親が理解していなければ先生との間でミスマッチが生じます。
また、親は高校3年生の1学期で成績が振るわなかったとしても、「夏前に部活を引退した後でも挽回できる」「塾や予備校は秋からでいい」と思うかもしれません。
確かに当時は、それでも成立したのでしょう。しかし、当時よりも大学受験の難易度が上がっているわけです。
高校の先生は、そういった考えを持っている親に対して「現実を理解できていない親」と認識するだけだろうと思います。
そもそも高校の先生が見ているのは、自分の子ども一人ではなく1クラス35人全員の進路です。。頭では分かっていても、意外と先生に期待しがちな親が多いので注意してください。
担任が我が子に使える労力はたったの3%
担任が一人の生徒に使える労力は、35人で均等に割ると3%にもなりません。自分自身、35個もの仕事をマルチタスクでこなしている状況を想像してみると担任の状況、そして気持ちが分かるはずです。「自分の持つ労力の3%でできることがどんなことか」と発想すると、少なくともあれもこれもしてもらえるようなことはあり得ないということが理解できるだろうと思います。
菅澤孝平(すがさわ こうへい)プロフィール
シンゲキ株式会社代表取締役社長。千葉県鎌ケ谷市出身。高校時代に偏差値32を経験。担任の先生と二人三脚で受験勉強をし、明治大学に逆転合格。その時の経験をもとに、誰かの挑戦に「伴走」したいという思いから、明治大学政治経済学部在学中にオンライン塾事業を始める。2021年、シンゲキ株式会社を創業。著書に『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)がある。