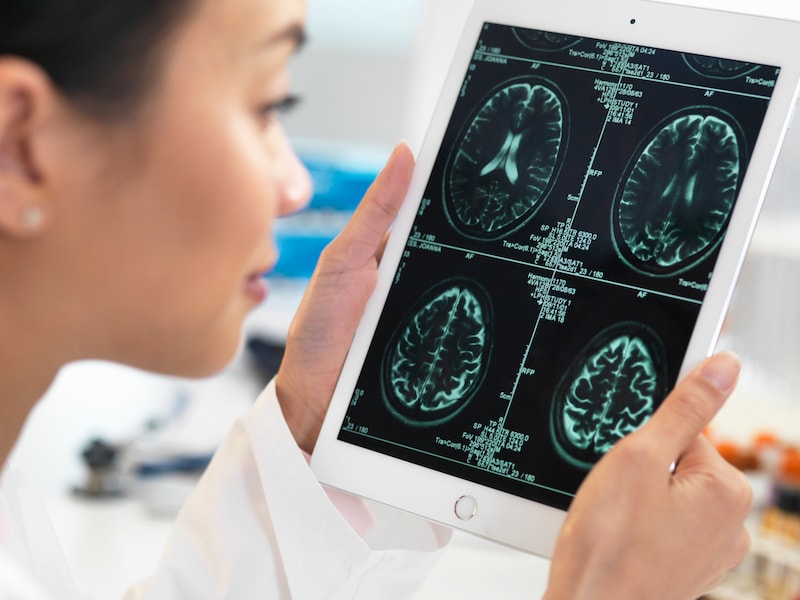突然ですが、働き盛りの皆さんは「認知症なんてまだ先の話」と思っていませんか? しかし、40~64歳という比較的若い世代で発症する「若年性認知症」が、世界的に増加しているのです。
2025年、中国で行われた大規模臨床研究から、「働き盛りの認知症」が増えていることが明らかになりました。若年性認知症に関する最新論文を基に、分かりやすくご紹介します。
世界で急増する40~64歳の若年性認知症……早期発症型アルツハイマー病とは
中国の研究チームは、1990年から2021年にかけて、40歳から64歳の若年成人における若年性認知症の患者数や、それに関連する健康指標が世界的に増加傾向にあることを明らかにしました。この研究は中国広州市、Jinan University First Affiliated HospitalのZenghui Zhang氏らによって、European Journal of Neurology誌2025年3月に報告されました。以下で研究の流れをご紹介します。
1. 研究の背景
一般的に、認知症は人生の晩年期に発症しますが、40~64歳という若い年齢にも発症することが知られています。これを「若年性認知症」と言います。
働き盛りの認知症である若年性認知症は、65歳以降の認知症よりも、仕事や金銭面の影響、職場や家族の影響が強くなることは、想像に難くありません。
2. 研究の目的
そこでこの研究では、1990年から2021年までの間に、40歳から64歳の若年成人において、若年性認知症の以下の数値が世界全体、各地域、そして国ごとにどのように変化したかを調べることを目的としました。
・有病率(病気を持っている人の割合)
・発生率(新たに病気になる人の割合)
・死亡率
・DALYs(障害調整生命年:病気や障害によって失われた健康な生活の年数を示す指標)
加えて、どのような人が若年性認知症を発症しやすいのかについても調べました。
3. 研究の方法
研究チームは、204の国と地域における371の疾病と傷害の健康への影響を評価する世界疾病負荷研究(Global Burden of Disease Study, GBD)2021の膨大なデータの中から、40歳から64歳までの成人に関する情報を抽出しました。GBDは、地域的・国際的な包括的な疾病負荷研究プログラムです。世界保健機関(WHO)も政策策定にGBD研究の結果を参考にしています。
上記のデータから、EOADの年齢を考慮して調整した有病率、発生率、死亡率、DALYsなどの主要な健康指標を分析しています。さらに21の地域と204の国々における、これらの指標の平均年間変化率(AAPC)を算出し、若年性認知症の非致死的負担や若年性認知症のリスク因子についても調査を行いました。
研究結果 「若年性認知症は生活習慣に関連し、増加している」
研究の結果、以下のことが明らかになりました。1. 若年性認知症は増加の一途をたどっている
2021年における世界の若年性認知症の総患者数は、なんと775万人に達し、1990年の367万人から2倍以上に増加していたのです。これは非常に衝撃的な数字です。
特に、2021年のデータでは、若年性認知症の有病率は女性(428万人)の方が男性(346万人)よりも高い傾向が見られました。
また、地域差や社会経済状況も若年性認知症と関連することが分かりました。
地域別では、高所得の北米地域や東アジアで有病率が特に大きく増加していました。 その一方で、サハラ以南アフリカの中部や西部では、有病率が減少する傾向も観察されたそうです。
さらに、社会人口学的指標(SDI)という、国の所得、教育水準、出生率などを総合的に示した指標が高い地域ほど、若年性認知症による影響も高い傾向が見られました。つまり、「裕福になるほど、若年性認知症が多くなる」というわけです。非常に興味深い結果と言えるでしょう。
2. 若年性認知症は生活習慣や死亡にも関わっている
その背景には、生活習慣が関わっていることが分かっています。特に、
1. 喫煙
2. 空腹時血糖値の上昇
3. 高いBMI(肥満度指数)
の3つは、若年性認知症の発症リスクを高めたり、病気の進行を早めたりすることで、約106万年分の健康な生活年数(DALYs)を失わせていると分かっています。若年性認知症では、世界全体で約377万年分のDALYsが失われていると言われています。
つまり、EOADによって失われた健康な時間(DALYs)全体の約28%(106万年 ÷ 377万年)が、これら3つの危険因子に起因する可能性がある、ということです。
また、若年性認知症は死亡にも大きな影響を与えており、2021年だけで、約7万人の死亡とつながっています。
臨床医の視点から考察する、若年性認知症の増加理由と私たちにできること
世界的に、働き盛りの世代で若年性認知症の影響が、急増していると明らかになったことは、非常に重要です。社会全体での対策が急務だと言えるでしょう。住む地域や性別による影響の違いもあるようですが、何よりも「喫煙」「高血糖の状態」「肥満」などの改善可能な問題点を見直すことが、若年性認知症予防に重要なことは明らかです。
筆者の周りにも、認知症になったご家族の介護をしている医療従事者の同僚や、小児科診療に訪れる子どもがいます。現在、認知症は、複数のアンケート調査でがんを抜き、「なりたくない病気・症状」の第1位になっています。「ヤングケアラー」も社会的な課題になっていますが、身近な人が認知症になったり、介護者になって疲弊してしまったりする様子から、多くの人が認知症を恐れているのでしょう。
認知症のメカニズムと予防法はまだ明らかになっていない点もありますし、努力しても発症してしまうケースもあります。しかしこれまでの調査や報告から、認知症は急になるのではなく、運動や睡眠、食事面などの生活習慣やストレスなどが関連し、徐々に進行していくことが分かっています。自分には関係ないと考えず、元気なうちから普段の生活習慣を見直し、できる限り若年性認知症の対策をしていきましょう。
■参考論文
Zenghui Zhang,Shaojie Han,Huimin Zhu,et al.Global, Regional, and National Burden of Early-Onset Alzheimer's Disease and Other Dementias in Young Adults Aged 40-64 Years, 1990-2021: A Population-Based Study.Eur J Neurol. 2025 Mar;32(3):e70116.