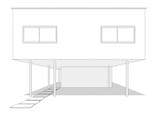今でも使われているのですか?
何に注意したらよいでしょうか?
アスベスト建材を見分ける方法はありますか?
アスベストの調査からアスベスト建材発見→解体作業までの流れ
| 1. 第一次スクリーニング | 設計図書(施工記録)などから使用建材や建材製造年、施工部位などを調査しアスベスト含有の有無を判断する。(書面での事前調査) ↓ |
| 2. 第二次スクリーニング | 書面で不明の場合、分析調査(試料採取)を行う。 ↓ |
| 3. 作業計画の作成 | 石綿が使用されている場合に作成し、関係労働者に知らせる。 ↓ |
| 4. 届出 | 労働安全衛生法に基づく届出。環境省では全ての建物の解体時に届出を義務づける方針で、国交省は建築基準法による規制を検討中。 ↓ |
| 5. 作業者への特別教育の実施 | アスベスト含有建材の解体作業者は特別講習を受けることが義務づけられている。 ↓ |
| 6. 作業主任者の選任 | ↓ |
| 7. 呼吸用保護具及び保護衣等の着用 | アスベストは極細粒子なので、粉じん用マスクでは吸引してしまう。アスベスト専用のものを使用することになっている。また身体を外部と隔離状態にする。 ↓ |
| 8. 解体方法の確認と指導 | 解体現場と外部はビニルシート・2重ドア等により厳重に隔離する。 ↓ |
| 9. 石綿含有建材の除去作業 | 除去は極力手作業によって、アスベストの飛散を抑える。 ↓ |
| 10.建設廃棄物の集積・清掃・搬出及び主要構造部の解体 | アスベストを外部に持ち出さないようにする。 ↓ |
| 11.保護具の管理 | 保護具は使い捨てで、厳重に処理する。 ↓ |
| 12.健康管理 | ↓ |
| 13.石綿含有建材廃棄物の処理 | 特別な工程で処理。 |
これから家をリフォーム・新築する人へアドバイス
こちらへ→