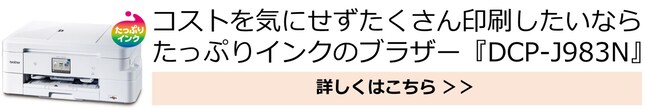手にとり、アクションしてもらうために考えたいこと
自分の思いやセンスを形に! “ZINE(ジン)” の魅力とつくり方のポイント
誰でもクリエイターとなり、発信したい情報を冊子として制作する“ZINE(ジン)”。同人誌やミニコミ誌とはちょっと違う、そんなZINEの魅力やつくり方を専門家に聞きました。
提供:ブラザー販売株式会社
お話をうかがった方
諫山 三武(いさやま・さぶ)
1988年、福岡県出身。東京都在住の編集者。大学在学中にZINE『未知の駅』を創刊。「もうひとつの生き方」をテーマに、国内外のDIY実践者を取材し続けている。
“ZINE(ジン)”って何? 同人誌とはどう違う?
自主制作の小冊子と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか? 人によっては、アニメやゲームなどのファンが手掛ける同人誌かもしれません。そんな同人誌と広義は同じながら、少し毛色が異なるのが今回、ご紹介する“ZINE(ジン)”。
ZINE『未知の駅』編集長でもある諫山さんによると、もともとはアメリカのSF小説ファンがつくり始めたもので、“ファンジン(fanzine)” と呼ばれていたそうです。その後、1980年代から1990年代にかけて、アメリカ西海岸のスケーターたちが情報を紙にまとめてホッチキスで留め、仲間内で回し読むようになったのが、現在のZINEに近いものだとか。
諫山さん「といっても、ZINEに明確な定義はありません。共通するのは、ミニマムコミュニケーション、つまり小規模という点。僕が手掛けている『未知の駅』も発行部数は500部くらいで、友人とその友人などと一緒に手作業で製本しています」
もちろん、テーマも体裁も自由。
諫山さん「カレー好きな人がカレー屋探訪記をまとめたZINE、服が好きだからその情報だけに特化したZINE、脱原発を掲げるZINEなど、それぞれが伝えたいことを形にしています。体裁は、紙をパチパチッと留めただけのような、手作り感満載のものがいかにもZINEらしいですが、折りたたんだだけだったり、折り紙や立体にしたりする人も。極端な話、紙をクシャッと丸めただけのものでも、つくり手が“これはZINE”と言えばZINEなんです」
こうした自由度の高さ、多種多様さは、ZINEを扱うお店に行くと一目でわかるとか。
諫山さん「僕は東京・新宿のI.R.A.(IRREGULAR RHYTHM ASYLUM イレギュラー リズム アサイラム)や、代官山 蔦谷書店のZINEコーナーなどにもよく足を運びますが、サイズひとつとっても、手のひらに収まるほど小さな豆本から、597mm×841mmのA1サイズなどまで、本当にさまざま。大きいものは並べられないので、壁に吊してあったりしておもしろいですよ」
“PARC自由学校” にて、2015年に諫山さんが行ったZINE講義の1シーン。こちらはイラストレーターの受講生による『IMAGINE/IMAZINE』。折り目を開くたび、さまざまなイラストが現れる綴じないZINEです。
自らの手でつくり、モノとして残せることもZINEの魅力
「情報を自由に伝えるなら、ブログやSNSでいい」と思っていた人も、先ほどの諫山さんのお話を聞けば、考えを変えるはず。そう、ZINEはただ情報を発信するツールというわけではありません。
諫山さん「自分で手を動かしてつくるのが楽しいんですよね。内容を考えるのももちろん楽しいし、体裁で遊べるのも魅力だと思います。以前、東京芸術大学に呼ばれてZINEのつくり方や楽しさを伝える講義をしたとき、最後の5分でZINEをつくってもらったんですが、みんなイキイキとした表情で作業していましたね」
また、モノとして残せるのもSNSとは異なる点。
諫山さん「Facebookに投稿しても1〜2日で流れてしまうし、ブログをやっているからとURLを伝えても、すぐに見てもらえることは少ないですよね。でも、ZINEなら渡したその場でページをめくってもらえます。仕事に繋げようと、名刺代わりに渡して売り込みするのもありではないでしょうか」
あなたは何を発信する? 実際に制作・配布してみよう!
前述のとおり、ZINEにルールはありません。つくりたいと思ったときが、そのタイミング。手書きはもちろん、デザインソフトを使って誌面をつくるのもいいでしょう。そうやって誌面ができたら、コピーや印刷の段階へ。
諫山さん「印刷に家庭用プリンターを使う場合は、フチの余白をとらずに印刷できるモデルがいいですね。写真などを見開き全面で使うとき、余白があるとこぢんまりしてしまうので」
また、ZINEの制作には多少なりともお金がかかるので、印刷コストを抑えられるプリンターがオススメです。特に、「伝えたいことがたくさんある」「長く発信していきたい」と思うなら、この点にも注意したいところ。気兼ねなくどんどん印刷して、思い通りのZINEをつくりましょう。
さて、印刷の次は製本。『未知の駅』は、諫山さんをはじめとした数名で行っているそうです。
諫山さん「作業場所として市や区のコミュニティセンターなどを借り、メンバーはFacebookなどでボランティアを募ることが多いですね。作業工程は、刷り上がった紙面を1枚ずつ重ねていき、落丁などがないかをチェックしてからホッチキスで綴じていくというもの。1000部の製本で約2日かかりますが、みんな文化祭の準備のようなノリでやっていますよ」
そうやってつくられたZINEを配布するには、いくつかの方法があるのだとか。
諫山さん「ひとつは書店やカフェなどに置いてもらう委託販売。見本誌を持って営業に行く形です。また、“ディストロ(店舗を持たずに売り歩く人のこと)”と呼ばれる人が、代わりにいろいろな場所で売ってくれたりすることもありますね」
そんな諫山さんから、ZINE制作にあたってのアドバイスを聞いてみました。
諫山さん「最も大切なのは、締切を設けること。いつかやろうと思っているだけでは、いつまで経っても完成しません。また、どっち開きにするか、サイズはどうするかなどで悩む前に、まずは紙とペンで書きましょう。タタキ台でいいので形にすることが大切。このほか、つくる過程で行き詰まったら、いっそそのまま綴じちゃってもいいと思います。それもまたZINEなのですから」
あなたのZINE制作の頼れる味方 >>
ZINEなど…たくさん印刷する人の味方! たっぷりインクのブラザー『DCP-J983N』
ZINEで情報を発信し、形にして残したい。そう思っている方にオススメしたいのが、ブラザーの家庭用プリンター『DCP-J983N』です。
最大の特徴は、印刷コストを従来モデルの1/2に抑えたこと! A4カラー文書ならカラーインクは約2.5倍、ブラックインクは約6倍の枚数を印刷できるんです。(※)
印刷コストを心配せずに、たっぷり印刷できる『DCP-J983N』は、まさにスリラーの味方! 気になった方は、ぜひチェックしてください。