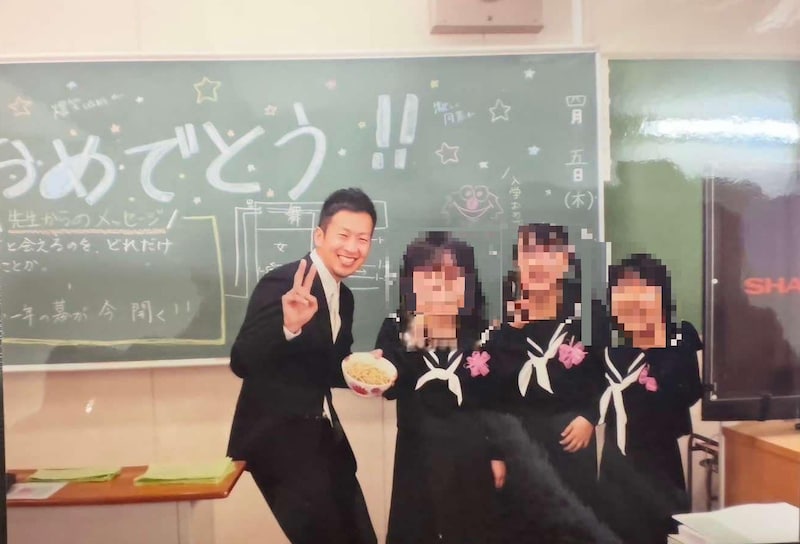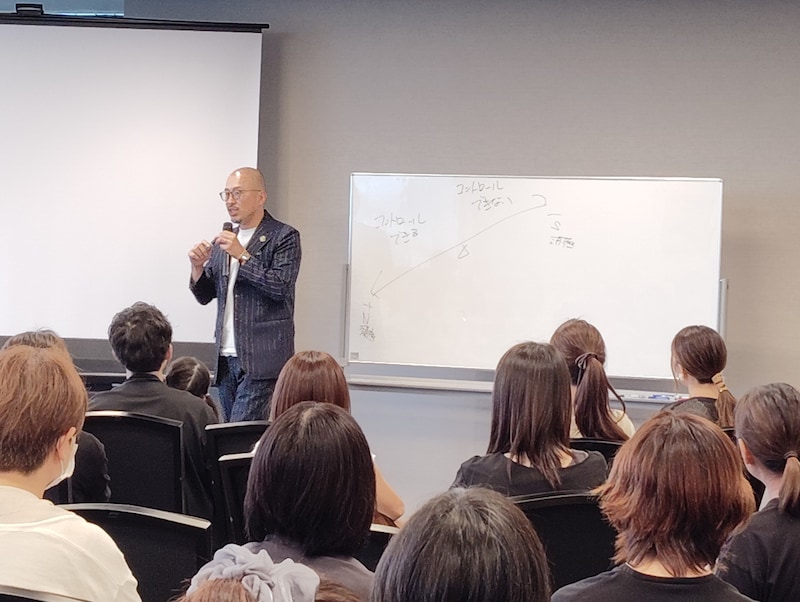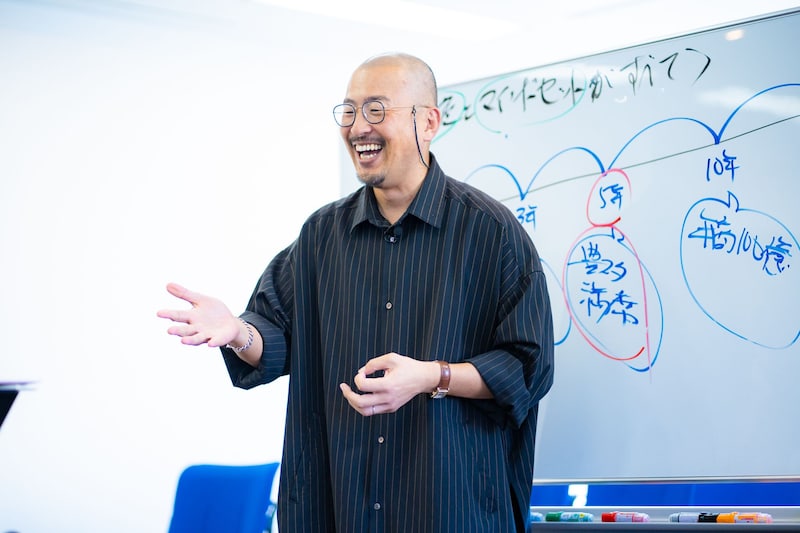今、筆者の主宰するコーチング塾には、退職予定の教員や退職された教員が多く集まってきます。こうした方々や筆者の経験から、教員のキャリアと学校現場がともによりよくなるための考え方をお伝えします。
教員は適職だと思っていたが……
筆者は、小学校・中学校の教員として約12年間勤務する中で、教員としてのやりがいを感じ、子どもたちや保護者との信頼関係を築くことに喜びを感じていました。子どもたちや保護者から信頼が得られ、職員室でも認められている実感があり、業務量は大変多い中でも教員は適職だと思っていました。転機となったのは、やったことのない学年主任と進路指導を同時に任されたときです。ただでさえ業務過多だったのが、さらに2倍になるのか……とがっくりしたのを覚えています。
しかし、未経験の担当をスムーズにこなすために、リーダーシップを学んだり、スクールに通ったりする中で、学校以外の世界を知ることになりました。また、200時間を超える残業、増え続ける業務量、それに見合わない給与、必死に働いても変わらない現状に疑問を抱き、「もっと違う形で教育に関われるのではないか?」と考えるようになったのです。
教員が学校を去っていく3つの理由
そして、自分のキャリアを考えたときに、「このまま教頭、校長へと進む道にワクワクするか?」と自問しました。答えは「NO」でした。管理職への道に魅力を感じず、学校の中で働き続けることが、自分にとっての最良の選択ではないと確信しました。
教員が学校を辞める理由は人それぞれですが、大きく分けて「労働環境の厳しさ」「キャリアパスの閉塞感」「教育方針の不一致」などが挙げられます。筆者自身も、ティーチングが基本の学校教育への違和感、管理職になる未来にワクワクできず、長時間労働や給与への不満などが積み重なり、退職を決断しました。
退職後、筆者は教育以外の世界を知ることになります。特に、ビジネスやフリーランスの世界には、これまでの学校現場とは全く異なる価値観が広がっていました。「自分で選び、自分で決める」働き方の自由度に衝撃を受けました。
「学校教育を変革したい」退職していく“ふきこぼれ教員”たち
「ふきこぼれ教員」とは、「教育を変革したいがために学校を離れた教員」という意味を包含した言葉で、大阪公立大学の伊井義人教授と時事通信社の坂本建一郎氏が研究を行い、日本教師教育学会で発表をされています。筆者が退職した当時、そんな言葉はありませんでしたが、子どもも授業も学級経営も大好きで、退職後に「ドラゴン教育革命」という会社を設立し、学校の外から教育を変えようとしていた筆者は、間違いなく「ふきこぼれ教員」でした。
そんな筆者が主宰しているからか、筆者のコーチング塾には多くの「ふきこぼれ教員」や「ふきこぼれそうな教員」が集まってきます。意欲と能力がありながらも、学校という組織の中でその力を十分に発揮できず、結果的に現場を去りたくなる教員たちです。そういった教員はよりよい教育を求めて挑戦しようとしても、その意欲を受け止める環境がなく、孤独感を抱えながら現場で浮いてしまうことが多いのです。
管理職側も受け入れる余白がないため、「やる気があるのに報われない」という状況が生じています。筆者も学校に新しい提案をした際には、「それはあなたにしかできない」と言われたことがあります。管理職の方々は、とても忙しいと思いますが、現場教員からの新しい意見をいったん受け入れ、できないと決めつけるのではなく、一緒に考えていく姿勢が重要だと思います。
教員のスキルとキャリアの可能性
教員を一生続ける人は多いですが、教員の転職や起業を見てきた立場から、「教員スキル」の市場価値についてお伝えします。なんといっても教員は「真面目さ」という最強の武器を持っています。筆者も元教員のフリーランスの方に仕事をお願いすることがありますが、「レスポンスの速さ」「仕事の丁寧さ」は抜群です。それは、教員は責任感が強い人が多く、即レスが当たり前のなかで仕事をしてきたから。学校の外に出ても、信頼して仕事を任せられる存在となります。
また、教員は「子どもに慣れている」という点も大きな強みです。転職市場では、教育現場から異業種へ移るのは難しいと言われますが、塾・教育業界など「子どもに関わる仕事」では大きな価値を発揮できます。
ただし、教員が持つスキルだけでは市場価値が高まりにくい側面もあります。例えば、5年目の先生と30年目の先生の違いを、外の世界から見たときに明確に示せるでしょうか? そこには、専門性の「積み上げ」が不足していることが影響しています。これからは、教員の真面目さに「マーケティング」や「ビジネススキル」などを掛け合わせ、付加価値を付けていくことが求められるでしょう。
しかし、筆者は決して教員を辞めさせたいわけではありません。むしろ、教育界においても社会と人材が循環する仕組みを作りたいと考えています。先生たちが学校以外の社会を知り、また現場に戻ることで、新たな視点を持って教育に関わることができる。そういった先生が増えることで、学校はもっと柔軟で、ワクワクする場所に変わるのではないかと思っています。
教員が社会とつながり、よりよい教育をしていくために
教員が社会とつながるために必要なのは、「学校の外」に目を向けることです。「学校現場だけしか知らない」「教員は社会で通用しない」と揶揄(やゆ)されることがありますが、それは大きな誤解です。むしろ、教員はビジネスの世界でも活躍できる可能性を持っています。それは教員を退職するという意味だけではなく、外の学びを活かすことでよりよい学校教育を行うことにもつながります。特に、学校教育にコーチングを取り入れることは大きな意味を持ちます。コーチングは「相手の能力を引き出す技術」であり、教員がこれを学べば、生徒の自発的な学びを促すことができます。
また、学年主任を経験して痛感したのは、「生徒を指導すること」と「担任の先生をまとめること」は全く違うスキルが求められるということです。教員はこだわりが強く、自分の教育方針を大切にしています。そのため、管理職になったときに「調和をとる力」が不足し、苦戦することが多いのです。このような現状を変えるためにも、教育の外の世界を知り、違うアプローチで関われる教員が増えることが必要です。
学校教育に携わる教員達が、学校教育をよりよくするために外からの学びを行える、そして、そこで得た学びを現場で実践できる受け入れ体制、それらがスムーズに循環することで学校教育は大きく変わります。筆者は心からそれを望んでいます。