肩こり知らずで新年スタートできましたか?

心も体も快適に新年を迎えましたか?
そのような人の首・肩・背中は、筋肉がギュ~っと縮まるように緊張を起こし、必要以上の張りが生じている可能性があります。自覚症状がない場合もあります。次の項目に当てはまる数が多い場合、首・肩・背中に緊張感を背負い込んだまま、新年をスタートさせている可能性が高いです。
■新年のスタートは快調? 年始の肩こりチェック
□思い通りの理想的な休日を過ごすことができなかった
□食べ過ぎ飲み過ぎで胃腸の調子に変化(不調気味)が出てしまった
□連休中は、予定を詰め込みすぎた気がする
□夜更かしすることが多かった
□あまり体を動かしていない
□連休中も仕事をしていた
□イライラする出来事があり気分も下降気味に
□昨年の過ごし方に心残りがある
□新年になり風邪をひいたなど、体調を崩してしまった
□今年は実現させたいことが沢山あり、目標もかなり高めに設定した
□テレビやDVD鑑賞、パソコン、ゲームをする時間が長かった
いくつ当てはまりましたか?
当てはまる項目数については次の通りです。
1~3つの人……そこそこ筋肉の緊張が高まりつつある可能性があります。肩こり、頭痛、不眠、胃腸症状など、今後の体調変化に要注意です。
4~7つの人……体の力が抜けにくくなってきているかもしれません。肩こりや背中のこりが慢性化しやすい状態に! イライラしやすくなる場合もあります。
8~11つの人……今すぐ体のメンテナンスを! 肩こりも進み疲れやすい状態で、新年をスタートさせている可能性が高いです。今年の前半でパワー切れしないためにも、早めに体の変化に目を向けてみましょう。
肩こり解消のポイント! まずはゆったりとした呼吸を心がける

連休をダラダラ過ごしてしまうと体のリズムが狂い緊張した体に!
全身的にカチコチ緊張感が高まることを予防するためには、呼吸が大切です。呼吸が浅くなっている場合が多いため、意識的にゆったりと深く呼吸をする時間をつくりましょう。仰向けに横になると、余計な力が抜けやすくなりますが、通勤電車の中や職場で、横にならずに行っても効果は出すことができます。
■ゆっくり呼吸をしてみましょう!
1. 可能であれば目を閉じて、鼻から空気を吸い込みます。もし、鎖骨の下に手を当てることができれば、呼吸による胸部の動きが分かるため、呼吸を意識しやすくなります。
2. 口から少しずつ息を吐いていきます。吐ききったら「1」へ戻りましょう。3~5回繰り返して行います。繰り返していくうちに、今まで呼吸が浅く早かったことに気が付くかもしれません。
肩こりにも効く! 簡単・脱力系エクササイズ
毎朝の習慣として続けると、緊張感を和らげて1日をスタートさせることができ、職場やお風呂上りに行うと、疲労を軽減させリラックスに導くエクササイズをご紹介しましょう。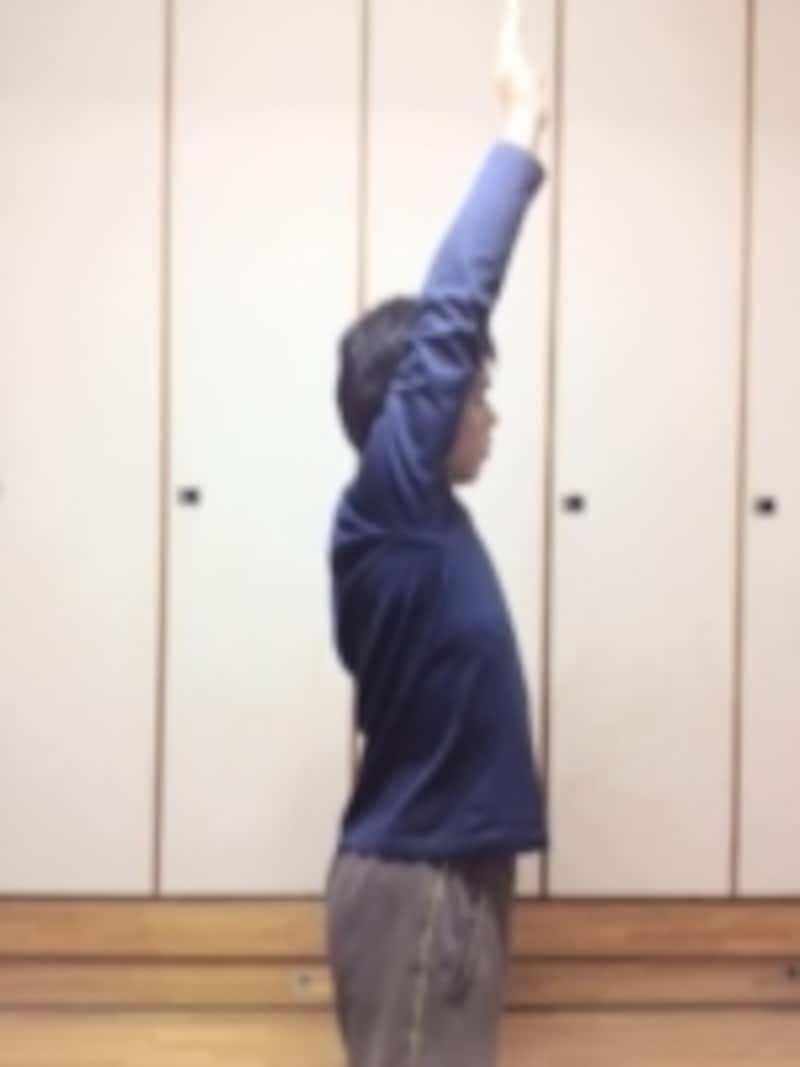
横から見たポーズです。以下後方から見たポーズに変わります。

肩こりがひどく、腕が挙がりにくい人は可能な範囲で挙げて下さい

気持ちよく伸ばされる程度が目安です。ゆっくり行いましょう。
4.同様に反対側も行います。時間が無い時は、左右1回ずつを1セットでも緊張を押さえる働きをします。時間があるときは、3~5回くらい行って体の力を抜いていきましょう。無意識のうちに力が入っていた肩周りも楽になっていきます。







