佐藤亜紀『ミノタウロス』
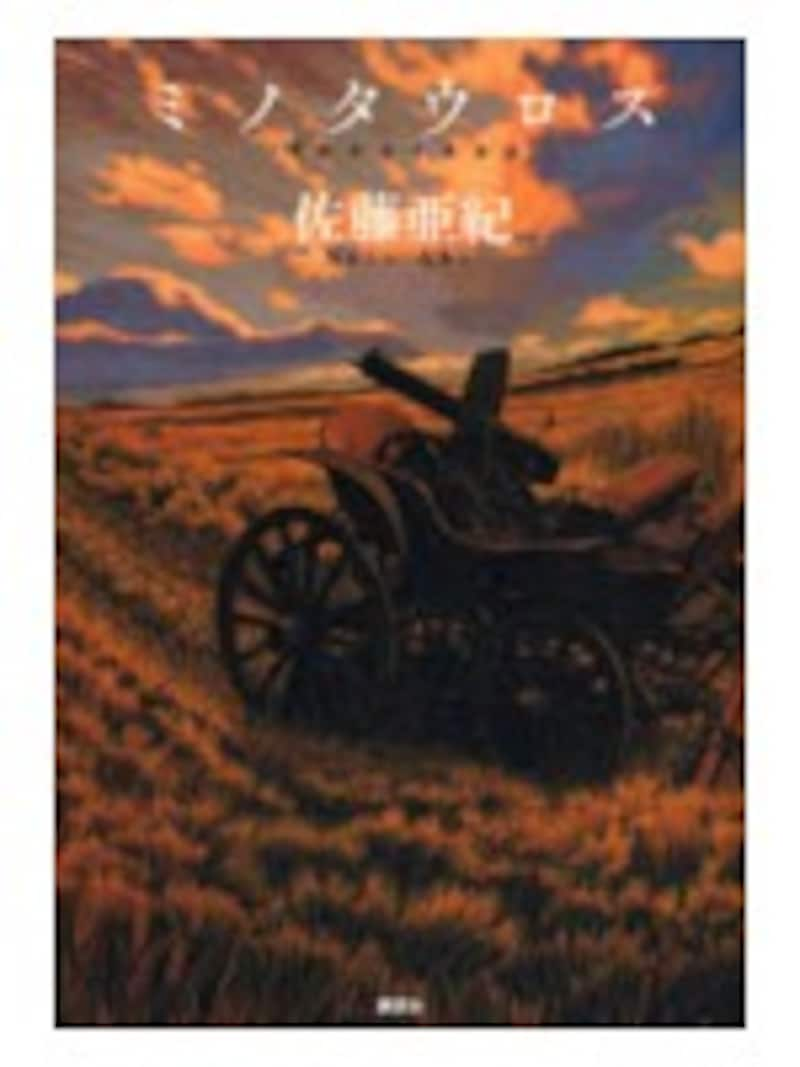 |
| 革命期のロシアを舞台にしたクールでカッコいい歴史文学。淡々としているのに迫力のある文章、ひとつひとつの場面の完成度の高さを味わおう! |
上の文章は、佐藤亜紀が絵画や芸術全般の観賞を例に出し、小説のおもしろさはどこにあるかを述べた刺激的な一冊『小説のストラテジー』から引用した。17世紀イタリアの絵画「カナの婚礼」を評した一文だ。この〈絵画〉の部分をそのまま〈小説〉に置き換えれば佐藤亜紀の作品の魅力になる。
最新作『ミノタウロス』も、どのシーンを抜き出しても筆致に迫力があり、構成の緻密な名画を見るようだ。舞台は20世紀初頭、革命前後のロシア。語り手のヴァシリは、農奴から地主に成り上がった男の次男坊。頭脳明晰な少年だが、同じような田舎地主の子はたくさんいると考え、
ぼくたちはみんな、別々の工場で同形の金型から鋳抜かれた部品のように作られる。(中略)彼の代わりにぼくがいても、ぼくの代わりに彼がいても、誰も怪しまないし、困らない。
と、うそぶくニヒリストだ。前半で印象に残るのは、彼が同級生・ポトツキの家に遊びに行った時の描写。滅びる寸前の貴族の暮らしを描いた蟲惑的な一枚の絵が思い浮かぶ。途方もない金持ちで、美貌の少年であるポトツキ。ヴァシリは自分とはまた違う意味で学校の友人から浮き上がっている彼と仲良くなるが、男色をせまられるやいなやボコボコに叩きのめす。
『ミノタウロス』レビューの続きはこちら







