この記事では、その違いがどこにあるのか、資産価値を保つための選び方のポイントを株式会社さくら事務所の山本直彌氏が解説します。まずは、知らずに選んでしまうと後悔につながりかねない、「売れにくい間取り」の典型的なパターンから見ていきましょう。
思わぬ「負動産」に? 注意すべき間取りの落とし穴
一見、魅力的でも売却時に買い手を悩ませてしまう間取り。その原因は、「検索で見つけにくい」「新生活をイメージしにくい」といった買い手の購入意欲をそぐ根本的な要因にあります。最初に挙げられるのが、現代の不動産探しにおける大きな障壁、面積と間取りの不一致です。
1LDKのマンションを、開放感を求めてリフォームし、リビングと寝室の間の壁を取り払って1つの大きな空間にしたとします。住んでいる人にとっては広々とした快適な空間ですが、不動産広告のルール上、この部屋は「ワンルーム」として扱われることになります。
問題は、家を探している人が50平米の広さで探す場合、検索条件に「ワンルーム」と入れることはまずなく、1LDKや2LDKで絞り込むことです。このミスマッチにより、本来その広さを求めているはずのターゲット層に物件情報が届かず、結果的に売却が難しくなってしまうのです。
メゾネットタイプや、いびつな形の間取りも注意
また、物件の構造そのものが、売却の足かせとなるケースもあります。その代表例が、1階と地下1階で構成されるメゾネットタイプです。メゾネットと聞くと、最上階にあるような開放的なプレミアム住戸を想像するかもしれませんが、地下階を含む場合はまったく評価が異なります。日当たりや湿気の問題、携帯の電波状況といった地下ならではの懸念点が生じ、敬遠される傾向にあるからです。同様にいびつな形の間取りも、買い手の購入意欲をそいでしまう典型例と言えるでしょう。例えば、リビングが三角形になっているような部屋は、手持ちの家具がうまく収まらず、空間を有効に使いこなすのが困難になります。
たとえ居住者が間取りの形に合わせて家具をあつらえるなど魅力的に住みこなしていても、初めて内覧した買い手が生活を具体的にイメージするのは至難の業。多くの人は、愛用している家具を新居でも使いたいと考えているため、「自分の家具が置けないかもしれない」と感じさせてしまうことが、売却の大きなハードルとなり得るのです。
買い手に選ばれる「資産性の高い」間取りとは?
では、どんな間取りが売りやすいのでしょうか。時代や流行に左右されにくい普遍的な価値を持つ間取りには、3つのキーワードが存在します。1. 王道にして最強「田の字型」の分かりやすさ
廊下を挟んで部屋が整然と並ぶ、教科書通りの間取りが田の字型の特徴です。一見すると特徴がない、と感じるかもしれませんが、実はその普通さこそが最大の強み。
誰が見ても部屋の用途を直感的に理解でき、家具の配置にも困りません。中古マンション市場では、内見は1回か2回で決断を迫られることも珍しくないため、こうした分かりやすさは買う側の判断を助け、スピーディな売却につながります。
2. 家事動線がスムーズになる「回遊性」の高い間取り
キッチンから洗面室へ抜けられる「2WAY動線」に代表される、家の中をぐるりと回れる回遊動線も、近年高評価を集める間取りです。行き止まりがない動線は、日々の家事効率を劇的に改善してくれるため、特に多忙なファミリー層から絶大な支持を集めています。
さらに希少価値が高いのが、住戸内をぐるりと一周できる完全な周遊型の間取り。このタイプは、家事動線が便利なだけでなく、来客時の動線を分けやすいという大きな利点を持ちます。
例えば、家族がくつろぐリビングを通過させることなく、玄関から直接ゲストルームへお客さまを案内できるため、プライバシーを保ちやすいのです。こうした付加価値の高さから、「この間取りだからほしい」という指名買いにつながるケースも少なくありません。
3. 家族と共に成長する「可変性」のある間取り
ライフステージの変化に柔軟に対応できる「可変性」も、現代の重要なキーワードです。
例えば、リビング横の部屋を可動式のスライディングウォールで仕切るタイプ。普段はウォールをすっきりと収納して広々としたリビングとして使い、子どもが成長したら壁を作って個室にする。そんな変幻自在な使い方が、家族の未来のニーズに応えてくれます。一部屋で二役も三役もこなせる柔軟性が、資産価値を力強く支えます。
残念な間取りは諦めるべき? 流動性を上げる売り方の工夫とは
では、人気がないであろう間取りの物件は、諦めるしかないのでしょうか。必ずしもそうとは限りません。なぜなら、不動産の価値は現在の間取りだけで決まるのではなく、将来どれだけ柔軟に変化できるかというポテンシャルも関係してくるためです。幸い、現在多くのマンションは、それが可能な構造で建てられています。すると、多くの方はこう考えるかもしれません。「リフォームで変えられるなら、きれいに直してから売るべきでは?」と。しかし、売却における考え方はその真逆。原則として「リフォームしないで売る」が、実は賢い選択と言えます。
背景にあるのは、リフォーム費用も住宅ローンに組み込めるようになった、という資金計画の大きな変化です。
買い手にとって物件を素材として、内装は自分たちの好きなように作り上げる、という選択肢を無理なく選べるようになりました。だからこそ、売り手がよかれと思って費用をかけたリフォームも、買い手の「自分らしく暮らしたい」という思いと食い違えば、評価されにくくなってしまいます。自由にできる可能性をそのまま残しておくことこそが、選ばれる間取りに不可欠なのです。
個性的な間取りを売る場合は、買い手の想像力を手助けする
ただし例外もあります。三角形のリビングなど、個性的で買い手が使い方を想像できない間取りの場合です。買い手は、平面的な間取り図だけでは、なかなか具体的な生活をイメージできないでしょう。そこで売り手が、その想像力を手助けしてあげる必要があります。例えば、現在の間取りを生かす方法として効果的な家具を配置し、空間を有効活用できる具体的な“暮らし”を提示するのも一案です。さらに「この壁を動かせば3LDKとして利用できる」といった将来の可能性を、CGや立体イメージ図を用いて視覚的に示すことも有効な方法となります。こうした工夫によって、買い手は将来のライフスタイルを具体的に描けるようになるはずです。
将来にわたって価値が落ちない間取りの条件
このように、間取りの資産価値はその形だけでなく、時代の変化や売り方の工夫によっても大きく左右されます。そして住まい選びは、未来への投資です。その価値を測る上で、間取りは極めて重要な指標になることもお分かりいただけたと思います。では、資産価値を保ち続ける間取りに共通する本質とは何でしょうか。それは次の3つの条件に集約されます。
- 誰もが見つけられること(検索性・分かりやすさ)
- 暮らしの変化に強いこと(可変性・柔軟性)
- 買い手が自分ごとにできること(想像のしやすさ)
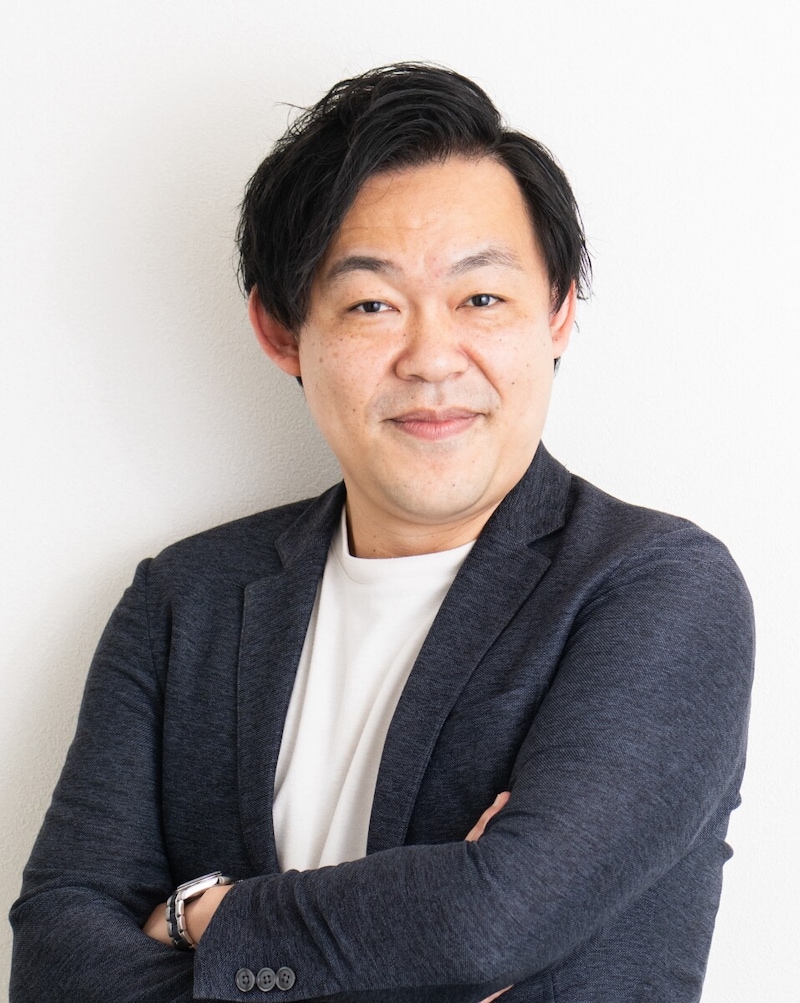
株式会社さくら事務所・取締役副社長 COO 山本氏
マンション・ビル管理、不動産仲介の経験を経て、マンション管理コンサルタント・不動産エージェントの業務に従事。これまでに50棟を超えるマンション管理フロント業務、500件以上の不動産仲介を経験。2020年4月 株式会社さくら事務所へ参画。2025年にさくら事務所・取締役副社長COO、同年、グループ会社のらくだ不動産株式会社・取締役副社長COOに就任。自身が取材協力した「マンションバブル41の落とし穴」(小学館)が発売中。






