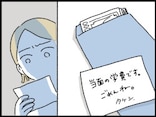このところ、「さす九」という言葉がSNSでトレンド入りするなどして話題になった。
これは「さすが九州」を縮めたネットスラングで、主に男尊女卑など九州のネガティブイメージを増長させるものとして九州出身者からは「地域差別」という声も上がっている。一方で、九州出身で「脱出組」の女性たちからは、「出てみて初めてよく分かった。男尊女卑は確かにひどかった」という意見もある。
男尊女卑は九州に限った話ではない
良くも悪くも地域愛が強い場所には見られる傾向であり、もちろん九州に限った話ではないのだ。もともと長男を特別視するのは家の存続が重要だった大昔からの習性だったのだから。東京のように日本全国から人が集まる場所には、郷土愛は育ちにくい。地方には地方なりの郷土愛があり、それが家の存続を願うための「長男重視」につながっていくのだろう。
実際、都道府県別のジェンダー・ギャップを見ても、特に九州がひどいというわけではない。
一方で、男尊女卑あるいは女性の人権が守られていないことに限っては九州だけの問題ではなく、日本全体の問題である。
2024年の日本のジェンダー・ギャップ指数は146カ国中118位。経済や政治、どの分野をとっても情けないほどに後進国である。多くの国が緊急避妊薬を処方箋なしで買えるのに、日本では少なくともオンライン診療を受けなければ手に入れることはできない。しかも価格は1万円前後。数百円、もしくは無料でも手に入れられる国が多い中で、この国では女性の「生殖に関わる自己決定権」が圧倒的に抑圧されているのが現状だ。
人は自分が住んでいる地域の価値観の中で育っていく。それが当たり前だと思い込む。だから今回の「さす九」問題で、九州を揶揄(やゆ)されていると感じて憤る人がいるのも当然だろう。ただ、もっと違う価値観があると知ることも重要なのではないだろうか。
九州に限らず、「クソみたいな価値観」から脱却した女性たちの意見を聞いてみた。
離婚したら「帰ってくるな」と言われた(九州/40代)
15年前、夫のモラハラで離婚しました。結婚したら仕事を辞めるのが当然という夫だったので、それに従って専業主婦になったけど、当時2歳の子を抱えて離婚したこともあって困ってしまい、とりあえず実家に戻ろうと思ったら、親から「離婚したなんてみっともないから帰ってくるな」と言われました。「おまえがダンナを立てないから怒られてばかりいたんだろう」とも……。こうなったら自立するしかないと子どもを抱えて大阪へ。とりあえずは水商売に飛び込み、必死で働きました。もちろん、大阪でも男性から下に見られていると感じることは多々あったけど、「家を中心にものを考えるべき」という価値観からは解放された。
子どもが小学校に入るのを機に仕事を変え、今は営業職で頑張っています。子どもも今年から高校生。親とはあれきり連絡をとっていませんが、心配してくれるいとこが、それとなく私たち親子が元気でいることは伝えてくれているようです。
「家」が重要なのではなく、個人の生き方が重要なのだと知ることができてよかったと思っています。
女は大学に行かなくていいと兄を優先(北陸/30代)
子どものころから勉強が好きだったけど、両親は私より勉強のできない兄ばかり大事にしていました。県で1番の高校に進学したのに、両親は「女の子なんだから大学へは行かせられない」と。父の妹である叔母が、「私が学費を出してあげる」と言ってくれました。独身の叔母は東京で仕事をしていたから、「兄(私の父)夫婦の感覚は古すぎる」と擁護してくれたんです。私は両親に黙って東京の大学を受験し合格。その時初めて、「東京の大学へ行く」と宣言して上京しました。父は自分の妹に相当文句を言ったようですが、叔母は「あの子は私が引き受ける」と言い張ってくれました。
そのまま東京で就職して結婚。共働きをしながら子どもを育てています。あのまま地元にいたら、私は進学もできずに就職して、地元の男性と結婚していたんでしょうね。母と同じように舅姑に仕える人生が待っていたんだろうと思うと、叔母には心から感謝しています。
メディア関係に女性が少ない(九州/40代)
フリーランスのメディア関係者です。普段は東京で活動していますが、時々出身県にも取材に行きます。いまだにメディア関係は女性が少ないし、新聞もテレビも男性ばかり。私が取材に行くと、「なんだこの女」という目で見られ、場を仕切っている男性から肘鉄を食らったこともあります。「痛い!」と大きな声で言ってやったら、睨まれました。見慣れない人物は排除しようという雰囲気を感じるんですよね。
東京の記者会見などだと、テレビは後ろ、他のメディアは前の方と決まっているんですが、地方だとそういうコンセンサスがない。地元テレビ局がやけにエラそうにしているのが目につきます。
一方で、女性起業者が多いのも特徴的です。それも社員が1人か2人の会社。当事者に聞いたら、企業内での出世が見込めないので独立する女性が増えているそう。だからといってフリーランスで活動できる下地がない。だから起業する。自治体も女性起業家は応援してくれるそうです。起業家となると、周りの見方も変わるとか。
それでも既存の企業の「おっさん」たちから嫌がらせされることもあるらしい。自治体の取り組みは手厚いけど、実態は女性が苦労しているように見えますね。
地域性なのか世代なのか
場所によるのか世代によるのか、はたまた両方が組み合わさると強烈になるのか。いずれにしても女性たちがあちこちで不快な思いをしているのは事実である。<参考>
・「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」公表(NHK)
・「GGI ジェンダー・ギャップ指数」(男女共同参画局)