「あんまり客の多くないバーを教えてもらえませんか」
はてさて。客が多くなければ店は立ち行かないではないか。困った。私は冷たく無視する訳にもいかないから、「普段よくいかれる店を挙げてみてくださいませんか」と一応は聞いてみた。
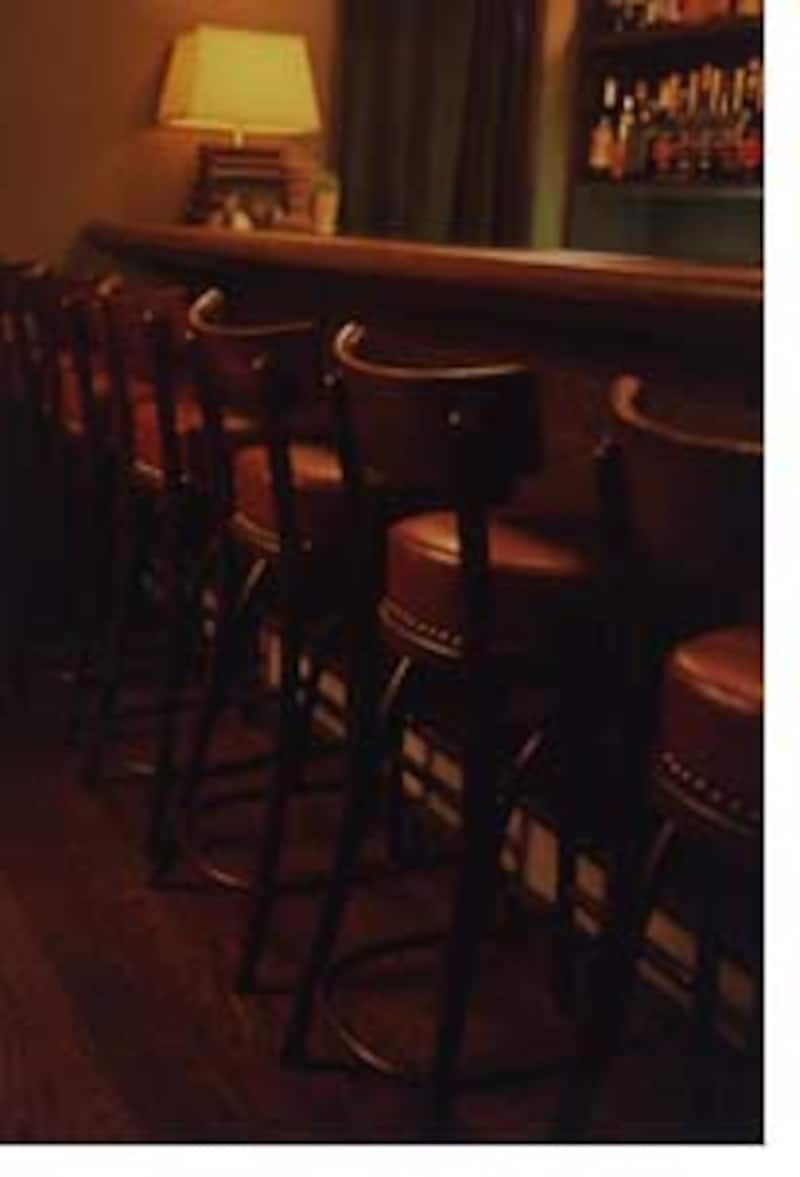 その人は四つほど店の名を挙げたが、ひとつだけ私が二度ほど行ったことのあるバーの名があった。なるほどである。たしかにそこは客が少ない。というより少なかった。あんまり客がこないものだからこの1月末で閉店となった。その人はそれを知らなかったようである。それを告げるとひどく残念がった。
その人は四つほど店の名を挙げたが、ひとつだけ私が二度ほど行ったことのあるバーの名があった。なるほどである。たしかにそこは客が少ない。というより少なかった。あんまり客がこないものだからこの1月末で閉店となった。その人はそれを知らなかったようである。それを告げるとひどく残念がった。「どうして閉店しちゃったんだろう。誰も知らなくて、客がいなくてよかったのに」
まいった。「だからあ」と言いたいところを我慢して、私は精一杯の優しさを見せて説明してあげた。
「あそこのオーナーは、飲食業界の人じゃなかったんです。つまり道楽。知り合いの不動産会社から、地下のフロアが空いてて困ってるから、なんかやってもらえないかと頼まれて、興味本位にはじめたんだそうですよ。よく2年持ちましたよ」
こう説明しても彼はただ溜め息をつくだけだった。
その店はたしかに静かだった。私は知り合いの編集者に二度とも打ち合わせができるバーとして連れて行かれた。3時間いて、編集者と私だけだった。若いバーテンダーのカクテルの味は教科書通りの可もなく不可もなくといったものだった。ウイスキーはそこそこの品揃えで、私はウイスキーばかりを飲んだのを覚えている。内装だけはとても立派だった。
悲しい常連客
こういう人もいれば、「どうせ、自分の最も大切な店は紹介しないんでしょう」と言われることがある。これもまいったである。私は芸能人じゃないからこそこそする理由もなければ、それにたかだかバーである。そしてされどバーである。何を隠すことがあろうか。出かけた店でよさそうなら、ガンガン紹介する。ただ考えることはひとつ。インターネットだろうが、雑誌だろうが、媒体として合致しているかどうかは悩む。
隠れ家的でいいという人がいても、どこか私の波長と合わなければ紹介しない。それだけのことだ。
紹介する時は店主にきちんと内容説明して、日時を決めて取材に行く。原稿を書いたらチェックしてもらう。それだけのこと。教えたくないバーもたしかにあるが、店主がOKなら紹介する。
だから時折、恐ろしく悲しい言葉を受けることがある。(次ページへつづく)






